大腸がんの「骨盤内臓全摘術」治療の進め方は?治療後の経過は?

- 絹笠祐介(きぬがさ・ゆうすけ)先生
- 静岡県立静岡がんセンター 大腸外科部長
1973年東京生まれ。98年、東京医科歯科大学医学部卒業後、同大学腫瘍外科教室に入局。2001年より国立がんセンター中央病院下部消化管外科勤務、05年、札幌医科大学にて骨盤解剖学の研究に従事。06年より静岡県立静岡がんセンター勤務、07年東京医科歯科大学・大学院腫瘍外科学分野修了。10年より現職。日本外科学会専門医。日本消化器外科学会専門医。日本大腸肛門病指導医。日本内視鏡外科学会技術認定医ほか。
本記事は、株式会社法研が2012年6月26日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 大腸がん」より許諾を得て転載しています。
大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。
骨盤内まで広がったがんを周囲の臓器ごと切除する
がんが大腸を突き破って広がったときに行われる手術です。浸潤(しんじゅん)した可能性のある臓器をすべて切除することで、再発がんや他臓器浸潤がんでも根治が期待できます。
がんが広がっていても取りきれるなら手術をする
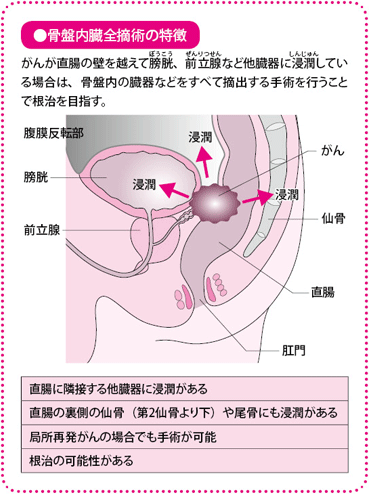
当施設は、がん専門病院という特性からか、がんがかなり進行してから受診する患者さんが多い傾向にあります。そのなかには、ほかの病院ですでに「手術は不可能」といわれた患者さんも含まれています。
がんが他臓器に浸潤しているような進行がんの患者さんに対しては、大腸を腸間膜ごとリンパ節切除する通常の手術(TME)ではもう意味がなく、がんが広がってしまっている周辺の臓器を丸ごと摘出する拡大手術が必要となります。これを「骨盤内臓全摘術」といい、この手術によって、かなり進行したがんであっても根治を望むことができます。
大腸がんの治療法には、抗がん薬による化学療法や放射線療法などもありますが、手術以外の治療では延命は望めても根治は期待できません。そこで、大腸がんに対しては、私たちはできるだけ「限界をつくらずに手術を行う」と考えて治療にあたっています。それが専門病院としての役割であるとも考えています。
骨盤内の臓器を根こそぎ取ってしまう骨盤内臓全摘術は、長時間にわたる大手術で、患者さんの体力や全身状態がよくなければできず、また手術の難易度が非常に高く、合併症に対応する知識や経験も必要なため、高度な技術をもつ治療チームの存在が必要です。そのため一般の医療機関ではあまり積極的には行われていません。そこで、手術はできないとあきらめてしまう患者さんも少なくないと思います。
しかし、それでもあきらめずに当施設を受診する患者さんに対しては、十分な検査を行い、骨盤内臓全摘術による治療が可能である、または排尿・排便機能を温存して骨盤内臓器の摘出を行えると判断した場合に、この手術を提案し、積極的に根治を目指します。
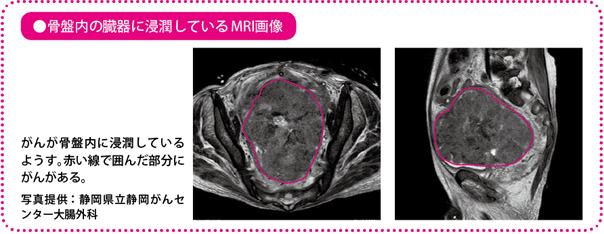
大きな手術が「できる・できない」の基準とは?
直腸がんに対する骨盤内臓全摘術には、大きく分けて「骨盤内臓全摘術」と「仙骨合併骨盤内臓全摘術」の2種類があります。
前者は骨盤内にある臓器、直腸と膀胱、尿道、男性なら前立腺、精のう、女性なら子宮と膣(ちつ)をすべて摘出する手術です。それに加えて仙骨を一部削るのが後者で、直腸の裏側(仙骨周辺)にがんが広がっているときなどに行われます。
骨盤内にある臓器や組織の一部を残す場合は、骨盤内臓全摘術といわず、他臓器合併切除(直腸切除+子宮全摘、あるいは膀胱部分切除など)と呼んでいます。肛門(こうもん)は括約筋(かつやくきん)などの機能を一部残せる場合(ISR)と、まったく残せない場合とがあります。
この骨盤内臓全摘術を行えるかどうかには、患者さんの体力などいくつかの条件があります。
この手術は、根治が期待できる反面、切除する範囲が大きく、排便、排尿、生殖にかかわる機能など失うものも少なくありません。したがって、手術にあたっては、患者さんや家族の方に納得して同意してもらうことが不可欠です。
臓器を切除した場合、どれだけ日常生活にかかわる機能が損なわれるのかを検討し、術後の日常生活にきたす支障の程度や、機能が失われる場合の対処法などをしっかり話し合ったうえで、選択してもらうことになります。
●手術の適応
| ・大手術(全身麻酔)に耐える体力があり、基礎疾患がない |
| ・がんが第2仙骨より下にある |
| ・骨盤側壁にがんが広がっていない |
| ・肝臓、肺に転移がないか、あっても切除可能な場合 |
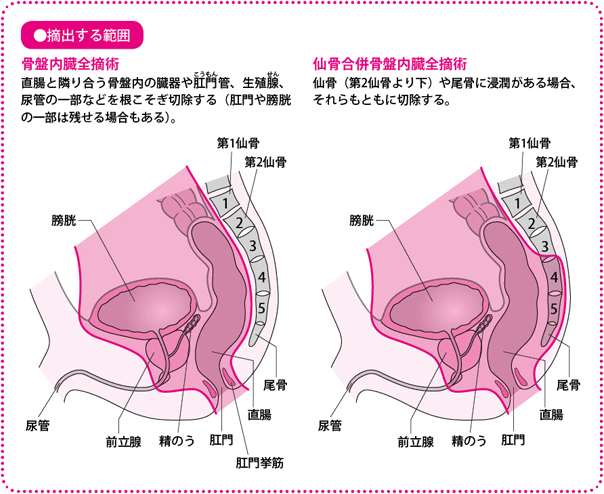
治療の進め方は?
おなかを切開したあと、直腸の上、背中側、おなか側、下の4方向から少しずつ骨盤内の臓器を剥(は)がしていきます。大変難易度が高い手術で、10時間以上かかることもあります。
手術時間は通常で10時間 再発がんの手術なら12時間
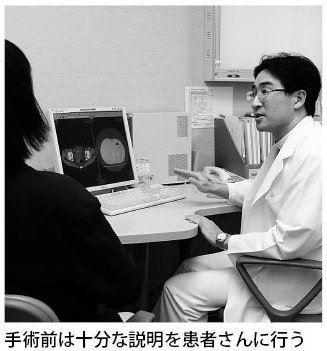
手術の基本的な流れは、一般的な開腹手術と同様です。摘出する臓器が多いので、長時間の手術になります。
まず、全身麻酔をした患者さんのおなかを切開し、腸を覆う膜を剥がしながら奥に進みます。直腸の上(結腸側)の裏側(骨盤側)をゆっくりと仙骨から剥がしていきます。直腸の裏側の処置が終わったら、口側の直腸を切除します。次におなか側の処置に移り、膀胱、生殖器(前立腺、子宮など)をおなかから剥がします。
最後に、直腸の下(肛門側)を肛門ごと切除します。肛門を残す場合は直腸と肛門の境目を切り離します。このように、上、裏、前、下の4方向からアプローチして、少しずつ骨盤内から臓器を切り離します。
この手術で注意しなければならないのは、出血です。骨盤内には大腿部(だいたいぶ)や裏面に向かって太い血管が走っています。それらを傷つけると大出血がおこる可能性もあります。腸や臓器に栄養を送る細い血管は、臓器の切除とともに不要になるので、一つひとつ止血処理しながら切除していきます。こうした細かい作業を行うことで、大がかりな手術であっても安全に施行することが可能です。
骨盤内臓全摘術は、すでに手術を一度行った再発がんの場合にも行われることがあります。再手術では、おなかをあけたときに組織どうしがくっついて硬くなる癒着がおこっているため、通常の剥離(はくり)層ではうまく剥離できないことが多くなります。その場合、がんの取り残しがないように、以前の切除範囲よりひと回り外側を剥離していくことになり、一度目の手術よりもかなり難しい技術が必要となります。
手術歴がない患者さんでは、手術時間は10時間程度ですが、再発がんでは難易度が高くなるので12時間以上かかることもあります。
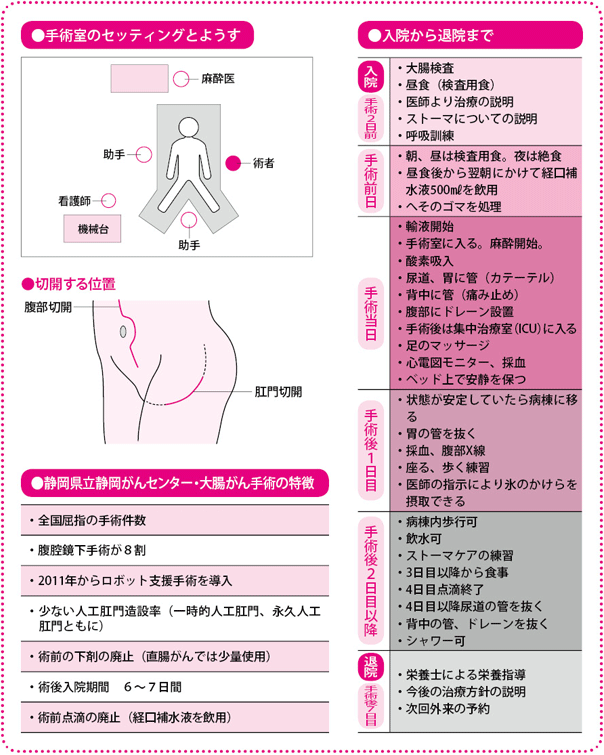
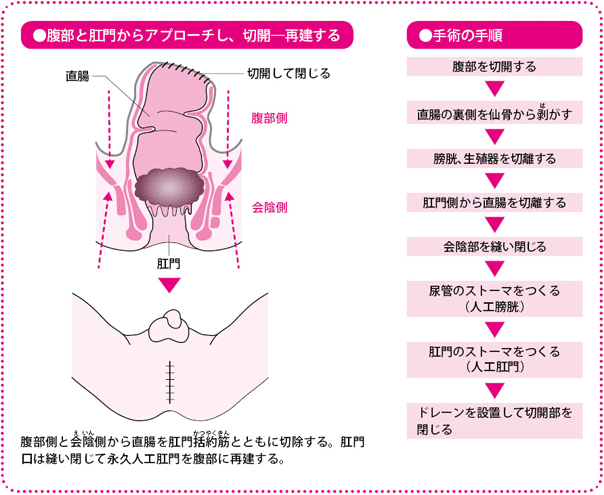
入院日程は通常の開腹手術と変わらない
退院までの日数は、通常の開腹手術と変わりありません。患者さんの回復の程度にもよりますが、およそ2週間の入院となります。
具体的なスケジュールはまず、手術2日前に入院し、検査を受けます。下剤(ピコスルファートナトリウム水和物:商品名ラキソベロン、シンラックなど)は直腸がんでは10mLほど飲んでもらいますが、結腸がんでは飲まずに手術を受けてもらいます。
下剤を飲むのは、便が残ったまま手術をすると縫合不全がおこりやすいと考えられていたからです。しかし、海外では、下剤を使用した場合と使用しない場合とを比較しても縫合不全の発症率には影響がないと報告されています。
下剤の服用は患者さんの負担も大きいことから、現在は、できるだけ用いない方針で臨んでいます。実際に下剤を使わなくとも、静岡がんセンターでの縫合不全率は非常に低いです。
排便と排尿を人工的に行うダブルストーマ
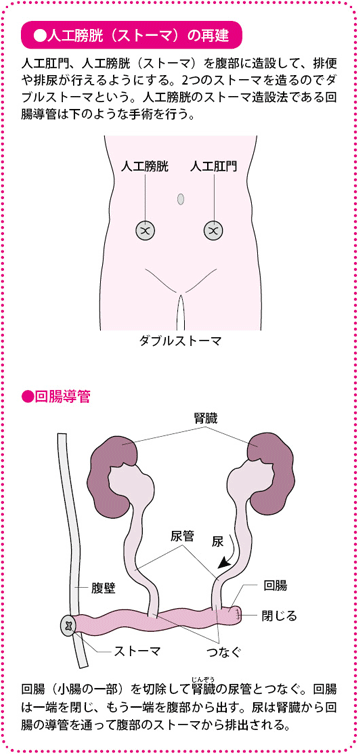
骨盤内臓全摘術では、膀胱や前立腺、子宮といった臓器を丸ごと切除するため、排便機能や排尿機能、性機能が損なわれることは避けられません。特に、人工肛門と人工膀胱(これをダブルストーマといいます)の造設が必要になる場合は、排泄について患者さんの生活は大きな影響を受けます。最近では肛門を残す骨盤内臓全摘術も行われていて、これまでで、4割に肛門を温存できています。どうしてもそれが難しい場合はダブルストーマを選択せざるをえません。
人工肛門や人工膀胱を造設する場合は、入院した日や手術前日に説明をして、手術後2日目から看護師のつきそいのもと、人工肛門や人工膀胱の洗浄や装具を交換する訓練を行い、徐々に扱いに慣れてもらうようにしています。
脚のつけ根の神経やリンパ節は温存できますので、脚がむくむリンパ浮腫(ふしゅ)や脚のしびれ、歩行困難といった合併症はほとんどありません。
治療後の経過は?
定期検査は3~6カ月おきに受けます。
進行がんでみつかった場合の手術ではおよそ7割、遠隔(肝臓や肺)転移がなければ約9割の患者さんが、再発なく根治できています。
全国平均より低い合併症 定期検査は3~6カ月ごとに

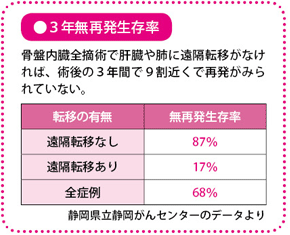
当施設では直腸がん手術後の合併症である縫合不全は3.4%(2007年以降のデータによる)です。さまざまな工夫をしているので、全国の専門病院に統計をとった平均である10~12%よりかなり低く抑えられています。しかも、縫合不全を予防する一時的人工肛門はほとんど造っていません。
一般的な合併症のほかに、骨盤内臓全摘術では術後の深刻な合併症(骨盤膿瘍(のうよう)症や骨盤死腔(しくう)炎など)をおこしやすく、術後は慎重な経過観察とケアを行っています。
退院後の定期検査は、通常の診察と腫瘍(しゅよう)マーカーの測定を3~6カ月ごとに行います。腫瘍マーカーとは、がんが再発すると高くなるたんぱく質で、血液検査で調べることができます。当施設ではCEA、CA19‐9の2種類の腫瘍マーカーを測っています。
このほか、胸部X線検査あるいは胸部CT検査、腹部超音波検査あるいは腹部CT検査を6カ月ごとに受けてもらいます。必要に応じてPET検査を追加します。大腸内視鏡検査は手術の2年後まで年1回続けます。これらの検査で、局所再発や肺や肝臓への遠隔転移の有無を調べます。
●骨盤内蔵全摘術に多い合併症
|
出血 ・吻合(ふんごう)部出血、腹腔(ふくくう)内出血 |
|
感染症 ・創(そう)感染、骨盤内膿瘍(のうよう)、骨盤死腔(しくう)炎(直腸切断術や骨盤内蔵全摘術で会陰部に創(きず)がある手術でおこる) |
骨盤内の解剖を熟知しないとできない手術
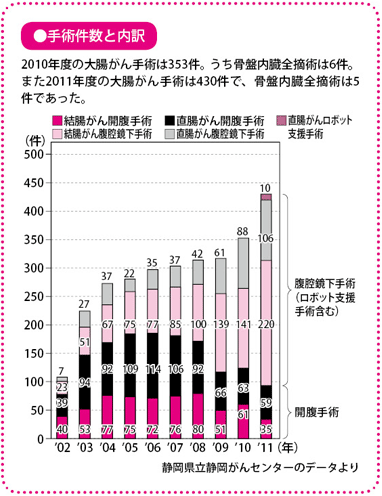
骨盤内臓全摘術に関して当施設での成績をみると、開院してからの年数になるので、まだ十分なデータとはいえませんが、原発巣(げんぱつそう)では、およそ7割が根治しています。特に遠隔転移を伴っていない患者さんの場合、3年経過しても再発を認めていません。これらの患者さんが骨盤内臓全摘術以外の治療法を選択した場合には、平均余命(6~12カ月)をどれだけ延ばせるかということが治療の目標となります。しかし、この手術を行えば、余命ではなく、寿命をまっとうすることができるのです。
骨盤内臓全摘術はどこの医療機関でもできるような手術ではありません。骨盤内の解剖を熟知し、十分な経験と高度な技術をもつ外科医でなければ、期待する結果は得られないといえます。
当施設のようながんを専門とする医療機関など、骨盤内臓全摘術の実績がある医療機関を選ぶことが大切です。
大腸がんでもロボット支援手術が始まる
日本では2009年から大腸がんのロボット支援手術
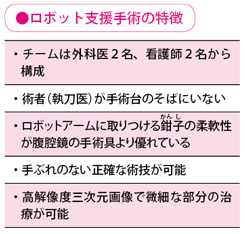
前立腺がんなど一部のがんの治療ですでに行われている「ロボット支援手術」が、大腸がんに対しても普及しはじめています。
大腸がんでの最初のロボット支援手術は、2009年に藤田(ふじた)保健衛生大学病院によって実施されました。当施設に手術支援ロボットが導入されたのは2011年9月末で、同年12月22日に直腸がんの第1例目を成功させました。現在までに16例実施し、いずれの患者さんも元気に退院されています。
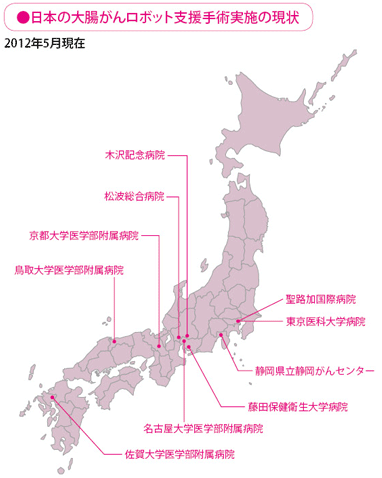
手の動きを忠実に再現した装置が手術を行う

ロボット支援手術とは、術者の手の動きを忠実に再現した手術支援ロボットのダヴィンチ(da Vinci)が、執刀医に代わって手術を行うもので、2001年にアメリカの医療機関が前立腺がんの手術に試みたのが世界初になります。もともとは戦場で傷ついた兵士の治療を遠隔操作で行うために開発されたもので、同国ではすでに1500台余のダヴィンチ装置が稼働、前立腺がんの手術の85%以上がロボット支援手術になっています。
わが国では2006年に東京医科大学病院がこの装置を導入し、現在は45台の装置が全国の医療機関(40施設)に設置されています。前立腺がんでは保険診療として認められていますが、大腸がんではまだ認められていません。このため、大腸がんでロボット支援手術を行う場合は、自費診療になります(医療機関によって金額は異なる)。
メリットは操作が楽で精度の高い治療ができること
ロボット支援手術では、執刀医である術者は手術台のそばにいません。そこが従来の手術と大きく違うところです。術者は手術台から離れた高さ1.5mほどのボックス(サージョンコンソール)に座り、カメラが映し出す画像を見ながら、そこに設置された器具を使って手術を進めていきます。
手の動きは、そのまま手術台の上に設置された手術装置(サージカルカート)に伝わり、実際の手術として反映されます。つまり、ロボットの手を借りて、術者の手術が再現されるだけで、手術の内容は、開腹手術や腹腔鏡(ふくくうきょう)下手術で行われているものとなんら変わりはありません。
しかし、ロボット支援手術では、顕微鏡的な手技も可能で、「2mmの血管が縫える」といわれるほどの細かい作業が可能になります。
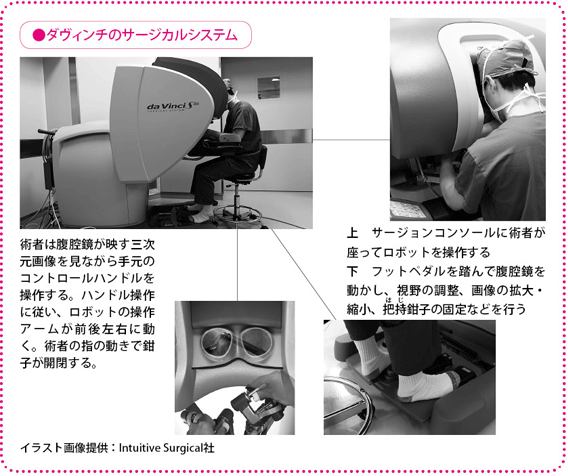
人間の手より多い関節でなめらかな動きが可能に
ロボット支援手術は、腹腔鏡下手術と同様、カメラが映し出した患部の画像を見ながら手術を進めます。画像は高解像度・高倍率の3D画像として映し出されるので、腹腔鏡とは違って奥行きをしっかりと感じながら操作を進めることができます。また、ロボット支援手術で用いる器具は人間の手より関節の数が多く、360度自在に曲げることができ、自由に方向を変えられるので、腹腔鏡下手術で用いる器具では難しかった、腸の裏側の剥離作業なども簡単に行うことができます。
手術台の周囲では、ロボットのアームを動かしたり、患者さんの体位を変えたりする助手が必要ですが、基本的な手技となる腹腔鏡やほかの治療器具はすべて術者一人で操ることができます。
腹腔鏡下手術と同じく、複数の小さな孔(あな)(約8mm)から手術器具を挿入して治療を行うので、患者さんの体に優しく、術後の回復が早い点もメリットでしょう。
操作次第では大きな危険を伴う
しかし、ロボット支援手術に問題点がないわけではありません。まず、触感がないこと。触っている感触は術者にはまったく伝わらないので、画面からはずれていると鉗子(かんし)などの手術器具がどんなものに触れているのかわかりません。一歩間違えば、血管や臓器を刺したり切ったりしてしまい、大出血につながる危険性があります。操作する器具は絶対に視野に入れておくなど、守るべき原則が厳しく設けられています。
このため、専用施設で一定期間のトレーニングを受け、認定された医師でなければ、治療を行うことはできません。また消化管のロボット支援手術では、術者が腹腔鏡下手術に慣れている必要もあります。
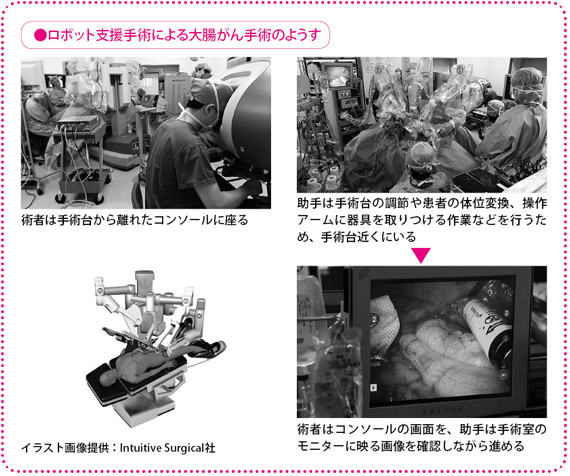
費用の高さが大きなデメリット
いちばん大きな問題点はコストです。装置も高価ですが、健康保険が適用されていない今は、手術費用も100万円以上になります。そのため当施設では、このロボット支援手術を、通常の腹腔鏡や開腹手術では難易度の高い直腸がんに限って行っています。
いずれにしても、ロボット支援手術については開腹手術や腹腔鏡下手術と比較した成績の検証を行ったうえで、利点を最も生かせる臨床例を見極めることが今後の課題といえます。

