がん相談スペシャルーがん闘病中の患者さん・家族が抱える「心の痛み」について腫瘍精神科医が回答
がんの疑いと言われた時から、検査、診断、告知、治療、再発など、次々と起こる出来事に対し、がん患者さんは「心の痛み」を抱えています。がん患者さんをサポートする家族も不安を抱えています。がんで家族を亡くした遺族も、気持ちの整理がなかなかつかず、悩みを抱えています。がん闘病中の不安や悩みを誰に相談したら良いのか、どのような対処法があるのか――。「がん闘病とこころ」に関するさまざまな相談について、がん研有明病院腫瘍精神科の清水研先生に回答していただきました。
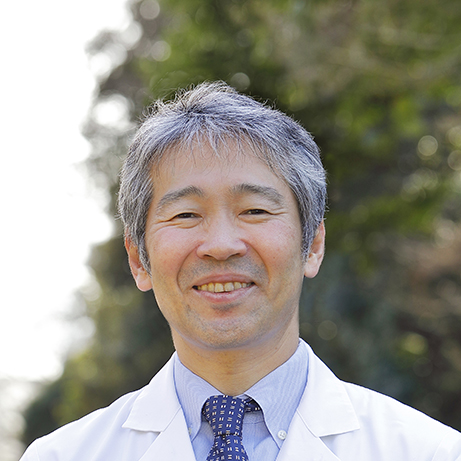
プロフィール
がん研有明病院腫瘍精神科部長、精神科医、医学博士
1971年生まれ。金沢大学卒業後、内科研修、一般精神科研修を経て、2003年より国立がんセンター東病院精神腫瘍科レジデント。以降一貫してがん医療に携わり、対話した患者・家族は4,000人を超える。2020年より現職。日本総合病院精神医学会専門医・指導医。日本精神神経学会専門医・指導医
2021.11 取材・文 がん+編集部
- Q がん闘病者自身が抱える、さまざまな悩みや不安(治療・お金・仕事など)は、誰に相談すれば良いでしょうか?
- Q がん治療中の不安を少しでも軽くするために、がん闘病者本人ができることはありますか?
- Q がん患者さんの心を支えるために、家族にできることはありますか?
- Q がん患者さんに精神症状が起こったとき、家族にサポートできることはありますか?
- Q がん患者さんに「がんばって」と声をかけても大丈夫でしょうか?
- Q がんで家族を亡くし、もっと何かできたのではないのかという後悔や罪悪感が消えません。誰に相談すればいいでしょうか?
- Q がんに伴う精神症状を専門とする腫瘍精神科/精神腫瘍科とは、どんな診療が受けられるのでしょうか?
Q がん闘病者自身が抱える、さまざまな悩みや不安(治療・お金・仕事など)は、誰に相談すれば良いでしょうか?
がんと診断され、がんの進行度や治療方針などを担当医から聞き、この先自分がどうなってしまうのかわからず不安に思うのは当然です。不安や悩みは自分で抱え込まず、家族など身近な話せる相手にまず相談してみましょう。家族に心配をかけたくないなら、看護師などの医療者に相談することもできます。
また、全国のがん拠点病院には「がん相談支援センター」という窓口があります。がん相談支援センターがある病院で治療を受けていなくても、誰でも相談できます。
がん闘病中の本人にしかわからない気持ちについて、同じ立場の人に話を聞きたいという人は、患者会を見つけて相談してみると良いと思います。
- 全国の「がん相談支援センター」(施設によって「医療相談室」など)
- 全国各地の患者会
- 日本対がん協会「がん相談ホットライン」(電話相談)
このような施設が相談に応じてくれます。また、仕事やお金に関する支援などは、病院の医療ソーシャルワーカーのほか、社労士さんにも相談してみるという方法もあります。
Q がん治療中の不安を少しでも軽くするために、がん闘病者本人ができることはありますか?
がんと診断された患者さんに、3つのことを伝えています。
- 正しい情報を得る
- 自分に「できること」「できないこと」を分ける
- 不安と上手に付き合う
まず1つ目ですが、がんと向き合うために必要なことは、「正しい情報を得る」ことです。人は、わからないことに対して不安になります。例えば、暗闇に1人取り残されていれば、なにも見えないため、どちらに進めば良いのか不安になります。もし、この状況で目印を見つけたとしても、その目印が間違っていれば、正しい方向へ進むことはできません。正しい情報を得ることで、正しい方向へ進むことができ、不安も和らぎます。
担当医は、患者さんの状態を理解している、身近な医療者の1人です。まずは、担当医にご自身の状態とこれから進む治療方針を確認してください。そのうえで、治療方針に関してほかの意見を聞きたい、ほかの治療法もあるのではないか、自分の選択はこれでいいのかなど、少しでも不安が残るようなら、「セカンドオピニオン」という方法もあります。セカンドオピニオンは、患者さんが納得のいく治療法を選択するために、担当医の先生とは別の医療機関の医師に第2の意見を求めることです。
インターネットでがんに関する情報を探す場合は、国立がん研究センターのがん情報サービス、各種学会、がん診療ガイドラインなど、科学的な観点を持って正確な情報発信をしているウェブサイトなどを参考にしましょう。
2つ目に、自分に「できること」と「できないこと」を分けて考えることも大切です。がん治療で自分にできることは、「最良の治療を選択して、それを完遂すること」です。ただし、標準治療を受けても再発することはありますし、結果を待つしかないことはありますので、自分の力では消すことができない不安もあります。消えない不安をなくそうと焦ると、余計に不安が大きくなってしまうこともあります。不安を大きくしないために、自分にできないことは「この不安は付き合っていくしかないな」と割り切ることも大切です。
3つ目に、消せない不安とは上手に付き合っていくことが大切です。でも、不安でつらいとおっしゃる方も一日中強い不安があるわけではなく、その時々の「行動」によって、不安の程度は変わります。まず、自分の不安を客観視することから始めてみましょう。そのためには「1日の行動を書き出してみる」ことで、「不安を見える化」することがあります。これは「認知行動療法」と呼ばれ、行動ごとに不安の強さが100%中何%かを採点して「週間活動記録表」に記録するものです。1週間ほど記録すると、1日のうちの何時ごろ、どんな行動の時に不安が高まっているのか、また、逆に不安が軽減されるのは何をしている時なのかが、一目で見えるようになります。不安が見える化されることで、不安と感じる行動や時間を減らすための対策につながります。

Q がん患者さんの心を支えるために、家族にできることはありますか?
家族が自分のことを思って「こうしたほうがいい」と言ったり決めたりしてくれているとわかっているがために、結果的に自分の思い通りでない方向に進んでしまい、悩んでしまう患者さんもいます。 そうならないために、何かをしようとする前に、患者さん自身の気持ちを理解しようとすることが大切です。また、「家族や友人には普段通り接してほしい」という患者さんも多くいらっしゃいます。何か特別なことをしなければいけないと考えてしまう人もいますが、患者さん本人の気持ちを尊重して、いつも通りに接するということも大切です。
Q がん患者さんに精神症状が起こったとき、家族にサポートできることはありますか?
家族が、「うつ」「適応障害」「せん妄」などの精神症状をしっかりと理解して何かをするのは難しいと思いますが、あらかじめ知っておくことで、あわてたり、不安になったりしないで済む場合もあります。
がんの告知や再発など、ショックなことがあった後にはうつ状態になる患者さんが多くいます。うつ状態になると、気持ちが1日中ふさぎ込んでしまい、今まで楽しみにしていた活動ができなくなってしまいます。こうした状態が、1日2日ではなく1週間以上続いていると気付いた場合は、うつの可能性がありますので、担当医に相談してください。
せん妄は、夢と現実の区別がつかなくなってしまっているような状態です。例えば、今、東京にいるのに「沖縄にいる」と患者さんが話したとします。そんなときには、その言葉を否定せず、話を合わせるようにしましょう。また、あまりに突拍子もないような話に進展しそうなら、うまく話題を変えてみるのも効果的です。
精神症状のことで何か変わった様子がみられたときは、家族だけでなんとかしようとせず、担当医や看護師などに相談してみましょう。
Q がん患者さんに「がんばって」と声をかけても大丈夫でしょうか?
がんばれと言われても、「これ以上何をがんばれと言うのか、もう十分がんばっているのに」「わかったようなこと言わないで」という気持ちになる患者さんは多いようです。どういうシチュエーションで伝えるかにもよると思いますが、簡単には使わないほうが良い言葉かなと思います。
Q がんで家族を亡くし、もっと何かできたのではないのかという後悔や罪悪感が消えません。誰に相談すれば良いでしょうか?
がん相談支援センターは、遺族の悩みの相談にも乗ってくれます。また、全国各地には「遺族会」がありますので、同じ悩みを抱えた遺族と話すことで「心の痛み」を軽減できるかもしれません。「遺族(家族)ケア外来」という専門外来が設けられている医療機関もあります。
「ときぐすり」という言葉があり、死別による悲しみは、時間が解決するものだ、と言われることもありますが、そう簡単ではないものだと私は思います。大切な方がお亡くなりになってから、何年も時間が止まったままだとおっしゃるご遺族もいらっしゃいます。悲しみが長引き、日常生活に支障が続く場合は、「遺族(家族)ケア外来」を受診してみてください。
Q がんに伴う精神症状を専門とする腫瘍精神科/精神腫瘍科とは、どんな診療が受けられるのでしょうか?
腫瘍精神科/精神腫瘍科は、がんを熟知している「心の専門家」であるスタッフが、患者さんの病態に応じた治療を提供することを専門にしています。具体的には、カウンセリング、薬による治療、生活に関するアドバイスなど、さまざまな方法で、がんという病気とうまく付き合っていくための治療やサポートをしています。患者さん本人はもちろん、ご家族も対象です。受診を希望する場合は、まず担当医や看護師に相談してみましょう。
当院の初診の場合は、最初に公認心理師が詳しい事情をうかがいます。
- どのようなことで受診されたか(主訴)および当科への希望
- 精神的な問題の経過
- がんの経過
- 生い立ちやこれまでの生活、家族について
こうした内容を30~60分ほどかけて聴かせていただいたのち、医師の診療になります。カウンセリングが適切と判断された場合は、引き続き公認心理士によるカウンセリングが行われます。お薬の投与が必要な方は、医師の診察を継続しますし、カウンセリングと診察両方を受けられる方もいらっしゃいます。

