がん相談スペシャル―がん闘病中の患者さんが抱える「がん疼痛」と緩和ケアについて専門医が回答
がんの闘病に伴うさまざまな痛みや症状に対処する、緩和ケア。「どのような場合に、何のために、どのような方法で行われるのか」「がんと診断されてすぐに始める場合は病状が深刻なのか」――。がん患者さんが抱えるさまざまな疑問や不安、誤解などについて、埼玉県立がんセンター 緩和ケア科長兼診療部長 余宮 きのみ 先生にご回答いただきました。
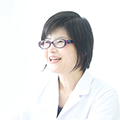
プロフィール
埼玉県立がんセンター緩和ケア科科長
1991年日本医科大学卒業。内科、整形外科、神経内科を経て、1994年日本医科大学リハビリテーション科。2000年より現職、緩和ケア病棟、緩和ケア外来、緩和ケアチームで緩和ケアを実践。日本緩和医療学会専門医。日本緩和医療学会 がん疼痛ガイドライン委員会委員長(2020年版、2014年版)、同学会がんの痛みの治療ガイド増補版作成委員、同学会 緩和医療ガイドライン統括委員会 副委員長医
2021.11 取材・文 がん+編集部
- Q がん闘病中に起こる痛みには、どのようなものがありますか?
- Q 緩和ケアとは、どのようなものですか?
- Q 痛み止めはあまり使わない方がいいのでしょうか?治療への影響はないのでしょうか?
- Q 痛み止めを使いすぎると効果がなくなるのでしょうか?
- Q 痛み止めを上手に使う方法はありますか?
- Q うまく痛みの症状を伝えられません。なにかコツはありますか?
- Q がんの痛みは、薬で抑えられるのでしょうか?どのような目標に向かって進められるのでしょうか?
- Q がんの痛みで使われる薬はどのようなものですか?
- Q オピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)で副作用が起こった場合どうしたらよいですか?
- Q 痛み止めは麻薬の一種とききましたが、依存症にならないのでしょうか?
- Q オピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)を使うということは、最後の手段なのでしょうか?
Q がん闘病中に起こる痛みには、どのようなものがありますか?
がん自体が原因で起こる痛みだけではなく、様々な痛みを体験する可能性があります
がん闘病中に起こる痛みの多くは、(1)がん自体による痛みですが、それ以外の原因で生じる痛み「(2)~(4)」もあります。
(2)がんに関連した痛み(筋肉のつり、便秘による痛み、手足などのむくみなどによる痛み)、(3)がんの治療に関連して起こる痛み(手術後の慢性痛、抗がん剤による口内炎や末梢神経障害、放射線治療による痛み)、(4)がん以外の原因で起こる痛み(変形性脊椎症、関節炎、胆石症)、誰でも経験するような痛み(単純な頭痛、歯痛など)です。
これらのうち、(1)のがん自体が原因で起こる痛みを一般に、「がん疼痛」といいます。これに対しては、痛みの原因に対する治療とともに、世界保健機関(WHO)や日本緩和医療学会が提唱している痛みの治療法が行われます。具体的には、解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン、非ステロイド性消炎鎮痛薬)やオピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)、鎮痛補助薬などを使用します。
Q 緩和ケアとは、どのようなものですか?
緩和ケアは、病気に伴う体と心の痛みを和らげる治療
緩和ケアは、がん疼痛(がんが原因で起こる痛み)に対する治療だけではなく、そのほかがんに伴うさまざまな症状、や心の痛みを和らげる治療で、がんと診断されたときから必要に応じて行われます。終末期だけに行われるものではありません。
通常は、主治医を中心とした看護師、薬剤師などのチームが、がんの治療と並行して緩和ケアを行っています。主治医チームでは対応が難しい場合などに、専門的な緩和ケアを行える緩和ケアチームが主治医チームをサポートします。
がんと診断されたときの心の痛みや不安、治療中の体の痛み、仕事や生活に関する問題などに対してさまざまなケアを行い生活の質を改善することで、がん患者さん本人や家族が、可能な限り質の高い治療や療養生活を送れるようにするのが、緩和ケアの目的です。
緩和ケアを受けたことで生存期間が延長し、生活の質が向上するという研究報告もあります。
Q 痛み止めはあまり使わない方がいいのでしょうか?治療への影響はないのでしょうか?
痛みを抑えることで、治療継続のサポートに
処方された痛み止めを使用しても、治療に悪い影響を及ぼすことはありません。がんの痛みを医師や看護師に伝えると、痛みをとる治療が優先され、がんの治療を中止されると心配される患者さんもいますが、がんの痛みをとりながら、がんの治療も続けて行うことができます。
逆に、痛みを我慢することが体力の消耗やストレスとなり、がんの治療に悪影響を及ぼすこともありますので、痛みは我慢せず、医師や看護師に相談してください。
Q 痛み止めを使いすぎると効果がなくなるのでしょうか?
痛み止めは、痛みの強さにあわせて量や種類を調整
痛み止めを長く使っていても、効かなくなるということはありません。また、痛みに対して必要な痛み止めの量は、患者さんごとに異なり、患者さん同士で多い、少ないと比べることはできません。穏やかに生活ができるように、痛み止めの量や種類を調整することが大切です。
また、時間の経過とともに、痛みの強さや性質が変わってくることはよくあることです。治療によって痛みが軽くなることもあります。そのため、そのときの痛みに合わせて、痛み止めの量や種類を変えます。
Q 痛み止めを上手に使う方法はありますか?
薬を飲む時間を決め、薬の効果が弱くなる時間ができないようにすることが大切
がんの痛みは1日中持続することが多いため、薬を飲む時間を決めることで、薬の効果が弱くなる時間ができないようにすることが大切です。
痛みの感じ方には個人差があるため、それぞれの患者さんの痛みに合わせて薬の量が決定されます。痛みが十分に和らぎ、眠気などの副作用が気にならないように、量を調整することが重要です。
痛みが一時的に強くなった時には、とんぷく薬(レスキュー薬)を使いましょう。1回使用しても痛みが治まらなければ、指示された間隔をあけてもう一度使用してみましょう。もし、とんぷく薬を使用しても痛みが治まらず、眠気ばかりが出てしまうようなら、薬を変更することで改善することがありますので、医師や看護師、薬剤師に相談しましょう。
Q うまく痛みの症状を伝えられません。なにかコツはありますか?
痛みの状況を整理し、短時間で必要な情報を伝えるためにメモを活用
がんの痛みは、患者さん自身にしかわかりません。医師や看護師、薬剤師は、患者さんが伝えてくれた情報を元に、痛みの状況と原因を探り対応します。そのため、痛みを上手に伝えることが大切です。
痛みを伝えるときは、「どの場所に」「いつから」「どの程度(強さ)」「どんなときに」「どのような(痛みの種類)」「どのくらいの頻度」など、より具体的に痛みの内容を伝えましょう。
痛みの強さを伝えるためには、痛みのない状態を「0」、最も強い我慢できない痛みを「10」として、数字で伝えるとわかりやすくなります。
痛みの種類は、「ズキズキする痛み」「鈍痛」「ビリビリ」「刺すような鋭い痛み」「凝るような」など、ご自身で感じた痛み方を表現してみてください。
このような痛みの状況を医師や看護師、薬剤師に伝えるために、メモが役立ちます。メモを活用することで、痛みの状況を整理することもできますし、短時間で必要な情報を伝えることができます。また、「眠れない」「歩くのがつらい」「仕事や家事がつらい」など、痛みで日常生活に支障をきたしていることについても、伝えましょう。
Q がんの痛みは、薬で抑えられるのでしょうか?どのような目標に向かって進められるのでしょうか?
痛みに妨げられずに眠れる、安静時の痛みの緩和、などと段階的に目標を設定
一般に、治療の目標は以下の3つに分けられます。これら3つを達成できるように痛みの治療が行われます。
- 第1段階:痛みに妨げられない睡眠時間の確保
- 第2段階:安静にしていれば痛みが消えている状態の確保
- 第3段階:起立したり、体を動かしたりしても痛みが消えている状態の確保
第1、第2段階の目標は、痛み止めの薬を適切に用いることによって、多くの場合、達成することができます。
一方、第3段階の目標では、痛みの原因によっては薬だけでは達成できないことがあります。たとえば、骨転移で動いた時だけ痛みがでる、といった痛みには、放射線治療などの専門的な治療や、痛みがでにくいような環境調整、動き方を指導するリハビリテーションを行うことがあります。
Q がんの痛みで使われる薬はどのようなものですか?
患者さんの状態や副作用により、痛み止めの種類や剤形を選択
痛み止めには、いろいろな種類や剤形があります。同じ種類の薬でも、飲み薬、貼り薬、坐薬、注射薬などがあり、患者さんの状態により選択されます。
痛みが軽いときに使う薬
痛みが軽ければ、解熱鎮痛薬が使われます。解熱鎮痛薬には、アセトアミノフェンと炎症を抑える非ステロイド性消炎鎮痛薬があります。非ステロイド性消炎鎮痛薬は、炎症による痛みを和らげたり、熱を下げたりする作用がありますが、胃潰瘍、腎機能障害、肝機能障害などの副作用が起こる可能性があります。
アセトアミノフェンは、腎機能の低下や胃腸障害で非ステロイド性消炎鎮痛薬の使用が難しい患者さんに対して使用されます。炎症を抑える効果はありませんが、痛みの軽減や熱を下げる作用があります。まれに肝機能障害が起こる可能性があります。
痛みが中くらい~強いのときに使う薬
痛みが中くらい以上のときは、モルヒネ、ヒドロモルフォン、オキシコドン、フェンタニル、タペンタドール、メサドンなどのオピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)が使われます。オピオイド鎮痛薬は種類により、性質や使用法が異なります。
モルヒネは、古くから使用されている医療用麻薬です。錠剤、カプセル、液剤、坐薬、注射剤などさまざまな剤形があり、患者さんの状態により選択されます。モルヒネは腎機能が低下していると、眠気やせん妄が起こりやすくなります。
ヒドロモルフォンは、モルヒネと似た薬ですが、腎機能が低下している患者さんでも比較的安全に使用することができます。量の少ない錠剤があり少量から始められるため、初めて医療用麻薬を使う患者さんによく使われます。錠剤、注射剤などの剤形があります。
オキシコドンもモルヒネと似た性質の薬で、腎機能が低下している患者さんでも比較的安全に使用することができます。錠剤、カプセル、注射剤などの剤形があります。
フェンタニルは、腎機能が低下した患者さんでも安全に使用できる薬です。貼り薬、口腔内粘膜吸収剤(口の中で溶かし、口の粘膜から直接吸収される)、注射薬などの剤形があります。内服ができない患者さんに用いられます。
タペンタドールは、モルヒネやオキシコドンと比べ、吐き気、便秘、眠気などの副作用が少ないとされており、腎機能が低下した患者さんでも安全に使用できる薬です。初めて医療用麻薬を使う患者さんでよく使われます。
メサドンは、上記の医療用麻薬では抑えられない痛みがあるときに使用される薬です。使用に関しては、専門的な知識が必要なため、処方できる医師が限られています。一般に、緩和ケアチームの医師、在宅で緩和ケアを行っている医師などが取り扱っています。
痛みが中くらいのときに使う薬
痛みが軽~中くらいのときは、コデインやトラマドールというオピオイド鎮痛薬が使われることもあります。コデインは、痛みを抑えるほか、咳止めの効果もある薬です。これらの薬にも、便秘、眠気、吐き気などの副作用がありますが、適切に対処することで大きな問題となることはありません。
Q オピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)で副作用が起こった場合どうしたらよいですか?
副作用に合わせて対処方が異なる、薬以外の原因が関係していることも
どのオピオイド鎮痛薬も、便秘、吐き気、眠気、喉の渇きを生じることがあります。また頻度は少ない副作用として、尿が出にくくなる、かゆみ、呼吸抑制(呼吸の回数が減る)などがあります。ただし、副作用が原因で痛み止めが使用できなくなることはありません。
便秘
最も頻度が高く、オピオイド鎮痛薬を使うと8割程度の患者さんが便秘になり、持続します。ただし、オピオイド鎮痛薬の便秘を解消する専用の薬(ナルデメジン;商品名スインプロイク)がありますので、併用することでオピオイド鎮痛薬による便秘を最小限に抑えることができます。
また、がん患者さんでは、オピオイド鎮痛薬以外にも便秘の原因になる薬剤が使用される場合がありますし、痛みなどのストレスやがん治療による食事量・運動量の減少も便秘の原因になります。便秘に対する一般的な対処法として、「水分や食物繊維の摂取」「運動」「腹部マッサージ」などがありますが、便が硬い場合には便秘治療薬(下剤)を利用して適度な柔らかさの便に調整するようにしましょう。
吐き気
オピオイド鎮痛薬の使い始めに吐き気が起こることがありますが、1~2週間で徐々になくなってきます。もし、オピオイド鎮痛薬を使い始めてしばらくしてから初めて吐き気がでたようなときは、ほかの原因による吐き気の可能性があります。「食事をしたときに起こる胃腸に関わる吐き気」「動いたときやめまいによる吐き気」など、それぞれの状況にあわせた治療、または吐き気止めが使用されます。そのほか、「消化のよい食事にする」「部屋の空気の入れ替えをする」「香水や芳香剤を変える、もしくはやめる」などの対処法もあります。
眠気
ふらつきや眠気は、オピオイド鎮痛薬でよく起こる副作用の1つです。オピオイド鎮痛薬の使用開始時や薬の量を増やしたときに起こる一時的なもの、薬の量が多すぎるもの、ほかの薬の影響によるものなどが考えられます。痛みが取れたことで眠れるようになったという場合もあります。
痛み止めに慣れてくると1週間程度で、眠気はなくなります。心地よい眠気などは様子をみてかまいません。また食事や会話中にも眠ってしまうような強い眠気には注意が必要です。眠気が強い場合は、薬の種類を変えたり、量を減らしたりすることで対処することができます。ただし、原疾患からくる眠気もあります。強い眠気が続く場合には、血液検査で原因検索をする必要がありますので、医師に相談してください。
Q 痛み止めは麻薬の一種とききましたが、依存症にならないのでしょうか?
適切に使用すれば依存症になる心配はない
痛み止めは、痛みの強さにより、薬の強さや量が調節されるため、痛みにあわせて量を増やしたり、種類を変更したりすることもあります。
麻薬依存は、痛みがないのに薬を使いたくなり、自分でコントロールできない状態です。医師の処方により適切に使用されれば、依存症になる心配はほとんどありません。
Q オピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)を使うということは、最後の手段なのでしょうか?
オピオイド鎮痛薬(医療用麻薬)は、がんの痛みを治療する中心的な役割を果たす痛み止め
オピオイド鎮痛薬は、がんの痛みを治療するための中心的な役割を果たす痛み止めです。痛みが中等度以上である場合や、解熱鎮痛薬では痛みが抑えられない場合に使われます。
医師の処方により適切に使用すれば、オピオイド鎮痛薬を使っても寿命が縮まることはありません。

