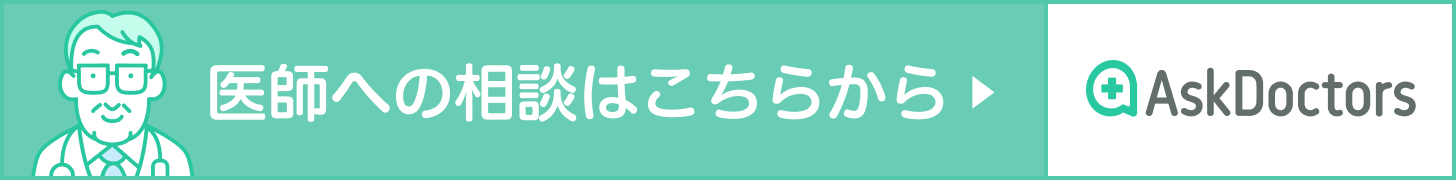相談:2度の内視鏡検査と生検でもはっきりとがんなのかわかりません。どうしたらいいですか?
私は79歳です。自治体の胃がんリスク検診を受診したところ、精密検査を受けるように言われ、近所の総合病院で内視鏡検査と生検を受けました。1回目の内視鏡検査で4か所の病変が見つかりました。うち1か所にがんの疑いがあることがわかり、再度、精度の高い内視鏡検査と生検を受けました。しかし、この結果も1回目の検査結果と同じで、がんか否か判断できないという結論でした。
医師から「2回目に採取した病変を再度生検して、それでも結果が同じなら3回目の内視鏡検査と生検をしましょう」といわれました。しかし、ずるずると判断を先延ばしにすることでがんが大きくなり、手術が大変になるのではないかと不安になっています。このまま、検査の結果を待っていても大丈夫でしょうか。がん専門病院でセカンドオピニオンを受けることも考えています。
(本人、男性)
回答:組織の挫滅や障害が強く、腫瘍か非腫瘍かの判断が困難な場合は再検査が必要
日本胃癌学会の「胃癌取扱い規約第15版」によると、胃がんの治療のポイントは以下の通りです。
胃がんの検査に関して
・胃がんの疑いがある場合、確定診断を目的に生検が行われます
・生検で「診断不適材料」と判断された場合は、再生検が行われます
・「診断適切材料」と判断された場合は、組織検査が行われます
・組織検査では、「非腫瘍(グループ1)」「不明(グループ2)」「腫瘍(グループ3~5)」の3つに分類されます
・「非腫瘍(グループ1)」と判定された場合は、必要に応じて経過観察とされています
・「不明(グループ2)」は、確定診断できない病変が含まれるため対応が異なります
・グループ3と判定された場合は、病変の大きさを参考に、必要に応じて内視鏡的切除が行われます
・グループ4と判定された場合は、がんが疑われる病変の大きさや内視鏡的な性状が確認され、再生検や内視鏡的切除が行われます
・画像診断(大きさ・深達度など)を参考にして治療方針が決定されます
不明(グループ2)と判定された場合
・組織量が少なく細胞異型からでは腫瘍性病変としての判断が困難な場合は、再検査が行われます
・びらんや炎症性変化が強く腫瘍か非腫瘍かの判断が困難な場合は、消炎後再生検を行うか十分な経過観察を行うとされています
・病変組織の挫滅や障害が強く腫瘍か非腫瘍かの判断が困難場合は、再検査が必要とされています。
胃がんの検査に関して
・胃がんの疑いがある場合、確定診断を目的に生検が行われます
・生検で「診断不適材料」と判断された場合は、再生検が行われます
・「診断適切材料」と判断された場合は、組織検査が行われます
・組織検査では、「非腫瘍(グループ1)」「不明(グループ2)」「腫瘍(グループ3~5)」の3つに分類されます
・「非腫瘍(グループ1)」と判定された場合は、必要に応じて経過観察とされています
・「不明(グループ2)」は、確定診断できない病変が含まれるため対応が異なります
・グループ3と判定された場合は、病変の大きさを参考に、必要に応じて内視鏡的切除が行われます
・グループ4と判定された場合は、がんが疑われる病変の大きさや内視鏡的な性状が確認され、再生検や内視鏡的切除が行われます
・画像診断(大きさ・深達度など)を参考にして治療方針が決定されます
不明(グループ2)と判定された場合
・組織量が少なく細胞異型からでは腫瘍性病変としての判断が困難な場合は、再検査が行われます
・びらんや炎症性変化が強く腫瘍か非腫瘍かの判断が困難な場合は、消炎後再生検を行うか十分な経過観察を行うとされています
・病変組織の挫滅や障害が強く腫瘍か非腫瘍かの判断が困難場合は、再検査が必要とされています。
また、この診断が行われる場合は、深切り切片などを作製し追加検討が行われます。何度か検査が連続して繰り返される場合は、専門家へ相談することが推奨されています
生検組織診断分類
グループ X:生検組織診断ができない不適材料
グループ 1:正常組織および非腫瘍性病変
グループ 2:腫瘍(腺腫またはがん)か非腫瘍性か判断の困難な病変
グループ 3:腺腫
グループ 4:腫瘍と判定される病変のうち、がんが疑われる病変
グループ 5:がん
セカンドオピニオンに関して
セカンドオピニオンは、患者さんにとって最善だと思える治療を患者さんと担当医との間で判断するために別の医師の意見を聞くことが目的です。そのため、新たな検査などは行われません。
しかし、同じ検査結果でも別の診断を示してくれる可能性もあります。また、医師や医療機関によって患者さんに提供すべきだと考える検査や治療は同じとは限りません。患者さんごとに、自分の受けたい診療はさまざまです。検査や治療方針は、医師だけが決めるものではなく、患者さんと相談し納得した上で決められます。情報や意見は多い方が納得した診療につながる可能性は広がり、セカンドオピニオンはそのための一手段となり得ます。
参考情報:
胃癌取扱い規約第15版XV胃生検組織診断分類(Group分類)
※同様の内容が、下記ガイドラインに掲載
胃癌治療ガイドライン医師用 2014年5月改訂 [第4版] III章.資料.生検組織診断分類(Group分類)の取扱い
http://www.jgca.jp/guideline/fourth/category3-b.html
生検組織診断分類
グループ X:生検組織診断ができない不適材料
グループ 1:正常組織および非腫瘍性病変
グループ 2:腫瘍(腺腫またはがん)か非腫瘍性か判断の困難な病変
グループ 3:腺腫
グループ 4:腫瘍と判定される病変のうち、がんが疑われる病変
グループ 5:がん
セカンドオピニオンに関して
セカンドオピニオンは、患者さんにとって最善だと思える治療を患者さんと担当医との間で判断するために別の医師の意見を聞くことが目的です。そのため、新たな検査などは行われません。
しかし、同じ検査結果でも別の診断を示してくれる可能性もあります。また、医師や医療機関によって患者さんに提供すべきだと考える検査や治療は同じとは限りません。患者さんごとに、自分の受けたい診療はさまざまです。検査や治療方針は、医師だけが決めるものではなく、患者さんと相談し納得した上で決められます。情報や意見は多い方が納得した診療につながる可能性は広がり、セカンドオピニオンはそのための一手段となり得ます。
参考情報:
胃癌取扱い規約第15版XV胃生検組織診断分類(Group分類)
※同様の内容が、下記ガイドラインに掲載
胃癌治療ガイドライン医師用 2014年5月改訂 [第4版] III章.資料.生検組織診断分類(Group分類)の取扱い
http://www.jgca.jp/guideline/fourth/category3-b.html
医師に相談したい場合、現役医師が回答する「AskDoctors(アスクドクターズ )」の利用もおすすめです。