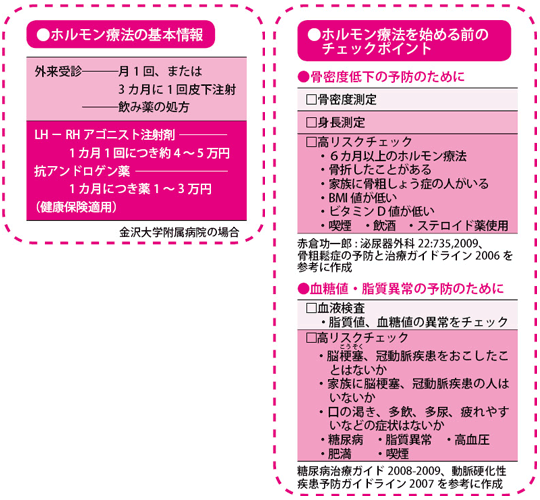前立腺がんの「ホルモン療法(内分泌療法)」治療の進め方は?治療後の経過は?
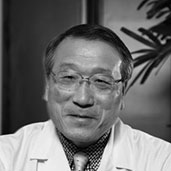
- 並木幹夫(なみき・みきお)先生
- 金沢大学附属病院 泌尿器科教授
1950年神奈川県生まれ。大阪大学医学部卒。国立大阪病院などを経て、1995年から現職。2008年金沢大学附属病院副院長。日本アンドロロジー学会理事長。
本記事は、株式会社法研が2011年7月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん」より許諾を得て転載しています。
前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。
男性ホルモンを抑えてがんを縮小させる
がんの増殖に影響する男性ホルモンを抑制。進行がんには単独で用い、局所進行がんには手術療法や放射線療法と併用することもあります。
精巣と副腎から分泌される男性ホルモンをブロック
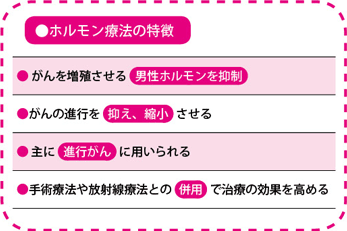
ホルモン療法は内分泌療法ともいいます。前立腺がんは男性ホルモンと関係が深く、男性ホルモンがたくさんあるほど増殖する性質があります。そこで、男性ホルモンの分泌やその作用を抑えて、前立腺がんを小さくしていくのがホルモン療法です。
がんを根治できるとは限りませんが、前立腺がんの進行は遅いので、とくに高齢者にはきわめて有効な治療法といえるでしょう。
男性ホルモンは主に精巣(せいそう)から分泌されていますが、一部は副腎(ふくじん)からも分泌されます。そこで、精巣からの男性ホルモンをブロックする薬と、副腎からの男性ホルモンをブロックする薬があります。それぞれ単独で使われることもありますが、両者を併用して治療するのが一般的です。
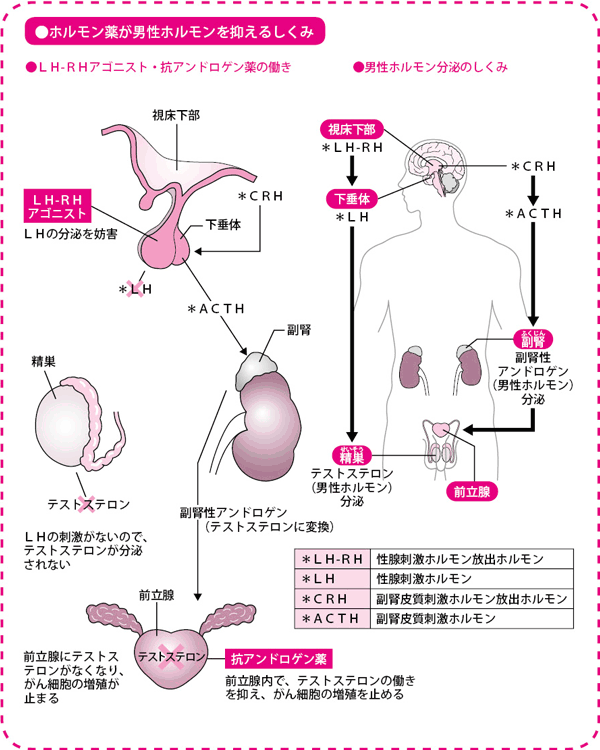
●精巣からの男性ホルモンをブロックするLH-RHアゴニスト
精巣からの男性ホルモンをブロックする方法として今いちばん多く使われているのは、LH-RHアゴニスト(酢酸ゴセレリン/商品名ゾラデックス、酢酸リュープロレリン/商品名リュープリン)と呼ばれる注射剤です。LH-RHとは性腺刺激ホルモン放出ホルモンのことです。
少し複雑な話になりますが、薬が効くメカニズムを説明しておきましょう。上の図を見てください。
精巣から分泌される男性ホルモンのテストステロンは、脳内にある下垂体から分泌されるLH(性腺刺激ホルモン)によって分泌をコントロールされています。さらに、LHは、脳内の視床下部から分泌されるLH-RH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)によって分泌をコントロールされています。LH-RH→LH→テストステロンという順番で分泌されていくわけです。
そこで、この流れのいちばん上流であるLH-RHが働かないようにしてしまおう、というのがLH-RHアゴニストという注射剤です。
アゴニストとは作用薬という意味ですが、わかりやすくいえば、“そっくりの偽物”です。LH-RHアゴニストは、LH-RHと似た構造の偽物で、下垂体にあるLHの受け皿である受容体と結びつきます。このため、本来結びつくはずのLH-RHがやってきても、結びつくことができません。結果として、LHは分泌されなくなるしくみです。
LH-RHの偽物を送り込んで、本物のLH-RHを働けないようにしてしまうのが、この注射剤です。注射剤になっているのは、飲み薬でとると、肝臓で薬としての働きを失ってしまう性質があるためです。
LH-RHアゴニストは、下腹部に打つ皮下注射です。月に1回注射を打つタイプと、3カ月に1回注射を打つタイプがあり、どちらも、効果や副作用に違いはありません。
精巣から分泌される男性ホルモンをブロックするにはもう一つ別の方法があります。精巣摘除術で、去勢術とも呼ばれます。男性ホルモンを分泌する精巣(睾丸)そのものを切り取ってしまう治療法で、30分程度の手術時間、数日の入院を要します。精巣を取るので、男性ホルモンは回復しません。
LH-RHアゴニストの開発により、この治療法を受ける人は減りましたが、ホルモン薬を長期に使用することに比べれば経済的に安価なため、現在でも主として高齢の患者さんに、希望があれば行います。
●副腎からの男性ホルモンをブロックする抗アンドロゲン薬
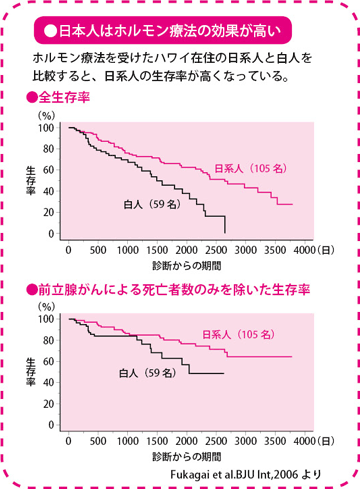
副腎から分泌される男性ホルモンをブロックするには、抗アンドロゲン薬を使います。アンドロゲンは男性ホルモンの総称です。
抗アンドロゲン薬は飲み薬で、副腎から分泌された男性ホルモンが、前立腺の内部でがん細胞に対して働くのを防ぐ作用をもっています。
抗アンドロゲン薬にはステロイド系のもの(酢酸クロルマジノン/商品名プロスタール)と、非ステロイド系のもの(ビカルタミド/商品名カソデックス、フルタミド/商品名オダインなど)があります。
ステロイド系のものは、副腎から分泌された男性ホルモンの働きを抑える作用のほかに、下垂体からのLHの分泌を妨げ、テストステロンの分泌を抑える効果があります。一方、非ステロイド系のものは、副腎から分泌された男性ホルモンのがん細胞への働きを防ぐ作用だけをもっています。
抗アンドロゲン薬の副作用には、ステロイド系では、性機能障害(勃起(ぼっき)障害=ED)と女性化乳房(乳房が女性のようにふくらむ)があり、非ステロイド系では肝機能障害と女性化乳房があります。
非ステロイド系のものは、男性ホルモンの分泌自体を抑制することはないので、性機能障害はおこりにくいと考えられています。このため、性機能を重視する場合は、非ステロイド系の抗アンドロゲン薬を単独で用いることもあります。
●主なホルモン療法
| LH-RHアゴニスト | 皮下注射 | ●下垂体に働きかけホルモン分泌を抑制 テストステロン分泌を強力に抑える 薬代が高い |
|---|---|---|
| 抗アンドロゲン薬 | 飲み薬 | ●副腎からの男性ホルモンが前立腺がんに作用しないようにする この薬だけでは効果が不十分な可能性がある |
| ステロイド系 | ●下垂体からのLH分泌を阻害する働きももつ 主な副作用は性機能障害と女性化乳房 |
|
| 非ステロイド系 | ●前立腺内の抑制作用のみ 主な副作用は肝機能障害と女性化乳房 |
|
| CAB療法 | 皮下注射 + 飲み薬 |
●LH-RHアゴニストと抗アンドロゲン薬を併用 ホルモン療法でもっとも多く行われている がんを抑える効果が単独での使用より高い |
| 精巣摘除術 | 手術 | ●男性ホルモンを分泌する精巣を取り除く 1回だけの治療ですみ、治療費が安い 手術が必要 副作用は少ないが、性機能が失われる |
転移がんなら第一に選択 局所進行がんなら併用
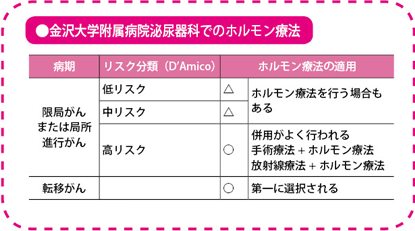
ホルモン療法は転移(進行)がんの場合、第一に選択される治療法です。また、局所進行がんの場合は、手術療法や放射線療法と併用されることがよくあります。
手術療法や放射線療法のあとの治療(アジュバント療法)としてホルモン療法を行う場合と、手術療法や放射線療法の前の治療(ネオアジュバント療法)としてホルモン療法を行う場合があります。
限局がんでは、ホルモン療法は第一に勧められる治療法にはなっていません。欧米では限局がんに対してはホルモン療法を行わないのが一般的です。ところが、日本では限局がんでもホルモン療法をすることがめずらしくありません。
この理由の一つには、日本人が手術療法や放射線療法などの治療を好まないという国民性があります。また、日本人は欧米人に比べて、ホルモン療法の有効性が高いことも理由の一つです。
ハワイ在住の日系人と白人の間でホルモン療法の有効性を比較した試験では、全生存率でも、前立腺がんによる死亡者数のみを除いて出した生存率でも、白人より日系人のほうが高くなっています。
また、限局がんでホルモン療法単独治療をした日本人を10年間経過観察したところ、生存率は同年齢の前立腺がんにかかっていない日本人とほぼ一致したという報告もあります。
ホルモン療法のあとに前立腺全摘除術(手術療法)を行った患者さんの組織を調べると、その15.7%以上ではがん細胞が見つかりません。また、28.7%の患者さんでは、がん細胞の半分以上が死滅していました。これは、ホルモン療法をすると、前立腺がんの大半がアポトーシス(細胞死)をおこすためです。
このようなことを総合的に考えると、ホルモン療法は限局がんに対しても有効な治療法といえます。
私の勤務する金沢大学附属病院泌尿器科では、前立腺がんに対してさまざまな治療法を提供していますが、ホルモン療法については上の表のように位置づけています。
治療の進め方は?
CAB療法から始め、その後は使用する薬の交換、治療を一時中断して再開するなど、いろいろな治療方法が試みられています。
通常は、単独療法より強力なCAB療法が第一選択
ホルモン療法として、もっとも一般的に行われている治療法は、LH-RHアゴニストと抗アンドロゲン薬を併用する治療法です。これは、CAB(combined androgen blockade)療法と呼ばれ、二つの薬を組み合わせて用い、精巣と副腎から分泌される男性ホルモンの働きを両方とも抑えてしまおうというものです。
精巣からのホルモンを抑える方法として、LH-RHアゴニストの代わりに、精巣摘除術を組み合わせる場合もあります。
LH-RHアゴニストの単独療法と、抗アンドロゲン薬(ビカルタミド)を加えた併用療法の進行がんに対する治療効果を比べた試験では、併用療法のほうが前立腺がんの増殖を止める力が強いことがわかっています。
PSA値が0.2未満まで低下すれば効果あり
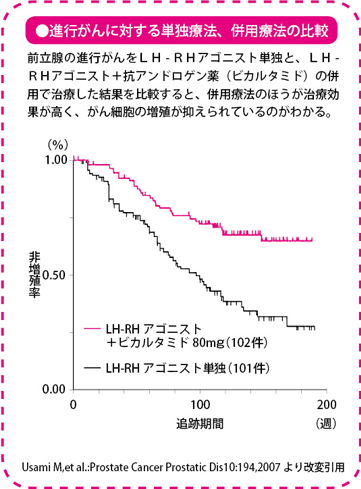
低リスクまたは中リスクの患者さんがホルモン療法を希望する場合には、まずCAB療法を始めてみて、6カ月以内のPSA値の変化から治療効果を見極めます。それによって、継続するかどうかを判断します。
PSA値が、0.2未満にまで下がれば、そのままホルモン療法を続けることができます。0.2未満に下がらない場合は、薬への反応が悪く、がんを抑えきれない確率が高いので、手術療法もしくは放射線療法を勧めます。
高リスクの患者さんの場合は、CAB療法を始めてみて、6カ月後にPSA値が0.2未満になり、かつ次の3条件のうち一つでも当てはまるものがあれば、手術療法や放射線療法などの根治をめざす治療を勧めます。
(1)グリソンスコアが6以下、(2)診断時のPSA値が20以下、(3)PSA値が0.2未満になるまでの期間が6カ月以内。
根治をめざす積極的な治療を勧めるのは、万一、その治療を行ったあとに再発した場合でも、ホルモン療法を再び開始すれば効果が得られると期待できるからです。
3条件のうちどれも当てはまらない場合は、体に負担のある治療は勧められません。6カ月後のPSA値が0.2より高い場合も同様です。
薬の効きが低下したらさまざまな工夫で効果を持続
ホルモン療法では、一定期間治療を続けると、効きが悪くなり、がん細胞の増殖を抑えきれなくなることがわかっています。そこで、ホルモン療法を行うにあたっては、いかに、効果を持続させるかに、さまざまな工夫がなされています。どのくらいの期間で効果がなくなってしまうかは、患者さんによって大きく差があり、数カ月の人もいれば、10年ほど持続する人もいます。
●抗アンドロゲン交替療法
PSA値が高くなってがん細胞の増殖が疑われるときは、LH-RHアゴニストはそのまま続け、抗アンドロゲン薬を別の薬に変えます。抗アンドロゲン薬には、大きく2種類(非ステロイド系とステロイド系)があり、違う種類に変えることで、再びPSA値を抑えることができます。
●女性ホルモン薬との併用療法
ただし、抗アンドロゲン薬を変えても、いずれ、その効果は薄れてきます。このような場合、抗アンドロゲン薬の代わりに女性ホルモン薬を使うことがあります。この場合も、LH-RHアゴニストの注射は続けます。女性ホルモン薬は男性ホルモンの濃度を下げる働きがあります。
女性ホルモン薬を用いると、狭心症や心筋梗塞(こうそく)になりやすいという副作用が欧米では報告されていますが、日本人の調査結果では、必ずしもこの副作用の指摘は当たらないという結果が出ています。
●抗がん薬との併用や間欠療法
そのほか、LH-RHアゴニストと抗がん薬との併用、LH-RHアゴニストと副腎皮質ホルモン薬との併用などの方法がとられます。
また、できるだけホルモン療法の効果を延長させるために間欠療法という方法が試みられることもあります。PSA値が一定の値まで低下したら、いったん完全にホルモン療法を中断し、その後PSA値がある値を超えたら再開するという方法です。
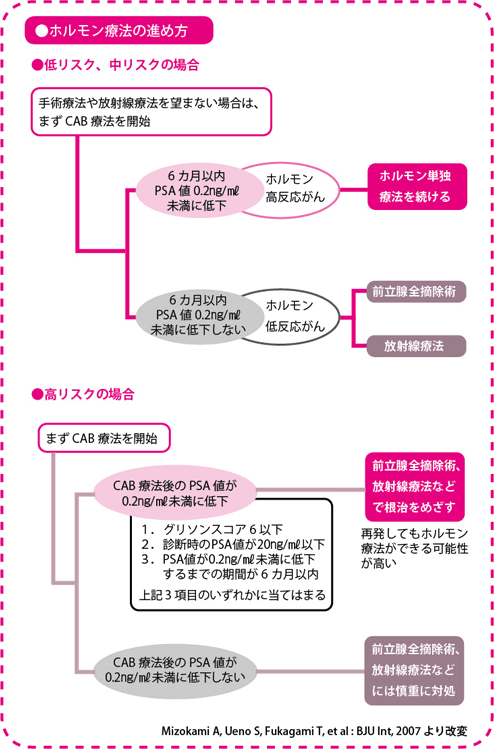
治療後の経過は?
低リスク、中リスクなら高い生存率。 高リスクでも、5年生存率は87.8%になります。 ただし、性機能障害は避けられません。
骨粗しょう症予防にはビスホスホネート製剤が有効
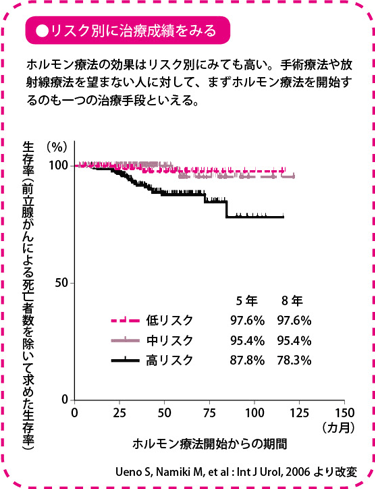
ホルモン療法を単独で行った場合のリスク分類別の治療効果を示したのが上のグラフです。低リスクでは5年と8年の生存率が同じで97.6%、中リスクでも5年と8年の生存率が同じで95・4%と良好な成績です。高リスクは5年生存率が87.8%、8年生存率が78.3%と少し落ちます。なお、このグラフでは、病期を除外して、PSA値とグリソンスコアだけでリスクを分類しています。
ホルモン療法の副作用についてまとめたのが下の図です。ホルモン療法を行うと、ほとんどの場合、性機能障害は避けられません。性機能障害を避けるためには、非ステロイド系の抗アンドロゲン薬を単独で使う方法がありますが、第一に選ぶべき治療法ではありません。
ホルモン療法では、メタボリックシンドロームになりやすいとも考えられています。内臓脂肪が蓄積しやすく、糖尿病や脂質代謝異常、高血圧といった病気に注意が必要です。また、これらの病気になると、動脈硬化をおこしやすく、狭心症や心筋梗塞など、心血管系の疾患にも注意しなければなりません。
また、ホルモン療法を続けていると、骨密度が低下しやすく、骨粗しょう症にならないように注意することが大切です。ホルモン療法では、1年に数%ずつ骨密度が低下していきます。高齢者が骨粗しょう症になると、ちょっと転んだだけで骨折してしまう危険があります。
そこで、ホルモン療法を長期に続ける場合は、骨密度を定期的に測定し、適度な運動をするとともに、カルシウムやビタミンDをとるように心がけることが大切です。
また、骨粗しょう症の予防には、ビスホスホネート製剤と呼ばれる薬が有効です。骨密度が一定レベル以下の場合には、ビスホスホネート製剤を使って骨粗しょう症を予防しています。
また、ビスホスホネート製剤には、がんの骨転移に伴う痛みや、骨折に伴う痛みを軽くする働きもあります。
さらに、ビスホスホネート製剤の一種のゾレドロン酸水和物(商品名ゾメタ)という点滴剤には、抗腫瘍作用もあると考えられています。そこで、前立腺がんで骨転移のある患者さんには、この薬を使っています。ただし、この薬は副作用も強いので、慎重に使わなければなりません。
このほか、ホルモン療法の副作用として貧血にも注意する必要があります。
また、薬によっては、ほてり(ホットフラッシュ)もしばしばみられる副作用です。
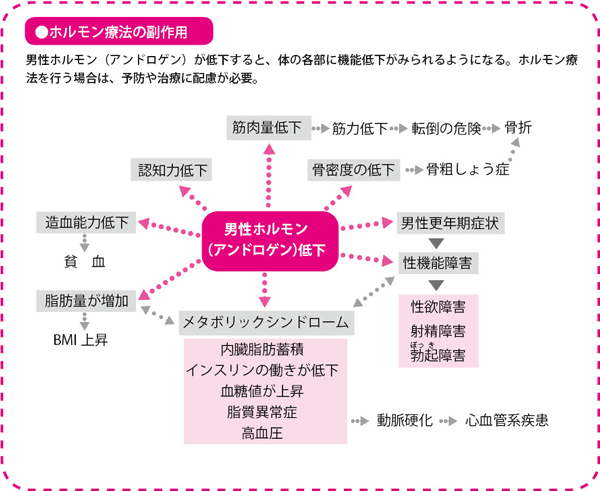
薬の価格はやや高めで自己負担は月額2万円超
ホルモン療法で使う薬は健康保険が適用されます。ただし、薬の価格はやや高めです。LH-RHアゴニストの注射剤は、月1回の注射が4~5万円、3カ月に1回の場合は、1回当たり7~8万円です。抗アンドロゲン薬も合わせると、1カ月の薬代は7万円を超え、健康保険が3割負担の場合は2万円超程度の自己負担となります。抗アンドロゲン薬にはジェネリックもあるので、それを使うと少し薬代が安くなります。
抗がん薬などに比べると安いのですが、長期に使うとなると、負担を感じる場合もあるでしょう。経済性を優先する場合は、LH-RHアゴニストの注射を打つ代わりに、精巣摘除術を受けるのも一つの考え方です。手術費用や入院費用が一時的にかかりますが、長期的にみれば経済性のある治療法です。