患者さんの生きざまに向き合う「優しさに勝るものなど何もない」鳶巣賢一先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2011年7月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん」より許諾を得て転載しています。
前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。
病気が人を変える現場で患者さんの生きざまに向き合う。そこで大切なのは優しさだけ。
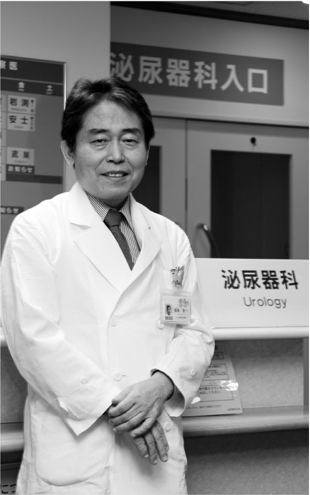
「患者さんにも覚悟が必要、そのためには、自分でとことん考えてほしい」
鳶巣先生は一貫して医療を受ける側の主体性を強調してきました。それは、「勝手にしなさい」と患者さんを突き放すことではなく、患者さんが自分らしい人生を送ることに、医療者が寄り添い、協力できる信頼関係を築くためです。一人の人間として患者さんを尊重し、その人生の一端をともに担う、そうした人間対人間のふれ合いには、互いの「責任」が欠かせないのです。
「人の心と接するチャンス。生きざまを実感する機会を得られるから、この世界に飛び込んだのです」
医師をめざし、泌尿器科を選ぶまでの鳶巣先生の道のりはきわめてユニークです。70年代、学生運動のただなか、鳶巣青年は「既存の価値観を壊し、世界を変える」ために闘っていました。しかし、ある日、思索の矛先が自分の内側に向かうようになったのです。「正しい価値観とは?この世に普遍的な正義、教えはあるのか?」内省の殻に閉じこもるように、引きこもり同然の生活をしながら、あらゆる哲学、宗教を疑う日々。
「いわゆる、うつだったのかもしれませんね」
外出もせず、食事も満足にとらず、やせ細った鳶巣青年は、下宿のおばさんに、裏の柿の実を取ってくれないか、と声をかけられました。フラフラしながら柿の木に登り、柿の実を一つ、また一つ取るうちに、不意にその柿の実に食いつきたくなったそうです。
「あの味は忘れられません。本当にうまかった。生きているという実感。こんなにうまいものがあることを、何で自分は忘れていたのだろう。涙が知らずに流れてきました」
生の実感、それは積み重ねられた書物のなかにではなく、一つの柿の実に凝縮されていました。生の実感を得られる世界を求め、「優しいことがすべて。優しさに勝るものなど何もない」を信条に、職業を模索します。医学部入学前には、いったん一般企業で働いたこともありました。そして、「生きざまに本音で向かい合う。それで社会が変わるかもしれない」と思い、医療の道を選びます。
泌尿器科を選んだのも、学生運動を通しての縁。僻地(へきち)の病院にでも行こうかなと思っていた鳶巣先生に声をかけてくれたのが、当時の団交の相手側の教授でした。その教授が泌尿器科だったそうです。
「立場は敵対していましたが、実は、私という人間をきちんと評価し、信ずるに足る人間と思ってくれていました」
その後は、東京・築地(つきじ)の国立がんセンター、静岡県立静岡がんセンターで、臨床はもちろん、すぐれた管理者としての腕を発揮し、がんという病気を契機に、人があたかも生まれ変わったかのように変わる現場を、多く目撃してきました。とくに静岡では、思いを共有するスタッフに恵まれ、めざす医療の一つの形を提供できたのではないかといいます。
そして、今年、もう一度臨床の現場に立ち返りたいとの思いで、聖路加国際病院に。
「がん診療特別顧問という立場から、がん診療の質を高める役割を果たし、東京という地の特殊性を考慮したうえで、チーム医療や周辺地域との連携、医療資源の効率的な配分を考えていきたいのです。本音は、じっくり患者さんと向き合うことに専念したいんですけどね」
前立腺がんの患者さんにひとこと。
「説明を受けたら、自分なりにじっくり考えて。どの治療法も効果と安全性は確立されています。それでもリスクや予想外の展開は必ずあり得ます。だからこそ、腹の据わりがよい方法をみつけてほしいのです」
鳶巣賢一(とびす・けんいち)先生
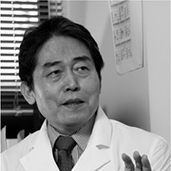
聖路加国際病院 がん診療特別顧問(泌尿器科)
1949年、兵庫県生まれ。京都大学経済学部経営学科卒業、日本電信電話公社(現NTT)入社。その後、京都大学医学部入学、卒業。同大泌尿器科研修医、滋賀県成人病センター泌尿器科を経て、国立がんセンター病院泌尿器科。2002年4月より静岡県立静岡がんセンター院長。2011年1月より現職。

