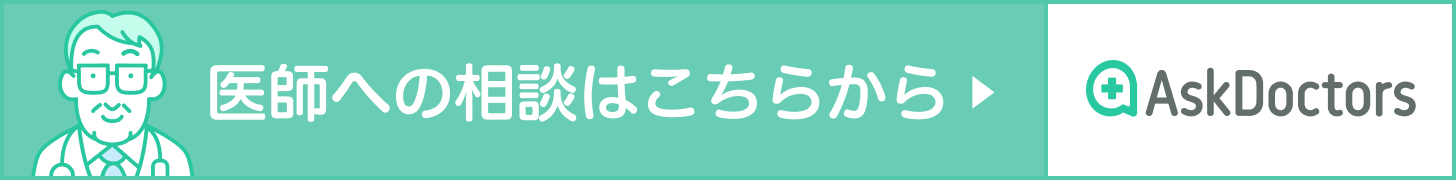相談:ステージ0の乳がんの可能性、悪性か良性か微妙な診断でセカンドオピニオンを受けたい
2013年子宮内膜症と診断され、リューブリン注射を6回受けたあとに、ディナゲストを服用開始し、現在も1日1錠を服用中です。
2020年1月に、右胸の小さなしこりに気がつき地元のクリニックを受診しました。マンモグラフィー、エコーともに異常なしのため、3か月ごとに経過観察を行っていましたが、腫瘤の大きさは8x5x3mmで1年間変わりませんでした。その後、針生検で悪性と診断され、手術のできる病院を紹介されました。
2020年2月~3月に、紹介された病院では、病理の見直しがあり良性といわれました。しかし「悪性の可能性を否定できる要素が見つからない。エコーの結果大きさは変わらず異常なし」とのことでした。念のため受けたMRIの読影医には、「小さすぎてわからない」といわれ、外科生検で腫瘤のみを取ることを勧められました。悪性と確定したら再度手術で周辺部分を取るとのことです。凍結療法かラジオ波焼灼療法による切らない治療を希望し、現在受診中のがん専門病院を受診しました。
2020年5月に受けたマンモグラフィー、エコー検査とも異常はなく、大きさは1cm未満でほぼ変わりません。以前に受けた針生検の病理の見直しの結果、「グレーとブラックの境目なので、悪性と見たほうが良い」と診断され、腫瘤と周辺部分を含む3~4cmを一度に取る手術を勧められました。「手術で取った組織を調べたら、悪性ではなかったということもありうる」とのことで、腫瘤だけを取って病理検査をしてもらえないかと頼みました。針生検で採取した検体の病理検査で悪性の可能性が高いと出ているため、新たな生検は意味がなく、おそらくステージ0だと思うが、この段階で悪性と捉えて3か月から半年ぐらいの間には手術をした方がいいとのことでした。 ラジオ波焼灼療法は、ステージ1でないと適応にならないし、皮膚に近いところに病変があるため火傷の可能性もあるといわれました。
病理の見直しで確定診断がつかず、もしかしたら悪性ではないかもしれないのに、腫瘤の周辺部分も手術で取るということにものすごい抵抗があります。セカンドオピニオンを受けたいと、必要資料を準備してもらっています。私は悪性であるという確定診断が出るまでは、不要な手術は避けたいと考えています。できれば今の病院で外科生検かマンモトームでもう一度組織診をしてもらいたいのですが、その必要はなしといわれました。ここでの選択肢は、悪性との確定診断がついたものとして手術で周辺部分まで取るということしかないようです。
確定診断をしてほしいという場合、セカンドオピニオンを受診することに意味はあるのでしょうか。セカンドオピニオンではなく、新規に受診して再度組織を取って調べてもらうのがいいのかと考えていますが、この判断は正しいですか?また、今の病院にかかりながら、他院を受診することは可能ですか?
(本人、女性)
回答:セカンドオピニオンは、患者さんに最善な治療を担当医と判断するために別の医師の意見を聞くことが目的
セカンドオピニオンで得た情報は、担当医にフィードバックすることが大切です。病状や進行度により、時間的余裕がない場合もあるため現在の病状と治療の必要性についての確認も大切です。複数の医師の意見を聞くことで、治療法の選択に迷うこともあります。そうならないために、最初の意見を十分に理解しておくことも大切です。セカンドオピニオンを受けた後、担当医と相談した結果、セカンドオピニオンを受けた先の病院で治療を受けることになった場合は、あらためてこれまで受けた検査の結果や治療内容などと一緒に紹介状を書いていただき、治療を引き継くのが一般的です。その場合でも、先の病院の医師は、患者さんの病状などを理解している身近な医療者の1人であることに変わりはありません。
セカンドオピニオンを受けられるご予定があれば、新たに生検を行うことに有益性があるかをお聞きになってみてはいかがでしょうか。早期の乳がんで、細胞や少量の組織のみで診断困難な病変の場合、過小診断や過大診断のどちらの可能性もあるためセカンドオピニオンで別の医師の意見を聞いてみることもいいと思います。
画像誘導下で行われる針生検の診断能力は、外科的生検の能力に近似します。画像誘導下で行われる針生検を行うことで、外科的処置の回数が減少し有害事象が少なくなるといわれています。外科的生検を行うことで生じる可能性のあるデメリットは、整容性の低下、乳房温存手術やセンチネルリンパ節生検を行うときに生じる可能性が報告されています。そのため、一般的な乳がんの確定診断では、外科的生検より画像誘導下針生検が標準とされています。
参考文献
乳がん確定診断において,画像誘導下生検手技は外科的生検よりも推奨されるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/kenshingazo/bq1/
医師に相談したい場合、現役医師が回答する「AskDoctors(アスクドクターズ )」の利用もおすすめです。