前立腺がんの「化学療法」治療の進め方は?治療後の経過は?
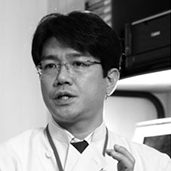
- 鈴木啓悦(すずき・ひろよし)先生
- 東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科教授
1965年東京都生まれ。千葉大学医学部卒。米ジョンズ・ホプキンス大学医学部オンコロジーセンター研究員、千葉大学准教授、同診療教授などを経て、2010年から現職。2011年東邦大学医療センター佐倉病院院長補佐、医療連携・患者支援センター部長。
本記事は、株式会社法研が2011年7月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん」より許諾を得て転載しています。
前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。
抗がん薬を用いて転移がんに対応する
抗がん薬を使って、がんの増殖や痛みを抑えます。 QOL(生活の質)を高めながら、がんと上手につきあっていく治療法です。
がん細胞の分裂を止めるドセタキセルが有効
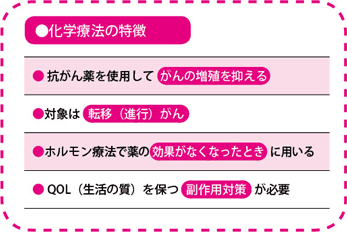
前立腺がんの化学療法は、精巣腫瘍(せいそうしゅよう)や膀胱(ぼうこう)がんの治療と違って、根治をめざすものではありません。抗がん薬を使いながら、がんの増殖や痛みを抑え、がんと上手につきあっていく治療法です。
化学療法の対象となるのは、転移(進行)がんの患者さんで、ホルモン療法を続けた結果、薬の効き目が悪くなってきた場合です。限局がんや、局所進行がんの患者さんは対象にはなりません。また、転移(進行)がんであっても、初めから化学療法を行うことはありません。ホルモン療法だけで十分対応できる場合もあるので、最初にホルモン療法を試してみることが大切です。
前立腺がんの化学療法に使う抗がん薬はドセタキセル(商品名タキソテール)という点滴用の薬で、日本では2008年に前立腺がんに対して健康保険が適用されました。
ドセタキセルは微小管阻害薬とも呼ばれています。細胞の分裂には細胞中にある微小管というたんぱく質がかかわっていますが、ドセタキセルはこの微小管の働きをじゃまする性質をもつ薬です。ドセタキセルによってがん細胞は分裂できなくなり、死滅します。
また、ドセタキセルはアンドロゲン受容体の働きを抑える力もあるとされています。アンドロゲンは男性ホルモンの総称で、男性ホルモンであるテストステロンは、細胞の男性ホルモンの受け皿であるアンドロゲン受容体を介して作用するしくみになっていますが、その働きを抑えてしまうのです。前立腺がんは男性ホルモンで増殖する性質があり、ドセタキセルはこの経路も抑えることで、より効果を高めているのです。
さらにドセタキセルには骨転移によっておこる疼痛(とうつう)をやわらげる働きもあると考えられています。
ドセタキセルは抗がん薬のなかでは副作用の少ない薬ですが、手足のしびれやむくみ(浮腫(ふしゅ))などがみられるため、この副作用対策として、副腎(ふくじん)皮質ステロイド薬のプレドニゾロン(商品名プレドニゾロン、プレドニンなど)、あるいはデキサメタゾン(商品名デカドロンなど)を併用するのが一般的です。
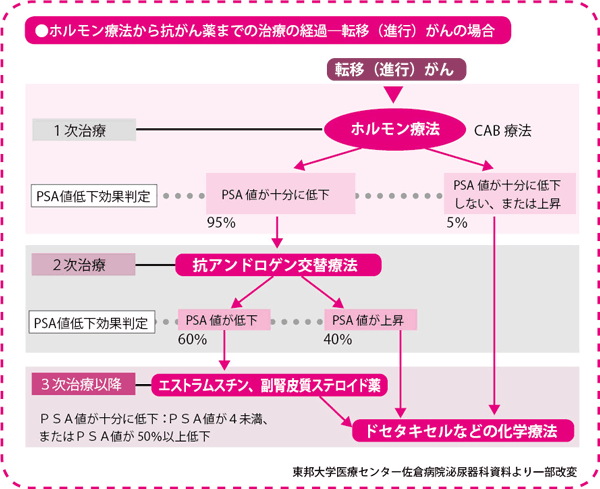
ホルモン療法のあとに化学療法を始める
化学療法に入るタイミングを説明したものが、上の図です。転移(進行)がんでも、いきなり化学療法に入ることはありません。まずホルモン療法から始めます。
ホルモン療法を行っても、薬が効かなかったり、最初は効いていたのに、使っているうちにだんだん薬が効かなくなったりすることがあります。薬の効果はPSA値で判断します。PSA値が十分に下がれば効果ありと判断しますが、十分に下がらなかったり、逆に上がったりした場合は効果なしと判断します。
ホルモン療法で一般的な治療は、LH-RHアゴニスト(酢酸ゴセレリン/商品名ゾラデックス、酢酸リュープロレリン/商品名リュープリン)と、抗アンドロゲン薬(ビカルタミド/商品名カソデックス、フルタミド/商品名オダインなど)を併用するCAB療法です。LH-RHアゴニストの代わりに精巣摘除術を行う場合もあります。
CAB療法でPSA値が十分に下がった場合は、そのまま治療を続けます。多くの人がCAB療法でPSA値が十分に下がるので、すぐにドセタキセルで治療を始めることにはなりません。
ただし、少数の患者さんでPSA値が十分に下がらなかったり、上がったりすることもあり、その場合はドセタキセルによる治療を始めます。
一方、PSA値がある程度下がった場合は、そのままCAB療法を継続しますが、2、3年たって効果が落ちてきた場合は、抗アンドロゲン薬の種類を変えます。これを抗アンドロゲン交替療法といいます。
抗アンドロゲン薬を変えてもPSA値が上がる場合は、ドセタキセルによる治療を開始するか、もしくは女性ホルモン薬と抗がん薬の作用をあわせもったエストラムスチン(商品名エストラサイトなど)や、副腎皮質ステロイド薬などによる治療に切り替えます。
抗アンドロゲン薬を変えてPSA値が下がった場合は、そのまま治療を続けますが、薬が効かなくなってきたら、エストラムスチンや副腎皮質ステロイド薬などによる治療に切り替えます。この治療が奏効しない場合も、ドセタキセルによる治療を始めるタイミングとなります。
現在のところ、ドセタキセルを使った化学療法は最後の手段と考えられているので、ホルモン療法である程度効果があればなるべく続けるようにし、どうしてもがんの進行が止められないと判断した場合に、ドセタキセルを使った化学療法に踏み切るという流れになっています。
●ドセタキセル使用の対象となるのは
| 1 前立腺がんの診断が確定し、転移(進行)がんの場合 |
| 2 1次治療としてLH-RHアゴニストと抗アンドロゲン薬の併用療法(CAB療法)を行い、定期的にPSA値による経過観察をして、かつ次の条件を満たす場合 (1)1次治療中にPSA再発をおこし、抗アンドロゲン薬を一定期間休止してPSA値の経過観察(抗アンドロゲン薬をいったん休止すると、PSA値が下がる場合がある) (2)抗アンドロゲン薬を休止後、別の抗アンドロゲン薬に変更(抗アンドロゲン交替療法) (3)交替療法開始後、原則として少なくとも3カ月以上のPSA値の経過観察 |
治療の進め方は?
治療開始のタイミングにも、指標があります。 ドセタキセルの副作用を抑えるため、薬の分量を減らし、投与間隔をあける工夫をしています。
ベストのタイミングで治療を始めることが大切
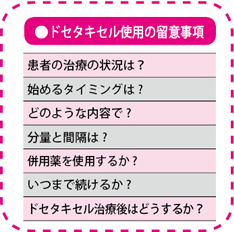
ドセタキセルによる治療開始は、慎重を期す必要があります。
ドセタキセルによる治療でPSA値が30%以上下がった人は、明らかに予後がよいことがわかっています。下の上図は私が以前勤務していた千葉大学医学部附属病院でのデータです。横軸が生存期間、縦軸が生存率を示しています。PSA値が30%以上下がった人のほうが、長く生存できていることがわかります。
さらに詳しく調べてみると、PSA値が30%以上下がる人は、ある特徴をもっていることがわかりました。それには下の表に示す四つの条件が関係しています。
この条件からリスク分類をすると、4条件のうちどれか一つでも当てはまるようになったら、そのタイミングでドセタキセルによる治療を始めれば、PSA値が30%以上低下する確率が高いと考えられます。
もちろん、4条件がみられないうちからドセタキセルによる治療を始めてもいいのですが、ドセタキセルによる治療が最終手段であることを考えると、踏み切るタイミングはなかなか難しいものがあるといえるでしょう。
治療開始は早すぎても遅すぎてもよくないのです。ベストのタイミングで治療を始めるためには、血液検査や骨シンチグラフィなどで、病状をしっかり把握しておくことが大切です。
薬の分量や投与間隔を日本人に合わせる工夫
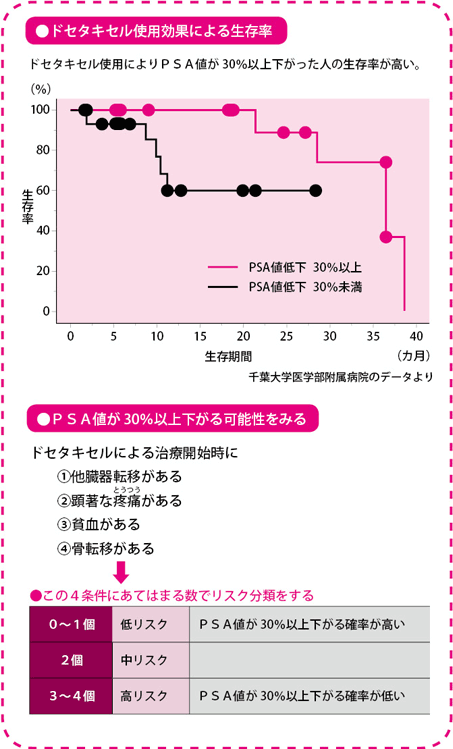
ドセタキセルの分量と投与間隔は、細かく決められていて、体表面積1m2当たり1回70~75mgの量を1時間以上かけて点滴することになっています。正式には体表面積ということですが、体重によって量が変わると考えれば、大きくは違いません。体重の重い人は薬の量がそれだけ増え、体重の軽い人は、それだけ少なくなるということです。
1回点滴したあとは3週間の間をあけて、再び70~75mg/m2の量を1 時間以上かけて点滴するしくみです。この間、プレドニゾロン、あるいはデキサメタゾンといった副腎皮質ステロイド薬を併用することになっています。プレドニゾロン、デキサメタゾンはいずれも飲み薬です。
ドセタキセルは1回75mg/m2が標準の量として定められていますが、実はこれは欧米の基準に合わせたもので、日本人の場合はもう少し減らした量でないと副作用が強く現れる傾向があります。
とくに問題となる副作用は骨髄抑制です。骨髄抑制とは、骨髄の働きが低下して、赤血球、白血球、血小板などが十分につくられず、これらが減ってしまう現象をいいます。なかでも注意しなければならないのが白血球の減少です。白血球が減ると感染症にかかりやすくなるため、生命の危険を招きます。
また、ドセタキセルは投与量の総量が一定量を超えると、手足のしびれ、むくみ(浮腫)が半数以上の人に出てきます。
そこで、私の勤務する施設(東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科)では、患者さんの年齢や体力も考慮しながら、ドセタキセルの量を50~60mg/m2程度に抑え、間隔も5~6週間あけるなど、分量を減らし、間隔を長くする「ロードーズ、ロングインターバル」の工夫をしています。これにより、治療効果を維持しながら、副作用をできるだけ抑える治療が可能になっています。
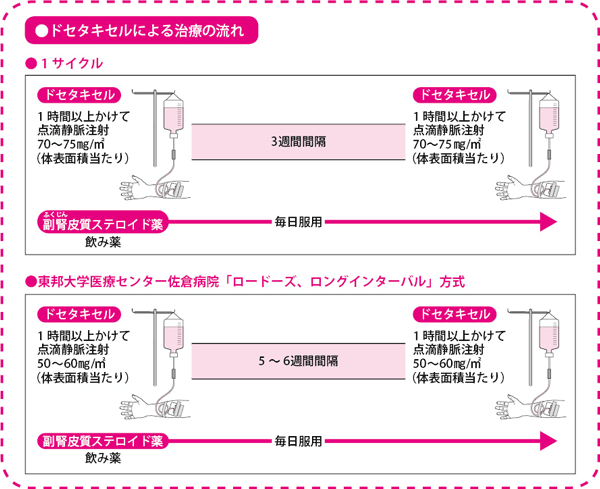
治療後の経過は?
骨髄抑制などの重大な副作用に注意が必要です。 つらい副作用がみられたら、投薬を休んだり、間隔を延ばしたりしながら対応していきます。
ドセタキセルの治療は効果がある限り継続する
先に説明した、PSA値が30%以上下がる確率に関する4条件でみたリスク分類に基づいて、生存率を計算した報告があります。
それによると、低リスクの場合は全生存率の中央値は25.7カ月です。約2年は生きられる計算になります。中リスクの人は18.7カ月、高リスクの人は12.8カ月です。あくまで統計的に出した数字なので、これより長く生存できる可能性はあります。
ドセタキセルの治療は、効果があるうちはそのまま続けていくのが原則です。私たちの施設では、先に説明した「ロードーズ、ロングインターバル」の考え方で、できるだけ副作用を抑えながら、長い期間、薬を使うことができるように工夫しています。
研究レベルでは、しばらく治療を続けて、いったん休薬し、PSA値が上がってきたら再び治療をするといった、間欠的な化学療法も試みられています。
海外では、50%以上の人に効果があったという報告も出ていますが、まだ十分なデータはそろっていません。
副作用によっては休薬や投薬間隔の工夫で対応
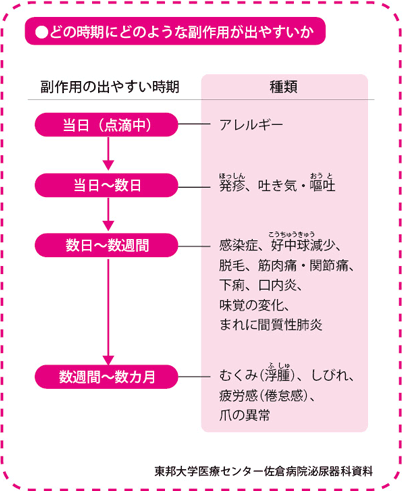
副作用によっては、投薬を休んだり、投薬と投薬の間隔を延ばしたりするといった工夫も必要になります。ドセタキセルによる治療の主な副作用を右図にまとめました。
点滴している最中にアレルギー反応がおこってショック症状に陥ることがあります。この場合はすぐに治療を中止しなければなりません。
当日~数日の期間には、発疹(ほっしん)や吐き気、嘔吐(おうと)などがみられることがあります。
数日~数週間の期間では、骨髄抑制に注意が必要です。骨髄抑制により好中球(こうちゅうきゅう)(白血球の一種)が減少すると感染症にかかりやすくなります。発熱などがみられたら、感染症を疑わなければなりません。
ほかに、脱毛、筋肉痛・関節痛、下痢、口内炎、味覚の変化などがみられることがあります。
まれですが間質性肺炎になることもあります。間質性肺炎は命にかかわる副作用なので、すぐに抗がん薬による治療を中止しなければなりません。
数週間から数カ月の期間になると、むくみ(浮腫)や手足のしびれ、疲労感(倦怠(けんたい)感)、爪の異常などがみられることがあります。
ドセタキセルによる化学療法は最終手段と説明しましたが、ドセタキセルによる治療が効かなくなった場合に、女性ホルモン薬と抗がん薬の作用をもったエストラムスチンを、ドセタキセルと併用してみるという方法があります。
ただし、この治療では、心血管系や消化管に重大な副作用をおこすことが少なくありません。心血管系は15%、消化管のほうは20%と高い確率になっています。
このため、エストラムスチンとドセタキセルの併用療法を行う場合、血栓塞栓(そくせん)症、心筋梗塞(こうそく)、心不全、狭心症、血管浮腫、胸水、肝機能障害、黄疸(おうだん)などの病気になったことのある人や、これらの病気になりやすいと考えられる人には注意が必要です。
カバジタキセルなど新薬も続々開発中
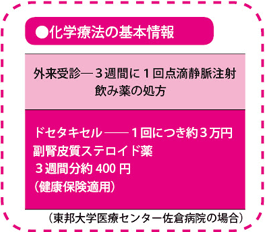
現在はドセタキセルによる化学療法が最終手段となっていますが、実は今、複数の抗がん薬の臨床試験が行われており、その結果しだいでは、今後、新しい抗がん薬が前立腺がんの治療に使われるようになるかもしれません。
有力な薬の一つがカバジタキセルという薬です。国際的に多施設での共同研究が進んでいます。アビラテロンという薬も研究が進んでいて、効果が期待されています。このほかにもいくつか臨床研究に入っているものがあります。
副作用が強くドセタキセルによる治療ができなくなった場合、あるいはドセタキセルの治療効果が認められない場合は、積極的な治療はやめて、痛みが出ないようにするなどQOL(生活の質)を高めることを治療の中心におく緩和療法をすることになります。
前立腺がんの緩和療法のポイントは、骨転移による痛みをやわらげること、脊椎(せきつい)転移による脊髄(せきずい)まひ対応、排尿に関するトラブルの改善などとなります。目的は病気の治療ではなく、痛みや不快を取り除くことなので、副作用に注意しながら進めていきます。
なお、ドセタキセルの点滴は、薬剤費の自己負担が1回当たり約3万円(健康保険3割負担の場合)です。
●骨転移の痛みにはゾレドロン酸が効く
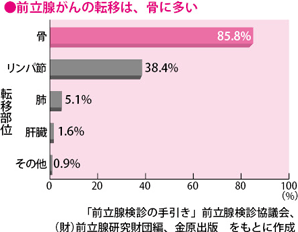
前立腺がんは骨に転移しやすい性質があります。進行がんが転移した部位を調べると、下図のように8割以上が骨に転移していました。
骨に転移しているかどうかは、骨シンチグラフィと呼ばれる検査で調べることができます。骨に転移すると痛みが出ます。
ホルモン療法が効果を現すと骨の痛みは感じなくなったり、やわらいだりしますが、効果が薄れてくると、また、痛みが出てきます。
骨の痛みに対しては、鎮痛薬、放射線外照射、手術、ストロンチウム89の静脈注射などの対処法がありますが、有力な治療法の一つがビスホスホネート製剤であるゾレドロン酸水和物(商品名ゾメタ)という注射薬を点滴することです。3~4週間に一回、点滴することで、骨の痛みが改善され、ほかの鎮痛薬を減らすことができます。ゾレドロン酸水和物の点滴には健康保険が適用されています。

