がんプラス5周年対談企画 がん治療の進歩と5年後のがん治療―今を強く生きる人に向けて―


2022.9 取材・文:がん+編集部
この5年間で、がん医療は飛躍的に進歩してきました。一方で、5年前には67.6%だった5年生存率は、2022年の発表では68.9%と、わずか1.3%の改善に留まっていることが統計でも示されています※。この数字を単純に見ると、「がんと診断された10人のうち約7人が、5年後も生きている」ということになります。一方で、その全員が、「がんになる前の生活に戻っている」というわけではありません。5年生存率の改善は数字で見るとわずかですが、治療を受けた人たちの生活の質に改善は見られているのでしょうか。多くの人たちが社会復帰を望む中で、それを当たり前に実現するためのがん医療とは――。この先5年のがん医療の進展も見据えつつ、国立がん研究センター 先端医療開発センター長の土井 俊彦先生と、認定NPO法人 5years理事長の大久保 淳一さんに、それぞれの立場からお話しいただきました。
※5年前とは2007~2009年診断例、2022年の発表とは2011~2013年診断例、それぞれ全国がんセンター協議会加盟施設における5年生存率による。
この5年間で、がん治療は「延命治療」から「治癒率を上げる治療」に

土井先生
従来、抗がん剤治療は、がんの治癒が困難な状況の中で、延命を主な目的とした治療でした。そんな中で、「治癒率をできるだけ上げるような治療法を開発しよう」というのが、新たながん治療法開発に関する、この5年間での大きなテーマだったように思います。
治癒率を上げるために、2つの方法が考えられます。1つは「万能薬の開発」、もう1つは「特定の薬で治療効果が得られる患者さんを見つけること」です。万能薬はそう簡単に作れるものではありませんが、もう1つの、薬にマッチした患者さんを見つけて治療する方法を実現するために進められたのが、がんゲノム医療です。がんゲノム医療は、遺伝子パネル検査により、その人のがんで起きている遺伝子異常を特定し、その遺伝子異常に対する分子標的薬による治療を行うというものです。海外では、10年くらい前から取り組まれていますが、日本では若干遅れています。
がんゲノム医療では、特定の薬での治療効果が期待できる患者さんを絞り込める一方で、課題もあります。例えば、遺伝子パネル検査で異常が見つかった遺伝子ごとにがんを分類すると、それぞれの遺伝子異常に該当する患者数は、「大腸がん」「肺がん」などの従来の分類より、少人数になります。
ある遺伝子の異常ががんの原因になっているとわかり、それに対する分子標的薬の候補が見つかったとしても、その薬が承認されるまでには、臨床試験を経る必要があります。しかし、該当の患者数が少ないと臨床試験の実施が困難になり、なかなか治療薬の開発が進みません。また、治療薬が開発されても、対象となる患者数が少ないと、薬価が高くなってしまいます。現状、こうしたことが課題として挙げられています。
一方で、こうした現状を打開するために、万能薬とまでは言えませんが、もっと大勢の患者さんに広く効果があるような治療薬を開発するための取り組みも始まっています。iPS細胞の技術を使った「再生・細胞医薬品」「武装化抗体」「光免疫療法」などです。
大久保さん
治癒を目指したさまざまながん治療が、今まさに開発されているというわけですね。しかし、こうした取り組みは、この5年間というよりもっと以前からの取り組みのように思えますが――。
土井先生
確かに取り組みは5年以上前から始まっていましたが、薬剤開発の鍵となる「ナノテクノロジー」(原子や分子レベルの物質を扱う技術)の分野が、この5年で飛躍的に進歩しました。この技術により大きく開発が進んだ治療法の1つが「武装化抗体」です。武装化抗体は、抗体とがん細胞を攻撃する物質を結合させた医薬品で、抗体と抗がん剤を結合させた「抗体薬物複合体」、抗体と放射性物質を結合させた「放射免疫療法薬」などが、これに該当します。光免疫療法で使用される、抗体に光感受性物質を結合させた薬剤も、同じ武装化抗体の仲間です。
この武装化抗体の、抗体と抗がん物質の結合部分である「リンカー」の性能が、ナノテクノロジーの進歩により改良されました。開発初期の武装化抗体では、がん細胞にたどり着く前にリンカーが切れ、体内のがんではない部分に抗がん剤や放射性物質が取り残されてしまい、肝心のがんで治療効果が十分発揮できないといった課題がありました。しかし、簡単には切れないリンカーが開発されたことにより、狙い通りに効率よく武装化抗体ががん細胞に届くようになりました。そのため、副作用が減り、がん細胞への攻撃力もアップしました。
必要な人に必要な治療を届けるがん医療を望む

大久保さん
私はがん経験者です。15年前に精巣腫瘍になりました。ブレオマイシンの副作用で肺線維症になり、生死をさまよった時期もありましたが、奇跡的に助かりました。そこから7年後には、趣味だった100kmマラソンにも復帰できました。
治療を受けながらも、外資系の証券会社で、治療前と同じように働いていました。そんな中で、他のがん患者さんから「大久保さんと会って、がんの経験談を聞きたい」と度々言われるようになり、いろいろな病院で患者さんを励ますような活動をするようになりました。
そうして過ごしているうちに、自分はこのまま普通に会社で働いていても良いのだろうかと自問することが多くなってきました。「奇跡的に助かったのだから、なにか社会に恩返しをしたい」という思いが徐々に強くなり、自分が治療中に欲しかったものを具現化しようと考え、立ち上げたのが、がん経験者コミュニティ「5years」です。
がん治療中に私が欲しかったものは、2つあります。1つは「元気になった患者さんの情報」、もう1つは「先にがんになった経験者に相談できるインフラ」です。なぜ、この2つが欲しかったかというと、私を含め、がんと診断された人たちは、がんを治すことだけではなく、社会に復帰するまでを目標に、治療に臨んでいたからです。その目標を達成するためには、社会復帰をした先人たちの経験が必要だったのです。
5yearsは、がん患者さんのインターネットコミュニティで、現在1万9,000人の登録者がいます。朝から晩まで、登録者が交流している様子を見ていますが、私ががん治療を受けていた15年前と今とで、がん患者さんが思っていることに変わりはないと思っています。患者さんたちの変わらない思いは、「生きたい」という思いと、生きているだけではなくて、「元の社会生活を取り戻したい」という思いです。
この2つの思いに関連して、私は、この5年でやや頭打ち気味である5年生存率が、今後標準治療の継続により、ほんの数%向上することよりも、より社会に復帰しやすくなるような医療の進歩に期待したいと考えています。
今の標準治療は、必要のない人にも行われているのではないかと思うことがあります。5年生存率が70%近くにまで向上し、治癒率が改善したのは、医療の進歩のおかげだということは十分に理解していますし、意味があることだと思っています。しかしこれ以上、全員に対し、同じような標準治療を行っていくことで、5年生存率がさらに1~2%程度向上したとして、そこにどんな意味があるのかと、疑問に感じることもあります。必要でない治療を受ける患者さんが増えるのではないかという心配もあります。
土井先生
必要性をどのように決めるかは、とても難しい問題です。標準治療でも、患者さんにとっては必要性があるものとないものがあり、必ずしも全員に対し同じように治療が行われているというわけではありません。
例えば、愛媛のみかん農家の患者さんを診たときのことです。「今、みかんを収穫しないとみかんが全部腐ってダメになってしまうので、なんとかなりませんか」と相談されました。そんなタイミングで診療ガイドラインに書いてある通りの治療を行うために、その人の生活にとって重要なみかんの収穫を犠牲にして入院してもらうのは、その患者さんの治療として最良ではないと私は判断しました。ですので、そのときには、患者さんの希望を聞きながら、その間にできる治療を提案し、無事にみかんの収穫をしてもらってからまた治療に戻るといった方針になりました。
治療方針は、患者さんとのコミュニケーションの中で決めていくものです。標準治療は、診療ガイドラインに書いてある通りに行わなければならないというものではありません。ガイドラインは、守らなくてはならない法律ではなく、あくまでも診療の参考となるものです。
大久保さん
まさに、患者さんは、みかん農家さんの例のような提案が欲しいと思っています。必要な人だけが、必要な治療を受けられるような医療革命が起これば、ありがたいと思います。
例えば、乳がんの患者さんにホルモン療法が行われていますが、この治療を受けることで、子どもを産む機会を失っている20歳代~30歳代の患者さんもいます。子どもを望んでいる人を含め、ホルモン感受性乳がんの全ての患者さんに、標準治療だからという理由でホルモン療法を行うのは本当に正しい選択なのかどうかと疑問に思っています。
標準治療であっても、「そのタイミングでその治療を必要とする患者さん」と、「そのタイミングでは別の選択肢を必要とする患者さん」を、土井先生のようなエキスパート医師でなくても、一様に見分けるようなことができるようになれば、不必要な治療を受ける患者さんは減りますね。
土井先生
現状はまだ、患者さんごとに「必要とされる治療」を全体的に見分けることはできておらず、少し時間がかかると思います。
5年後のがん医療、「ドラッグラグの解消」が鍵

大久保さん
今後のがん医療について、標準治療をこのまま続けていくことより、「必要な人だけに行う治療」「より負担の少ない治療」「がん患者さんがより社会復帰しやすいような治療」など、患者さんの生活に関わる部分を改善するような方向性を考えることも重要なのではないかと思っています。標準治療のあり方や新たな治療開発など、先生は、今後がん医療はどのようになっていくのが望ましいとお考えですか。
土井先生
がんゲノム医療など、現在行われている最先端の医療は、標準治療の効果が期待できなくなった患者さんを対象に行われています。新たな治療法を開発するために行われている治験(臨床試験)も同様に、標準治療の効果が期待できなくなった、もしくはご本人が望んでいる治療がなくなったような患者さんに、治療を兼ねて試験に参加して頂き、行っています。
標準治療は、患者さんの病態に応じ、医学的根拠(エビデンス)に基づいた治療選択肢を提案するものです。現在治験が行われている新たな治療法なども、今後エビデンスが蓄積され、より治癒率の高い標準治療として置き換わっていくと期待しています。
大久保さん
それなら、最先端の医療は患者さんの希望となりそうですし、まだこの先、標準治療による治癒率の向上も望めそうというわけですね。開発中の新たな治療法について、どのくらいの効果が認められた場合、良い治療法が出てきたとお感じになられますか。
土井先生
有効な治療法が見つからない患者さんに対する早期の臨床試験では、10人中3人くらいに効果が認められれば、良い治療法が出てきたと感じます。ただし、治療効果があっても社会復帰できないほど毒性の強い薬ではいけません。その後の治療を受けなかったら余命3か月の患者さんが、その治療を受けることで1年間「元気に」過ごせれば、その間にたくさん出来ることがあるでしょう。そうした場合、この治療はその患者さんにとって「良い治療」だと言えると思います。
大久保さん
そうした治療法を開発していくうえで、障害となっていることはありますか。
土井先生
第1相の臨床試験の実施、でしょうか。現在開発中の薬剤、特に分子標的薬は、その薬の効果が期待できる人を、あらかじめ検査で絞り込み、その人たちを対象に臨床試験を行っているため、試験に参加できる患者さんの数は、どうしても限られます。これが、開発の遅れにつながっていると思います。
また、複数のがんの原因遺伝子の検査が一度にできるようになったとともに、各遺伝子異常に基づいて開発されている分子標的薬の種類も増えており、これに伴い、初めてヒトに対してその薬が投与される、第1相試験の件数も増えています。
第1相試験は、安全性の確認が最も重視される試験です。まず第1相試験が行われないと、その薬は承認されることがありません。ところが、臨床試験を行う施設の負担は大きく、臨床試験を実施できる医師の人数も限られているため、試験は思うようなスピードでは進みません。また、現状、国内のがん治験のうち、第1相試験の9割以上が、国立がん研究センターの中央病院と東病院を中心として実施されているため、首都圏から離れた地域にお住まいの患者さんが参加しにくく、地域差が生じています。
こうして日本は海外から遅れを取り、諸外国では承認されている薬が日本では使えないという、いわゆる「ドラッグラグ」が起こっています。この問題を解決するためには、日本全国のがん拠点病院で第1相試験が実施できる体制を、早く整備することが重要だと考えています。
ガイドラインの先にある「患者さんと向き合った医療」
大久保さん
がんと闘い、残念ながら亡くなっていく方がいるたびに、最終的に「今の標準治療では、もうこれ以上何もできない」という状況になるのは、残酷だなと思います。標準治療ができない方でも、何かしら受け続けていたほうが、「もうできる治療は何もない」と諦めて過ごすよりは良いのではないかと思うこともあります。もちろん、民間療法は、医学的根拠がありませんし高額すぎるという問題があるのは知っており、特に商売目的の金額設定は許せません。患者さんが絶望的な気持ちにならないようにする何か良いアイデアはありますか?

土井先生
患者さんにとって、補完療法(民間療法)が「信じられるもの」であれば、私も頭ごなしに全否定はしません。しかし一方で、治療を行う側が、それがどういった治療であるのかをきちんと説明できていない、もしくは意図的にしていないのが現状で、これは問題だと思っています。
私は、標準治療が終了した患者さんに対して、「もう治療法はありません」と、すぐにお伝えはしますが、納得されにくいときもあります。その場合、何もないではなく、希望される患者さんに、有効であった薬剤で効かなくなった薬について「もし、何かを望まれる場合は、もう1度同じ薬を試してみましょうか。4週間試してみて、副作用が辛かったり、効果が得られなかったりしたら、緩和ケアを考えましょうか」といった提案をする場合もあります。患者さんに突然、もう治療法はないという状況を突き付けるのではなく、標準治療やガイドラインの、その先にある「患者さんと向き合った医療」を考え、作っていくことが大切だと思っています。
がんゲノム医療の現状と展望
大久保さん
がんゲノム医療は、検査が治療につながる確率、また、治療を受けても効果が得られる確率が非常に低いという印象があります。遺伝子の検査をして、異常のある遺伝子が見つかり、その異常に合わせた治療法が見つかった人でも、治療効果が得られる人は、4人に1人もいないという印象ですが、実際どのくらいなのでしょうか。
土井先生
がん種にもよりますが、全体で見ると、がん遺伝子パネル検査で治療法が見つかった人の中で、その治療の効果が得られている人は10%程度だと思います。先ほどもお話ししましたが、それぞれの分子標的薬の効果が見込める患者さんを、あらかじめ遺伝子の検査で見つけ出し、グループ分け(=遺伝子に基づいたがんの層別化)をすることで治療につなげるシステムを作っていこうというのが、がんゲノム医療です。今のところ、治療効果に結び付いているのは10%程度ですが、このグループ分けがしっかり進んでいくことで、確実な改善が見込めると考えています。
遺伝子に基づいたがんの層別化とともに重要なのが、患者さんの気質や生活に基づいた個性による層別化だと考えています。この方法は、まだ研究もされていませんし十分に理解されてもいません。さっきの、みかん農家さんの話は、まだ例外的だったと言えますが、今後、患者さんの層別化が明確に行われるようになり、層別化されたがん医療と層別化されたがん患者さんが、標準的につながっていけば良いなと思っています。そして、病院は、この両者をマッチングさせる場になるのだと考えています。
ところで、最後にもう1つ、未来のがん医療として期待できるかも知れないと思っているものを紹介します。それは、がんが検出できない、ごく初期の段階でがん細胞を死滅させ、「がんを発症させない医療」です。病気があるかないかに関わらず、ヒトの体の中では1日に5,000~1万個程度のがん細胞が発生しています。こうして発生したたくさんのがん細胞は、通常、免疫の仕組みが排除しているため、がんを発症しません。しかし、免疫が疲弊してくると、がんを排除しきれなくなり、がんの発生につながると考えられています。そこで、免疫を疲弊させないような方法が開発されれば、あるいは、簡単な検査でがんの予兆がわかるようになり、その段階ですぐにがん細胞を薬などで排除できるような方法が開発されれば、がんで亡くなる人がぐんと減る可能性はあると思います。こうした医療の開発は、夢物語ではなく、この調子で医療が進歩していけば、必ずしも不可能ではないと思っています。
情報格差をなくすことが、日本のがん医療の改善につながる
大久保さん
米国のがん患者さんから、「日本はがんという病気をタブー視している」と言われることが、しばしばあります。確かに、日本の社会では、がんというと腫れ物に触るような感じがあり、この根底にあるのは、「がん=死」というイメージだと思っています。このネガティブなイメージのせいで、がんと診断されたことがきっかけで会社を辞める人もいますし、社会復帰に苦労をする人も多くいます。この状況を打破するためには、がん医療は進歩し5年生存率もいまや70%近いのだということを、患者自身も社会もまずしっかり理解することが重要と考えています。
そのうえで患者さんが社会復帰するために最適な治療を、医師としっかり話し合えるような社会になっていけば良いと思っています。自分の人生にとって良い医療とは何なのかを、冷静に判断して選ぶことができる人たちが増えれば良いと願っています。
土井先生
がん医療の進歩を日本全国の方々に、理解し実感してもらうためには、医療の均てん化が重要になってくると思います。先ほどお話しした臨床試験の地域差に関しては、全国で臨床試験を行うためのDecentralized Clinical Trial:DCT(分散型臨床試験)という取り組みがすでに開始されています。
地域差にも一部関連するのですが、もう1つ解消すべき重要な課題が、情報格差です。治療を受ける際には、ご自身がその治療を正しく理解し、納得したうえで受けることが大切ですが、「理解できない」「納得できない」よりも、「知らない」ことは、より深刻です。正しい医療情報が必要な場所に確実に届く仕組みを確立することで、一人ひとりの情報格差がなくなれば、日本の医療はより良くなると思います。
大久保さん
それは、私が5yearsで挑戦していることの1つです。5yearsのようながん患者さんのコミュニティを介して同じ境遇の人たちが全国でつながることは、地域による情報格差の低減に貢献できると考えています。例えば、何も情報が得られない中で、これから始まるがん治療に対し、大きな不安と闘いながらひとり悶々としていた人が、5yearsに参加し、「同じ経験をした人が標準治療を受けて元気になった」という情報を知るだけでも、希望をもって前向きに治療に取り組めるようになりますし、これはその人にとって大きな意味を持ちます。
もっとも、「がんで死なない世の中」を目指し、一人ひとりの患者さんに向き合って日々診療を続けておられる、土井先生のような医療者が増えることが、より良いがん医療の進歩に大いに貢献すると感じました。本日は、ありがとうございました。
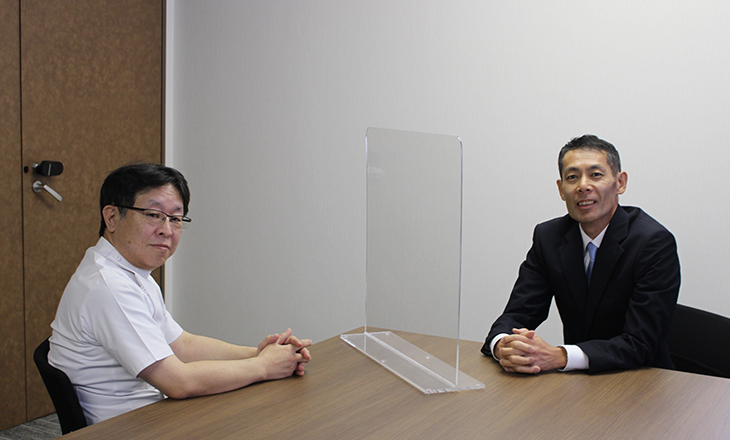
プロフィール
土井 俊彦(どい としひこ)
1994年 岡山大学大学院医学研究科第一内科卒業、国立病院四国がんセンター内科
2002年 国立がんセンター東病院内視鏡部
2004年 同院内視鏡部消化器内視鏡室医長/病棟部病棟医長
2009年 同院治験管理室室長併任
2012年 消化管内科長
2013年 早期・探索臨床研究センター先端医療科長/消化管内科長併任
2014年 副院長(研究担当)を兼務
2015年 先端医療科科長、先端医療開発センター新薬臨床開発分野長
プロフィール
大久保 淳一(おおくぼ じゅんいち)
0000年 名古屋大学大学院(工学)修了
1999年 シカゴ大学経営大学院MBA取得
1999年~2014年 ゴールドマン・サックス証券に在籍
2007年 精巣腫瘍のステージ3と診断
2008年 治療を経て復職
2015年 「5years」(https://5years.org/)を立ち上げ

