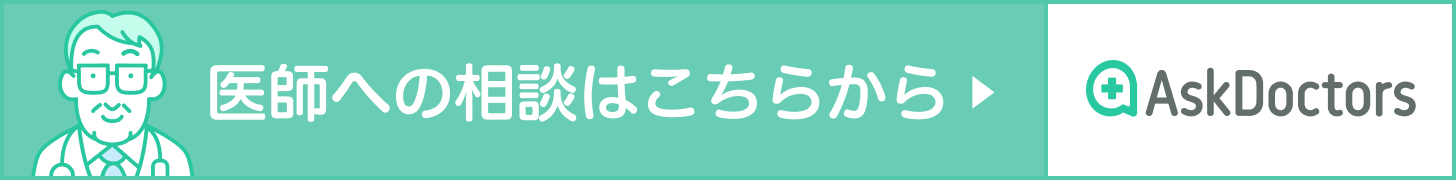相談:乳がんの手術、必要な範囲だけ切除したい
乳がんの手術を受けることになりましたが、手術前に最初の説明と異なる話をされました。1か月前の説明では、「しこりは1cm未満なので手術では3cm切除する。切除した組織を調べて悪性ではなかったということもあり得る。その場合には放射線治療は必要ない」とのことでした。昨日の説明では、「しこりは1cm未満。非浸潤がんで腋窩リンパへの転移はなし。リンパ節生検は必要なし。ただ、エコーやMRIでははっきりとしないので、3cm以上切除する。開けてみてがんの範囲が広ければいったん手術を中止し、再手術で乳房を全摘する」とのことでした。 1年半前から大きさは変わらず、マンモグラフィは異常なし、エコーでもMRIでもはっきりとわからない1cmのしこりのため、これまで4つの病院で診てもらいました。2番目の病院では針生検の病理検査で「良性だが悪性ではないとする理由が見つからない」とされ、しこりだけを取って悪性かどうかを見極める、悪性であれば追加の手術でしこりの周辺部分を切除するという2段階の手術の可能性を示唆されました。その他の病院では、「悪性」もしくは「悪性の可能性が高いが絶対に悪性ともいえない」という診断だったので、いずれにしてもしこりを取り除かなければならないと考えています。 悩んでいるのは、切除範囲についてです。ある病院では1cmのしこりとその周辺組織をあわせて2cm、他の病院では3cm、そして今の病院では3cm以上だが、もっと広範囲または全摘の可能性もあるとのことです。私の希望は2cm切除、術中迅速病理検査で断面にがん細胞が見つかったら3cmというように、本当に切除する必要がある部分のみを切除してもらいたいと思っています。同じ1cmのしこりなのに、切除範囲の大きさの違いに困っています。 2cm切除した組織を調べて悪性であると判断された場合に追加手術をすることになると、どのようなリスクが考えられますか。また、切除の対象となるしこりの周辺組織のマージンは、2つの病院で5mmといわれています。今の病院では1cmといわれているのですが、なぜ病院によってマージンの大きさについての考え方が違うのですか? 標準ではどのくらいとされていますか。エコーやMRIの画像にがんの広がりがはっきり映らないということはどういうことですか? 1cmのしこりのうち針生検で採取した組織は4mmのものが2本です。3つの病院でこの組織の病理検査結果が「早期の乳がん」または「悪性の可能性が高い」と診断されました。4mmの組織を2本取ることで、悪性の部分が取りきれるということは在り得るのですか? もし手術で切除した組織が「悪性ではなかった」ということであった場合も放射線治療は必要なのでしょうか。(本人、女性)
回答:切除した断端が陽性では、陰性に比べ有意に局所再発率が高まる
乳癌診療ガイドラインによると、乳房温存手術において切除断端陽性と診断された場合に、外科的切除が弱く推奨されています。乳房温存手術や手術標本の取り扱い、病理診断には各国、地域、病院や治療医ごとに違いがあり、乳房温存手術後の断端診断の基準を完全に統一することは難しく、断端陽性には多様な病態が混在しています。...
乳房温存手術後に断端陽性と診断されたとき、追加の外科的治療が必要か、放射線療法のみで十分であるのかを明らかにした前向きのランダム化比較試験は、現時点では存在しません。(※回答当時の情報です。)局所再発リスクは、断端陽性の場合、断端陰性の2倍です。断端陰性のマージン幅(>0 mm、1 mm、2 mm、5 mm)による、局所再発率を検討した報告によると、マージン幅が広くなるにつれて小さくなる傾向はありましたが、ばらつきが大きく有意な差は認められていません。断端陰性と診断するためのより広いマージン幅は、狭いマージン幅と比べて長期的には利益になっていないようです。断端陽性は陰性に比べて有意に局所再発率が高まるという結論は、対象となっている33の研究で結果に一貫性があります。
外科的追加切除のメリットは、局所再発リスクを低減し温存乳房内の局所再発を減らすことで、乳がんによる死亡リスクを減少させることです。外科的追加切除を行うことによる整容性の低下、再度の外科治療に伴う入院・治療費用の増加がデメリットです。
非浸潤性乳管がんに対する乳房温存療法のガイドラインでは、2mm以上のマージンを至適マージンとして、全乳房照射をすることで、局所再発率を低く抑え、再手術率を低下するとあります。ただし、断片の定義を2mmとする明確な医学的根拠はありません。
検査はもちろん治療に関しても、100%ということはありません。がんの腫瘍(しこり)といっても、ピンポン玉のように、きれいな球体をしているわけではなく、また細胞のがん化の状態も一定のものではありません。画像診断は、あくまでも体の外からみたものですので、明らかに腫瘍と思われる個所、腫瘍かもしれない箇所、腫瘍ではないと思われる個所など境界線がはっきりとしているわけではありません。
エコー検査は、小さなしこりも発見できるのが特徴ですが、乳腺線維腺腫や乳管内乳頭腫など、がんではない良性のしこりも画像に映ってしまいます。乳房に対する造影MRI検査は、乳がんを高い感度で判定できます。その一方で特異度は感度ほど高くなく、術前の造影乳房MRIで指摘された病変の擬陽性率(がんではなかった)が比較的高いとされています。造影乳房MRI検査が、乳がんの術前の治療方針決定に有用かどうかについて、広がり診断の正確さ以外に局所再発率やMRI検出病変の偽陽性率なども踏まえて評価するとしています。ここでいう感度とは、悪性腫瘍である確率のことで、特異度は、悪性腫瘍ではない確率ということです。
画像誘導下針生検での感度の平均は97%以上,特異度は92~99%です。また、画像誘導下針生検は外科的生検よりリスクが少なく、有害事象の発生率も低い、重度の合併症の発生はすべての手技の1%未満という報告があります。画像誘導下針生検では、感度と特異度が外科的生検に近似するため、画像誘導下針生検を行うことで外科的手技回数は減少し、有害事象も少なく済むということが示唆されています。
乳房温存手術後の術後放射線治療では、局所再発率が約半分に減少するという報告があります。また、腫瘍径が2.5cm以下で悪性度が低グレードから中間グレードの非浸潤性乳管がんで、断面距離が3mm以上の場合、術後放射線治療を行った場合の局所再発率が0.9%なのに対し、術後放射線治療を行わなかった場合は6.7%という報告があります。いずれも局所再発率は低く、病勢進行や死亡リスクなどに有意差は認められていません。術後放射線治療を省略できる可能性はありますが、今後の臨床試験の結果次第です。上記は、悪性腫瘍だった場合の標準治療ですので、良性(がんではない病変)に対しては、術後放射線治療は行われないはずです。
参考文献
浸潤性乳管がん/非浸潤性乳管がんに対する乳房温存手術において、断端陽性と診断された場合に外科的切除は勧められるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/gekaryoho/cq-2/
乳がん術前の治療方針決定に造影乳房MRIは有用か?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/kenshingazo/cq6/
乳がん確定診断において、画像誘導下生検手技は外科的生検よりも推奨されるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/kenshingazo/bq1/
非浸潤性乳管がんに対して乳房温存療法は勧められるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/gekaryoho/bq-1/
外科的追加切除のメリットは、局所再発リスクを低減し温存乳房内の局所再発を減らすことで、乳がんによる死亡リスクを減少させることです。外科的追加切除を行うことによる整容性の低下、再度の外科治療に伴う入院・治療費用の増加がデメリットです。
非浸潤性乳管がんに対する乳房温存療法のガイドラインでは、2mm以上のマージンを至適マージンとして、全乳房照射をすることで、局所再発率を低く抑え、再手術率を低下するとあります。ただし、断片の定義を2mmとする明確な医学的根拠はありません。
検査はもちろん治療に関しても、100%ということはありません。がんの腫瘍(しこり)といっても、ピンポン玉のように、きれいな球体をしているわけではなく、また細胞のがん化の状態も一定のものではありません。画像診断は、あくまでも体の外からみたものですので、明らかに腫瘍と思われる個所、腫瘍かもしれない箇所、腫瘍ではないと思われる個所など境界線がはっきりとしているわけではありません。
エコー検査は、小さなしこりも発見できるのが特徴ですが、乳腺線維腺腫や乳管内乳頭腫など、がんではない良性のしこりも画像に映ってしまいます。乳房に対する造影MRI検査は、乳がんを高い感度で判定できます。その一方で特異度は感度ほど高くなく、術前の造影乳房MRIで指摘された病変の擬陽性率(がんではなかった)が比較的高いとされています。造影乳房MRI検査が、乳がんの術前の治療方針決定に有用かどうかについて、広がり診断の正確さ以外に局所再発率やMRI検出病変の偽陽性率なども踏まえて評価するとしています。ここでいう感度とは、悪性腫瘍である確率のことで、特異度は、悪性腫瘍ではない確率ということです。
画像誘導下針生検での感度の平均は97%以上,特異度は92~99%です。また、画像誘導下針生検は外科的生検よりリスクが少なく、有害事象の発生率も低い、重度の合併症の発生はすべての手技の1%未満という報告があります。画像誘導下針生検では、感度と特異度が外科的生検に近似するため、画像誘導下針生検を行うことで外科的手技回数は減少し、有害事象も少なく済むということが示唆されています。
乳房温存手術後の術後放射線治療では、局所再発率が約半分に減少するという報告があります。また、腫瘍径が2.5cm以下で悪性度が低グレードから中間グレードの非浸潤性乳管がんで、断面距離が3mm以上の場合、術後放射線治療を行った場合の局所再発率が0.9%なのに対し、術後放射線治療を行わなかった場合は6.7%という報告があります。いずれも局所再発率は低く、病勢進行や死亡リスクなどに有意差は認められていません。術後放射線治療を省略できる可能性はありますが、今後の臨床試験の結果次第です。上記は、悪性腫瘍だった場合の標準治療ですので、良性(がんではない病変)に対しては、術後放射線治療は行われないはずです。
参考文献
浸潤性乳管がん/非浸潤性乳管がんに対する乳房温存手術において、断端陽性と診断された場合に外科的切除は勧められるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/gekaryoho/cq-2/
乳がん術前の治療方針決定に造影乳房MRIは有用か?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/kenshingazo/cq6/
乳がん確定診断において、画像誘導下生検手技は外科的生検よりも推奨されるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/kenshingazo/bq1/
非浸潤性乳管がんに対して乳房温存療法は勧められるか?
http://jbcs.gr.jp/guidline/2018/index/gekaryoho/bq-1/
医師に相談したい場合、現役医師が回答する「AskDoctors(アスクドクターズ )」の利用もおすすめです。