「三つも重なるなんて偶然とは思えない。もはや必然」江川裕人先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年12月25日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肝臓がん」より許諾を得て転載しています。
肝臓がんの治療に関する最新情報は、「肝臓がんを知る」をご参照ください。
移植を考える家族のドラマに背は向けない。なぜなら私は、患者さんとドナーの方と、2人分の人生を背負っているからです。

生体肝移植がほかの医療と大きく違うところは、”人の命の贈り物”があってはじめて成り立つところ。江川裕人先生が、この難しい医療に生涯をかけ、肝臓移植医として生きることは、いわば神様のおぼしめしだったのかもしれません。
京都大学医学部を卒業した翌年、江川先生は四国の小さな病院で医師としてのスタートを切ります。その病院で出会ったのが、当時部長だった伊槻敏信(いつきとしのぶ)先生。伊槻先生は江川先生に、「これからは肝移植の時代だ」と熱く語ったといいます。伊槻先生は、その5年後に白血病で他界。江川先生が肝臓移植医を目指して努力していることを、誰よりも喜んでいた一人でした。
その後、大阪の病院に勤務していたころに出会った肝硬変の患者さんは、「仕事を引退したら、それまでためた2万冊の蔵書を読むのが楽しみ」と話していたそうです。しかし、患者さんは間もなく、肝硬変が原因の食道静脈瘤(りゅう)で亡くなってしまいます。「移植さえできれば助かったのに、と思うと……」
この2人との出会いを通じて肝臓移植に強い興味を抱き、母校の京大病院に戻った江川医師を迎えたのは、日本における生体肝移植医療の先駆者、小澤和惠(おざわかずえ)先生の研究室でした。「伊槻先生と患者さんと、小澤先生と。三つも重なるなんて偶然とは思えない。もはや必然です」
1992年、アメリカの移植センターへ留学、3年後帰国した江川先生は、京大病院で腕をふるい、移植症例1,300例という圧倒的な経験を携え、昨年からは東京女子医科大学の消化器外科で肝臓移植の陣頭指揮をとっています。
先日、伊槻先生の墓前にも近況を報告したという江川先生。移植した肝臓がレシピエントの中で体の一部として生きて機能しはじめることを”生着”といいますが、「この病院に肝臓移植の最新技術を生着させることを、先生に誓ってきました」
生体肝移植では、患者さん、臓器提供をするドナー、その家族、親族に、さまざまなドラマがあります。手術だけに徹する医師もいますが、江川先生は努めてそうしたドラマに背を向けず、よく話を聞くようにしています。
そのとき、いいことも、悪いことも含め必要な情報をすべて提供し、心理的な問題は精神科医を交えて検討する。その結果、身体的な肝臓移植の条件はすべてそろっていても「肝移植をしない」という選択肢をとることも。「移植はできても、家庭が不和に陥る。それでは移植をした意味がなくなってしまう。病気の回復だけでなく、命の贈り物をするドナーの方も、贈られるレシピエントの方も幸せな人生になってこそ、移植医療の価値があると思うのです」
今、江川先生が憂慮していることの一つは、肝臓がんの患者さんに対して移植医療の情報不足があること。日本の移植技術は非常に高いのに、そのために患者さんがその恩恵を受けられないことだといいます。
「もちろん、すべての患者さんに移植が適しているわけではありませんが、そういう道があることさえ知らされていない。患者さんにとっては不利益で、とても残念です」
江川先生自身も、まさにそうした経験があります。その患者さんは、ほかの大きな病院にかかっていたにもかかわらず、肝移植という方法があることを知らされていませんでした。たまたま友人が江川先生の存在を知り、連絡をとったことで、移植につながったといいます。
「いくつも問題を乗り越えて時間をかけてみなが納得し、そのうえで行われる医療です。肝臓病の人は、万が一のことも考えて、一度、肝臓移植の専門医に相談してほしい。移植する必要がなければラッキーですし、必要があれば、そこからじっくりと家族で話し合う。検討を始めるのは早いほうがいいんです」
江川裕人(えがわ・ひろと)先生
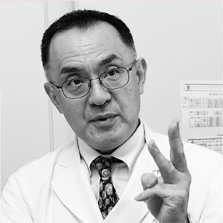
東京女子医科大学 消化器外科学教室教授
1957年鳥取県生まれ。82年京都大学医学部卒業。香川県坂出回生病院などで外科研修を経て、京都大学大学院で研究後、92~94年までカリフォルニアパシフィックメディカルセンター移植外科留学。2002年、京都大学大学院医学研究科移植免疫医学講座准教授。09年、朝日大学歯学部附属村上記念病院外科教授。11年より現職。日本外科学会指導医、日本消化器外科学会指導医、肝胆膵外科高度技術指導医、肝臓専門医、日本がん治療認定機構認定医ほか。

