肝臓がんの「肝動脈化学塞栓療法」治療の進め方は?治療後の経過は?

- 荒井保明(あらい・やすあき)先生
- 国立がん研究センター中央病院院長 放射線診断科長
1952年東京生まれ。79年東京慈恵会医科大学医学部卒。国立東京第二病院内科研修医、レジデントを経て84年より愛知県がんセンター勤務。97年同放射線診断部長。2004年、国立がんセンター中央病院放射線診断部長に就任。同病院副院長などを経て、現職に至る。
本記事は、株式会社法研が2012年12月25日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肝臓がん」より許諾を得て転載しています。
肝臓がんの治療に関する最新情報は、「肝臓がんを知る」をご参照ください。
がんを抗がん薬でたたき兵糧攻めにする
がんに栄養を送る血管に抗がん薬と血管をふさぐ物質を入れ、血流を止める治療法です。
肝切除やラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法では治療の難しい進行がんに選択されます。
血液をたくさん必要とする肝臓がんならではの治療法
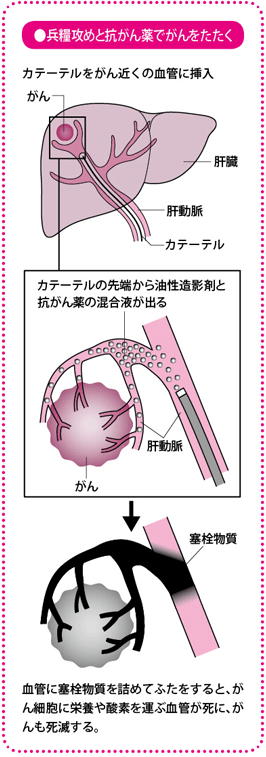
肝動脈化学塞栓療法(TACE:transcatheter arterial chemoembo-lization)とは、がんに栄養を送る血管に抗がん薬とゼラチン粒状の物質を入れ、抗がん薬でがんを攻撃し、同時に血流を詰まらせることによって、がんを死滅させる治療です。
栄養路を遮断する兵糧攻めと、抗がん薬の二重の効果で、より高い腫瘍壊死(しゅようえし)効果を狙います。
また、抗がん薬のほとんどががんやその周囲の血管にとどまり、がんに的を絞って作用するので、薬を全身に使う化学療法のような副作用が少なく、少ない量でも効果が得られます。
肝臓がんの成長には、ほかの部位のがんよりも、多くの血液を必要とするため、血流が豊富になっています。だからこそ、がんに栄養を運ぶ血流を遮断する兵糧攻めが効果的なのです。
「肝切除」、「ラジオ波焼灼療法」と並ぶ、肝臓がんの三大治療の一つが、この肝動脈化学塞栓療法です。
当センターでは、年間約500件の肝動脈化学塞栓療法を行っています。1日に何件も行うほど治療数が多いのが当センターの特徴といえるでしょう。それを可能にするのは、充実したスタッフです。肝動脈化学塞栓療法を含めた血管内治療を行う放射線科医は9人おり、そのうち6人がこの種の治療の専門医です。
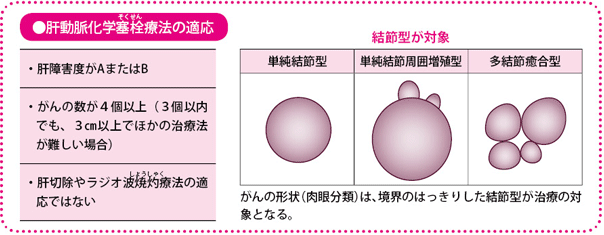
肝動脈を詰めるだけの治療から抗がん薬との併用療法へ
この治療の前身に当たる「がんに対する血管からの局所治療」が始まったのは、今から50年ほど前です。肝臓がんに対して動脈を遮断してがんを死滅させる治療法が試みられるようになったのは約35年前で、当時和歌山県立医科大学にいた山田龍作(りゅうさく)先生(現・大阪河崎(かわさき)リハビリテーション大学学長)が開発、普及させました。
当初は抗がん薬を用いず塞栓物質だけを詰める肝動脈塞栓療法も行われていました。その後、抗がん薬を併用したほうがより効果的であることが、経験的にわかってきたので、今は抗がん薬と塞栓物質を併用する肝動脈化学塞栓療法が一般的になっています。
いわば経験的に行われていた肝動脈化学塞栓療法の効果が科学的に検証されたのはおよそ10年前です。2002年に発表されたスペインでの臨床試験の結果では、2年生存率が63%でした。また、日韓共同で行った臨床試験(2012年に発表)では、2年生存率が75%でした。これらの結果を通じ、日本で生まれた肝動脈化学塞栓療法は、世界中の肝臓の専門医が認める標準治療となっています。
しかし、抗がん薬を用いない肝動脈塞栓療法だけでは効果が弱いとする明確なエビデンスはなく、抗がん薬との併用がよいかどうかは未だ議論が分かれるところです。私自身は、患者さんに苦痛を伴うなどの不利益がなければ、そして、塞栓と抗がん作用の合わせ技をすることで、より高い効果が得られるなら、そのほうがよいと思っています。
肝切除ができず、ラジオ波焼灼療法も難しい人が対象
肝動脈化学塞栓療法ができる条件は、日本肝癌(がん)研究会編集の『肝癌診療ガイドライン(2009年版)』によると、肝障害度がAかB、がんの数が3個以内であれば3cmを超えたもの、あるいはがんの数が4個以上のもの、となっています。位置づけとしては、肝切除ができずラジオ波焼灼療法では効果を得るのが難しい患者さんが対象になります。
体力があれば年齢にかかわらず治療が可能です。一方、若くても体力が極端に落ちている人や、重い持病がある人は、治療ができない場合があります。
道具の工夫や手技の向上で狙った血管に確実に注入する
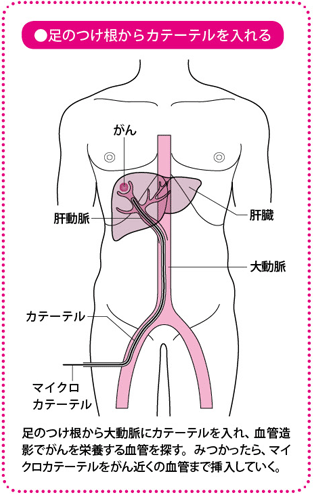
肝動脈化学塞栓療法は、肝動脈に抗がん薬と血管をふさぐ物質を入れる治療です。実際には、足のつけ根(または腕)の動脈を穿刺(せんし)して細く軟らかいカテーテルという管を入れて、がんに栄養を与えている肝動脈まで届かせます。そこに抗がん薬と造影剤を混ぜた液(エマルジョン)を注入し、そののち、塞栓物質を入れて血管をふさぎます。
こうして栄養路を絶たれてしまったがん細胞はいずれ死んで、免疫細胞に食べられます。治療後数週間の画像で見ると、がんが少しずつ小さくなっていくのがわかります。
最近ではマイクロバルーンという道具を併用した治療も行われています。その名のとおり、マイクロカテーテルの先につけて血管内でふくらませて使います。エマルジョンが入りにくかったり、入れてもあふれてしまったりするようなときに、手前でバルーンをふくらませて血流を止めておくと、エマルジョンが入りやすくなるのです。
目的は予後をのばすこと くり返しできる点がメリット
この治療の目的は、「予後をのばすこと」にあります。肝動脈化学塞栓療法をすると確かにがんは小さくなります。そのまま画像からは消えてしまうこともありますが、また大きくなっていくがんもあり、再治療が必要となります。
幸い、この治療は傷口が小さく、局所麻酔で済むので、くり返し治療を受けることができます。私が経験したなかでは、18回もこの治療を受けた患者さんがいます。
ただ、血管に入れた薬剤の影響で肝臓の正常な細胞や血管が傷むことがあり、回数が増えるほどそのリスクは高くなります。肝臓全体へのダメージを考えると、治療と治療との間は3カ月くらいあけたほうが望ましいとされています。それより期間が短くなるようであれば、患者さんの意見を聞いたうえで、別の方法を試すということも含め、治療方針を考えることが必要です。
| ●この治療のメリット・デメリット | ||
|---|---|---|
| メリット | 手術のできない進行がんに有効 | |
| 傷が小さく、くり返し治療できる | ||
| 高齢者でも治療できる | ||
| デメリット | がんの根治を得られるとは限らず、再発の可能性がある | |
| 血管が痛み、正常な肝細胞へのダメージがある | ||
できるだけがんのみを狙う周到な治療計画を立てる
肝動脈化学塞栓療法では、がんに栄養を送る血管を狙って、確実にそこをふさがなければなりません。血管の太さや位置は一人ひとり違いますから、CTやMRIなどで血管の位置を確認し、どこを塞栓すべきかを念入りに調べることが必要です。
ほかの多くのがんでは、周囲の正常な細胞に影響を与えることなく、がんに栄養を送る血管だけに的を絞って塞栓することは技術的にも難しいのですが、肝臓がんの場合、がん細胞は肝動脈から栄養をもらい、正常な肝細胞は門脈という別の血管から栄養をもらうという性質があります。そのため、がんに栄養を運ぶ動脈を塞栓しても正常な肝細胞が兵糧攻めに遭うことはなく、がんのみを攻撃することが可能です。
もちろん、より効果的に抗がん薬を効かせるためには、できるだけがんの近くの血管をふさぐ必要があり、十分な検査と治療計画を立てることが、効果を高めることにつながることはいうまでもありません。
治療の進め方は?
足のつけ根の大腿(だいたい)動脈から挿入したカテーテルを、血管の撮影で確認しながら肝動脈に進めます。がんのある血管に入ったら、エマルジョンと塞栓物質を注入します。
治療は血管撮影室で行い平均1時間で終了
この治療はCTやX線の撮影が必要になるので、当センターでは放射線診断科の血管撮影室という場所で行います。治療時間は塞栓する個数や場所にもよりますが、早ければ30分、難しいケースで1時間半、平均1時間です。
外来治療でも不可能ではありませんが、治療後の経過や合併症などを確認するため、基本的には入院して治療を受けてもらいます。
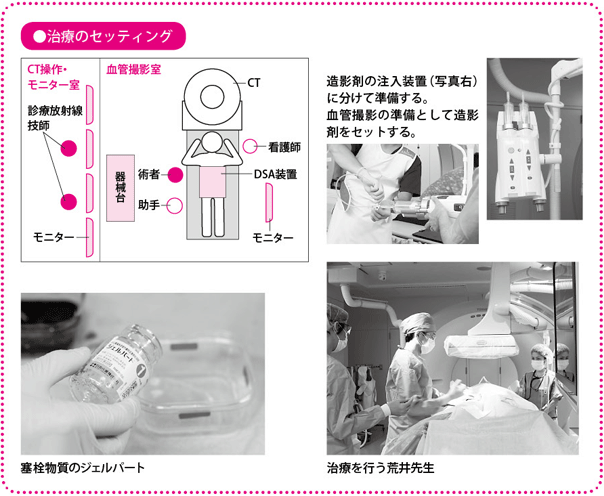
抗がん薬は油性の造影剤で包んで長く効かせる
肝動脈に入れる抗がん薬は、エピルビシン塩酸塩(以下エピルビシン:商品名ファルモルビシン、エピルビシン塩酸塩など)、マイトマイシンC(商品名マイトマイシン)、シスプラチン(商品名アイエーコールなど)、ドキソルビシン塩酸塩(商品名アドリアシンなど)などが使われています。当センターではエピルビシンを使うことが多く、次はシスプラチンとなります。シスプラチンのアイエーコールは、肝動注化学療法用の抗がん薬として用いられているものです。
エピルビシンは水溶性造影剤で溶解したものをヨード化ケシ油脂肪酸エステル(以下リピオドール:商品名リピオドール)という油と混ぜて使用します。この混合液を「エマルジョン」といいます。リピオドールは子宮卵管造影やリンパ管造影で使われている造影剤です。粘稠(ねんちゅう)性(粘り気があって密度がある)が高く、血管に入れるとその場にとどまりやすいという特性をもっているので、抗がん薬と混ぜればより長く、抗がん薬をがんの周囲にとどめて効果を持続させることができます。
塞栓物質は、球状のゼラチン粒の中心循環系血管内塞栓促進用補綴(ほてつ)材(以下ジェルパート:商品名ジェルパート)を使います。ジェルパートは2週間ぐらいで溶けて吸収されるので、何度も治療ができます。
粉状のエピルビシンをリピオドールと混ぜたり、必要に応じてジェルパートの大きさも調整して注入していきますが、これらを医師の手作業で行い、治療を進めていきます。
実際の治療の流れは以下のようになります。
まず、患者さんは鎮静作用のある薬(ジアゼパム:商品名ホリゾンなど)の点滴をした状態で、血管撮影室の治療用ベッドに横になってもらいます。痛み止めの薬(ペンタゾシン:商品名ペンタジンなど)を点滴します。
右足のつけ根を消毒し、局所麻酔をしたのちに、そこにある血管(大腿動脈)を穿刺し、X線で透視(必要に応じて造影剤を使って血管の状態を見ながら)しながらカテーテルを肝動脈に向かって進めていきます。この過程での痛みはほとんどありません。また傷も小さいので、治療後はほとんど目立ちません。
肝臓の入り口に到達したら、造影CTやDSA(コンピュータを使って血管だけを強調できる特殊な撮影装置)で撮影をして、肝動脈の全体像やがんの位置を確認し、そこからがんに栄養を送っている血管をみつけます。カテーテルの中にさらに細いマイクロカテーテルを入れて、再び透視をしながら目標の血管まで届かせます。
造影の画像を見ながら混ぜた薬剤を注入
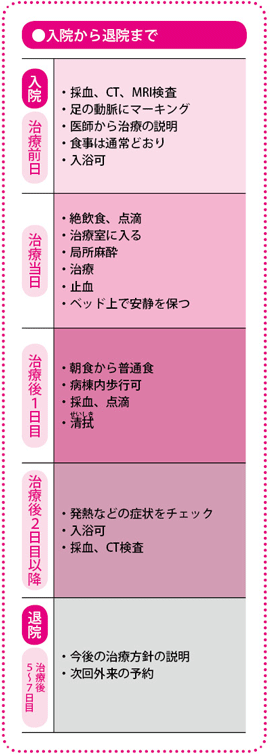
カテーテルを挿入したら、そこに入れる薬剤の用意をします。
エピルビシンとリピオドールは、二つの注射器をつないで中の薬を行き来させるパンピングという方法で混ぜ合わせます。この混ぜ合わせたエマルジョン(抗がん薬)をゆっくりと血管に注入し、がんにしっかり行き渡らせたあと、ジェルパートを入れ、がんに送られる血流を止めます。
塞栓が済んだら、CTで確認します。リピオドールは造影剤なので血管内に詰まっているかどうか、造影CTでわかります。このとき注意する点としては、がんは立体なので、正面はしっかり塞栓できていても、横から見たら塞栓できていない場合があることです。CTなどにより肝臓の360度からの画像を見て、しっかり塞栓できているかを確かめなければなりません。
その結果、十分に注入できていることが確認できたら、カテーテルを抜いて治療は終了となります。
治療後は圧迫して止血したあと、病棟に戻ります。出血予防のため、その日はベッドの上で安静にします。翌日からは普通に食事がとれますし、歩いてもらってもかまいません。がんが死滅すると、免疫反応がおこるため、38℃ぐらいの熱が出ますが、解熱薬などで対応します。
入院期間は1週間ほどですが、経過が順調であれば5日くらいで帰ることも可能です。
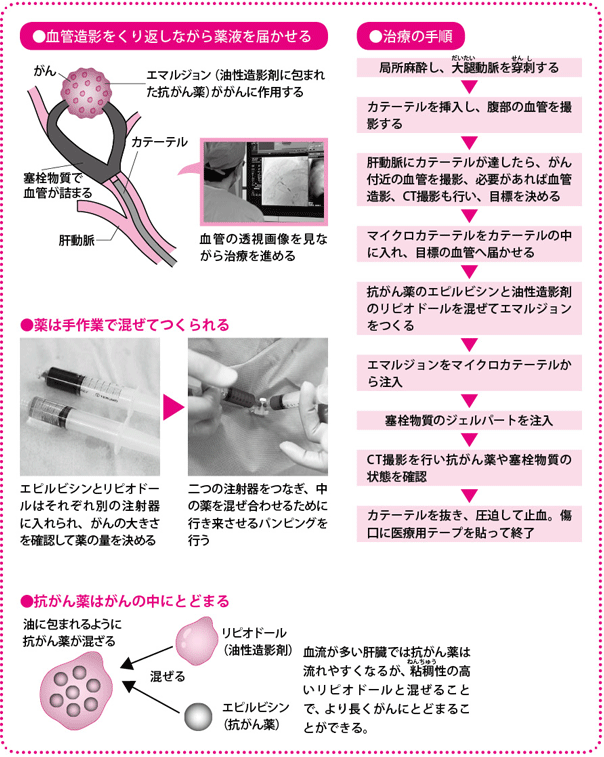
治療後の経過は?
1カ月後に受診し、CTで腫瘍の大きさを、血液検査で腫瘍マーカーを確認し、抗がん薬による副作用がある場合は、その治療を行います。
治療1カ月後に画像で効果判定をする
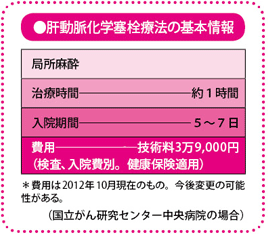
退院後は1カ月後にCTを撮り、がんの縮小効果を確認します。その後は、ほぼ3カ月に1度CTにより、効果が継続しているかをみます。がんが大きくなっていたら再治療を検討します。そのほか血液検査も行い、肝機能や腫瘍マーカーをチェックします。
術後の熱や痛みは心配な徴候ではない
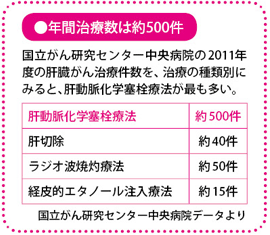
治療のあとは発熱、炎症、痛みといった症状が現れますが、心配はいりません。私たちは治療後のこうした症状を「塞栓後症候群」という、一種の好反応としてとらえています。というのも、これらはいずれもがんが死滅して免疫反応がおこっていることにより出る症状なので、治療がうまくいったときほど反応が強く現れることが少なくないからです。発熱は解熱薬で、痛みや炎症についても痛み止め(消炎鎮痛薬)やステロイド薬で抑えられます。
このほか、抗がん薬による副作用が出てくることもあります。エピルビシンであれば口内炎や脱毛がおこりますが程度は軽く、大量に髪が抜けたり、ものが食べられないほど口が荒れたりすることはほとんどありません。

