「自分にふさわしい薬を選ぶ主体性が大切」清水千佳子先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2011年11月25日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 乳がん」より許諾を得て転載しています。
乳がんの治療に関する最新情報は、「乳がんを知る」をご参照ください。
いろいろな女性の人生を追体験できるのが臨床の魅力。研究のヒントは患者さんからの贈り物です。

がんと診断されたとたん、人は「患者」になり、進行度、生存率、再発率、消失率、腫瘍径、投与量など、いろいろなものさしをあてがわられ、自分という存在、命そのものが、どんどん数字に置き換えられていくかのようです。「がんになっても、再発しても、その人らしくどう生きるか? それをサポートしていくのが私たち医療者の仕事であり、チームオンコロジー(患者さん中心のがんチーム医療)」と清水先生はいいます。手術をして、薬物治療、とくに副作用が強い化学療法を終えると、それまで落ち着いて考える暇もなく、走り続けてきた気持ちの張りがフーっと楽になり、逆に「これでいいのかって、いきなり不安に駆られ、何もしないことが怖くなってしまう」患者さんもいるそうです。「でも、くよくよ考えても再発するときはする、しないときはしない。どうせ同じ時間を過ごすのなら、少しでも前向きに過ごしてほしいです。病気になったことは変えられないし、再発の可能性はゼロにはできませんから」。決して、突き放すわけではなく、”その人らしさ”を失ってほしくない、というのが、清水先生の思い。がんばれ、とは決していわない、ただ、あなたらしければそれでいい、という患者さんへのエール。気持ちを表に出す人、自分のなかにしまい込む人。がんであること、がんとともに生きること、それぞれに納得のしかた、受け止め方があるのでしょう。
「時間が解決してくれるところも実際は大きいです。きっかけも人によって違う。くよくよしているのに飽きちゃいました」と、あるとき、ふっきれたように元気になる人も。
乳がんの治療は、薬物療法一つとっても多岐にわたります。化学療法薬、ホルモン療法薬、分子標的薬。それぞれに新しい薬も加わってきており、患者さんが理解しなければならない情報は山のよう。一方で、薬だから「副作用があるのは当たり前」といった乱暴な物言いも耳にします。
「事前に対応のしかたを知っておけば副作用を防いだり、軽くすませたりすることもできます。楽に過ごせるに越したことはありません。納得できないまま、苦痛を我慢してイヤイヤ進めるのでは効くものも効かなくなってしまいそう」。治療の中心は常に自分、治療を「受ける」というより、治療に「参加する」。難しいことかもしれませんが、副作用も含めて「自分にふさわしい薬を選ぶ主体性が大切です」。
「患者さんからリサーチクエスチョンをもらい、それに沿った研究を進めたい」という清水先生の最近のテーマはサバイバーシップ(がんとともに生きる姿勢)。とくに若い患者さんの妊よう性(妊娠する力)、外見(コスメティック対策)とQOL、遺伝性乳がんの場合のカウンセリングや情報提供などを主に取り組んでいます。たとえば40歳前後という微妙な年齢で発病し、出産希望がある場合には「いっぺんに、ものすごくたくさんのことを考えなくてはならなくなる。なかには子どもを産めなくなるのだったらがんなんてどうでもいい」と考える人も。冷静に客観的に「患者さん自身が理解したうえで、自分で問題に優先順位をつけられる」には、どんな情報を、どんなふうに伝えればよいのか、いまはまだ「患者さんの知りたいことを掘りおこす段階」だといいます。そのためには、医療者側のコミュニケーションの能力が問われるとも。「患者さん自身が見えていないところ、そういうところを引き出す医療者、医療チームを作りたい」という清水先生からひとこと。「自分のなかだけにしまっているような問題があったら、ぜひ、周りのスタッフに声をかけてみて。一緒に考えれば、解決のヒントがみつかるはずです」。
清水千佳子(しみず・ちかこ)先生
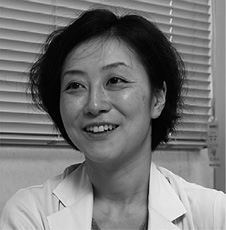
国立がん研究センター中央病院 乳腺科・腫瘍内科医師
1971年東京都生まれ。1996年東京医科歯科大学医学部卒業。国立がんセンター中央病院レジデント、がん専門修練医を経て2003年7月より国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科医員。専門は乳がんの薬物療法。2003年のM.D. Anderson Cancer Center Medical Exchange Programへの参加ががんの「チーム医療」を考えるきっかけに。乳がん患者のサバイバーシップの包括的な支援を目指す。

