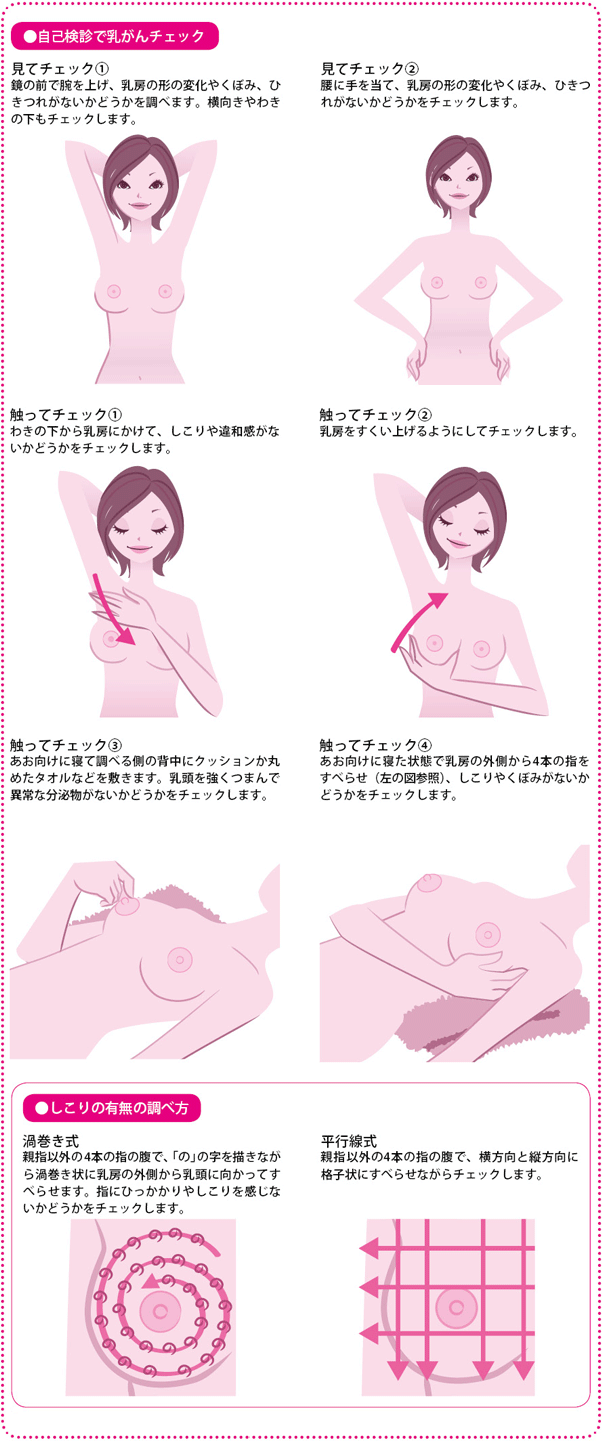乳がんの「検査」と「診断」画像診断・生検・病理検査って?

- 中村清吾(なかむら・せいご)先生
- 昭和大学医学部乳腺外科教授・昭和大学病院ブレストセンター長
1982年千葉大学医学部卒業。同年より、聖路加国際病院外科にて研修。1993年2月から、同病院情報システム室室長兼任。1997年M.D.アンダーソンがんセンターほかにて研修。2003年5月より、聖路加国際病院外科管理医長。2005年6月より同ブレストセンター長、乳腺外科部長。2010年6月より、現職。
本記事は、株式会社法研が2011年11月25日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 乳がん」より許諾を得て転載しています。
乳がんの治療に関する最新情報は、「乳がんを知る」をご参照ください。
画像診断、生検、病理検査等で乳がんをとらえ治療方針を確定
早期発見のために月に1回は乳房の自己チェック
乳がんは検診で早期発見が可能ながんの一つで、自分でみつけることができる数少ないがんでもあります。自分でみつけるために行う自己チェックの方法は、検査と診断(昭和大学医学部・昭和大学病院ブレストセンター中村清吾先生) 2/3ページの下にある「自己検診で乳がんチェック」の図を参考にしてください。自分の乳房の状態をよく知る意味でも、毎月1回の自己チェックを欠かさないのが理想です。20歳を過ぎたら毎月、月経後数日以内に自己チェックを行うとよいでしょう。
乳がんは、1~2cmほどの大きさになると注意深く触ればわかります(乳房の奥深くにあるとわからないこともあります)。そのため、日ごろから乳房のチェックをし慣れていると、がんによる皮膚の引きつれやくぼみなどに気づきやすくなり、小さいしこり(がん)の段階で発見することができます。
乳がん検診で疑いをもつ
乳がんリスクが高まる30歳前後から定期的な乳がん検診を行うことで、乳房の奥に隠れたしこりを早期発見することが可能です。
35歳以上は年に1回乳がん検診を受ける
日本では、40歳以上の女性を対象に、2年に1回の乳がん検診の受診が勧められています。
しかし、乳がん患者が増えはじめるのは30歳くらいからで、しかも若くして発症する乳がんのほうが、進行が速い場合が多いといわれています。乳がんのリスクファクターに当てはまる人は、できれば35歳くらいから毎年、乳がん検診を受けたほうがよいでしょう。自己チェックではみつけられない小さなしこりがみつかることもあります。
がんの検査には大きく、がんをみつけるがん検診、がんを確定する検査、がんの性質を調べる検査、再発や転移を調べる検査があります。
現在、乳がんをみつける検診として有効性が認められているのは、専門医が乳房を見たり触ったりして、しこりや皮膚の異常などを確認する視触診と、乳房専用のマンモグラフィ検査を併用する方法です。
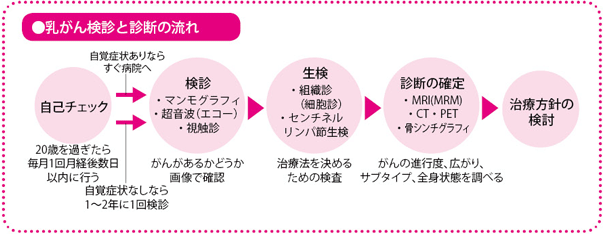
マンモグラフィ検査が基本場合によっては超音波検査
マンモグラフィは、2枚の透明な板(圧迫板)で乳房をはさんで薄くして、乳腺(にゅうせん)のようすを撮影する検査です。わきの下のリンパ節(腋窩(えきか)リンパ節)も確認するので、わきの下の肉も一緒に板にはさみます。
この検査では、しこりだけでなく、しこりになる前の石灰化した病変までみつけることができます。石灰化した病変は非浸潤がんであることが多いので、マンモグラフィは早期発見には欠かせない検査といえます。
その一方で、マンモグラフィの画像では白く写った部分ががんですが、乳腺症など良性の乳房の病気でも乳腺が白く写るので、これだけでがんを確定することはできません。とくに若くて比較的乳房が小さく、乳腺が密集している人は、検査画像が全体的に白っぽくなり、がんを見分けるのが難しいといった面があります。X線を使うので、妊娠中の女性にも使えません。
40歳くらいまでの女性や妊娠中の女性に勧められるのが、超音波(エコー)検査です。人の耳では聞こえないほど高い周波数の音(超音波)を乳房に当ててその反射した波のようすをチェックする検査です。石灰化した病変は写りませんが、数mm程度の小さなしこりをみつけることができます。
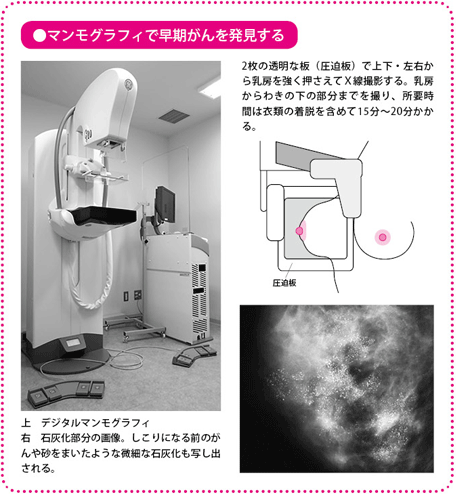
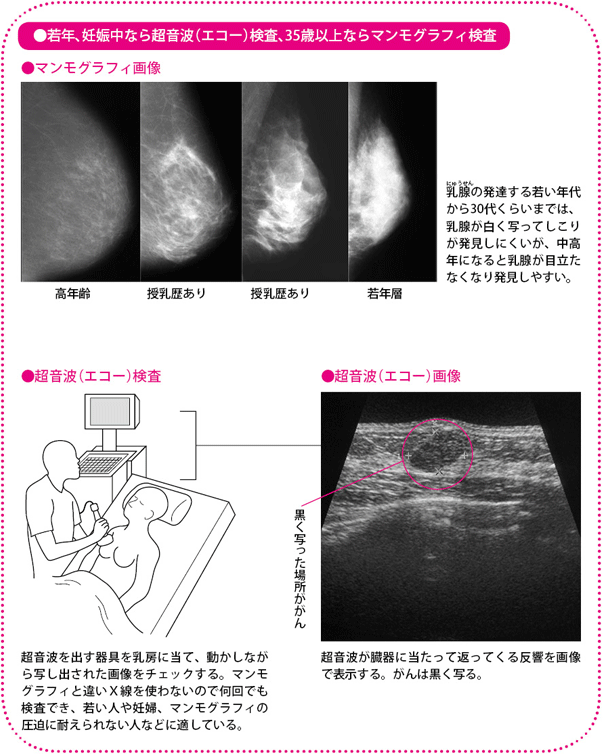
生検で診断を確定
がんのある病変組織を採取して調べる生検には、細い注射針で行う穿刺吸引細胞診と、やや太い専用針で組織を吸引する組織診があります。
細胞や組織を採取し顕微鏡でがんの有無を確認
がん検診などで疑わしいしこりや石灰化がみつかったら、次に、その部分の細胞や組織を採取して、顕微鏡でがん細胞があるかどうかを確かめる細胞診や組織診を行います。
細胞診は、超音波でしこりの位置を確認しながら、細い針をつけた注射器を用い、がんの疑いがある場所に刺して、細胞を吸引して採取し、がん細胞であるかどうかを調べます(穿刺(せんし)吸引細胞診)。針を刺すので痛みが少しあります。
細胞診でがん細胞がみつかったり、悪性の可能性が高いとわかったりすることもありますが、いずれの場合も、組織診は必ず行います。細胞診では、採取できる細胞の量はとても少ないので、がんの性質やホルモン受容体、HER2などを調べることができません。治療の方針を立てるために重要な情報を得るには、組織診は欠かせない検査です。
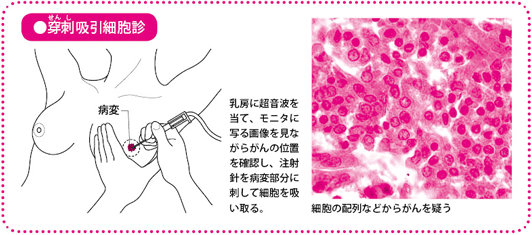
針生検でがんを確定同時にがんの性質も調べる
組織診は、針生検とも呼ばれます。以前は、皮膚を切開してしこりを一部取り出す「摘出生検(外科生検)」がよく行われていました。しかし、細胞診で使う針より太目の針を用いる「針生検」でも診断の精度が変わらないことがわかっており、患者さんへの負担が小さい針生検の方法をとることがほとんどです。
針生検は、針の太さや採取方法の違いなどで、いくつかの種類がありますが、多くの医療施設で実施しているのが「マンモトーム生検(吸引式針生検)」です。
マンモトーム生検は、マンモグラフィや超音波で、しこりや石灰化した病変の位置を確認しながら直径3mmぐらいの特殊な針を刺し、側面にある吸引口でその部分の組織を採取するものです。切らないとはいえ、太めの針を刺すことから痛みがあるので、局所麻酔をするのが一般的です。
検査にかかる時間は30分~1時間程度です。傷口は4mmぐらいになりますが、縫う必要はなく、1カ月ぐらいで目立たなくなります。
組織診では、用いる針が細胞診より太い分、1回の検査でたくさん細胞が採取できるので、がんかどうかを調べることはもちろん、がんの性質(サブタイプ分類)も確認することができます。通常は、この組織診によって、がんかどうかを確定します。
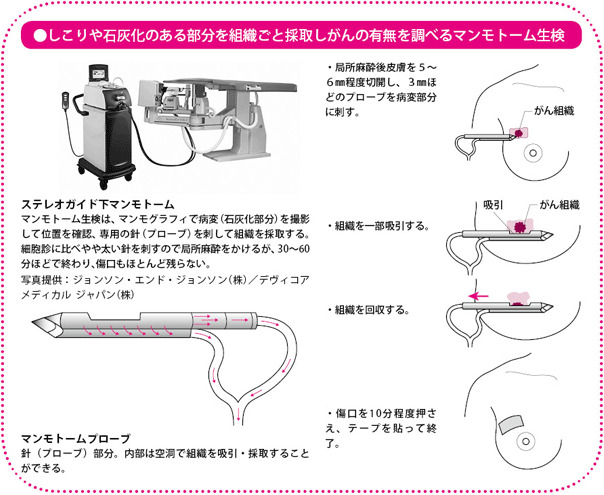
がんの広がりと悪性度を判定
生検で乳がんとわかったら、さらに精密検査を行ってしこりの位置や大きさ、悪性度を確認し、術前薬物療法を行うかどうかを検討し手術の方法を決めます。
がんの広がりを確認するMRI(MRM)とCT

乳がんと確定されただけでは、治療方針をまだ決めることはできません。乳がんでは、がんがどこまで広がっているのか、リンパ節への転移はあるのかといった病期だけでなく、ホルモン受容体やHER2の状態などのサブタイプ分類も考慮されます。
がんがどこまで広がっているのか、あるいは乳房以外への転移はないかを調べるのが、MRI(核磁気共鳴画像)検査やCT(コンピュータ断層撮影)検査です。
・MRI検査(造影MRI)

がんの広がりを調べるためには、MRIに写りやすいガドリニウムという造影剤を血管内に注射して行う「造影MRI」が有用です。MRマンモグラフィという意味で、MRMということもあります。がんは成長のために栄養を得ようと、血管(新生血管)をつくり始めますが、造影剤を入れるとその新生血管も写るので、がんの広がりぐあいが確認できるのです。
薬物療法の前後でがんの状態を確認したり、乳房部分切除術では、切除する範囲を正確に決めたりします。
手術の際にがんの取り残しがないようにするためにも、造影MRIが重要です。
・CT検査(ヘリカルCT)
CTは、人体を輪切りに細かくX線撮影する検査で、最近ではらせん状に回転しながら撮影するヘリカルCTも使われています。三次元の画像を得ることができ、検診などではみつけにくかった小さながんもみつけることもできます。
X線に反応しやすいヨード造影剤を用いてCT検査をする「造影CT」では、造影MRIと同様、がんの広がりを確認することができます。
なお、造影MRIや造影CTは、術前薬物療法の効果を判定したり、手術後の再発や転移を確認したりするために実施されることもあります。
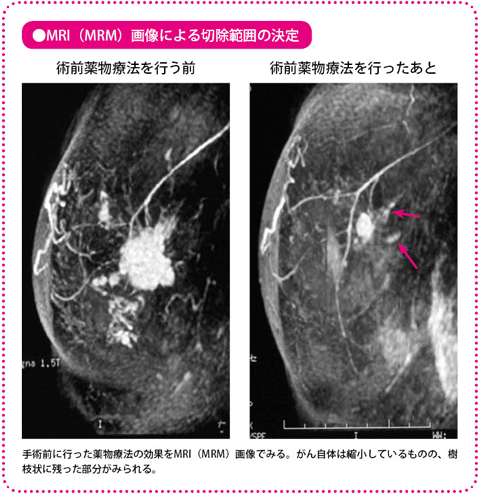
患者さんに優しい新しいがんの検査方法も登場
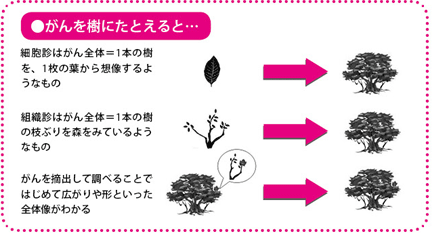
乳がんではほかにも、さまざまな新しい検査法が試みられています。
たとえば「造影マンモグラフィ」は、CTと同じヨード造影剤を使って、マンモグラフィを行う方法です。マンモグラフィの見落としやMRIにおこりやすい偽陽性(実際はがんがないのに、がんがあるようにみえる状態。不要な治療をするおそれがある)を減らすことができると期待されています。
もう一つ、PET検査で使われるFDGという造影剤を使って、マンモグラフィのように乳房をはさんでその状態を撮影する方法「PEM(陽電子乳房撮影)」もあります。小さながんもみつけやすいと、注目されています。
このほかにも、MRIでがんの位置を確認しながら組織診を行う「MRIガイド下生検」や、通常のMRIでがんが疑われたときに、再度、超音波検査を行う「セカンドルック・エコー」なども始まっています。
ただ、こうした新しい検査については、健康保険で認められていないものもあり、費用が高くつくこともあります。また、本当にこの検査が必要かどうか、検証中のものもあります。
PET検査や骨シンチグラフィで転移を確認する
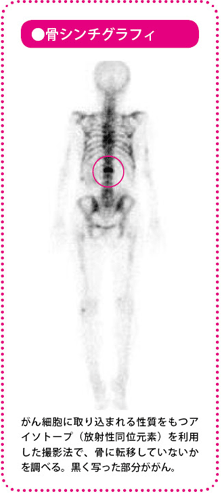
乳がんの確定診断において、腋窩(わきの下)リンパ節への転移があるかないかを調べることも非常に重要です。転移の有無によって、がんだけでなく、わきの下のリンパ節を脂肪組織ごと摘出(腋窩リンパ節郭清)するかどうかが決まるからです。これを調べる方法が、「センチネルリンパ節生検」です。
乳房から遠い位置にある臓器への転移を調べる方法には、「PET(ポジトロン・エミッション・トポロジー)検査」「骨シンチグラフィ」があります。
・PET検査
PETは全身のどこに転移があるかを調べる検査です。
がん細胞は、増殖のために正常細胞の5~8倍の量のブドウ糖を取り込みます。そこでこの性質を利用し、ブドウ糖に似たFDGという物質を体内に注射して、それが集まった部分をPETカメラで撮影します。脳や膀胱(ぼうこう)以外でFDGが集まっている部分に、転移が疑われます(脳や膀胱はもともとブドウ糖がたくさん存在する部位なので、PETの対象にはなりにくい)。
・骨シンチグラフィ
乳がんは骨に転移しやすい性質があります。そこでがんに取り込まれやすいアイソトープ(放射性同位元素)と呼ばれる物質を体内に注射し、シンチカメラで撮影します。これによって骨に転移があるかどうかがわかります。
がんの性質や悪性度を調べるのが病理検査
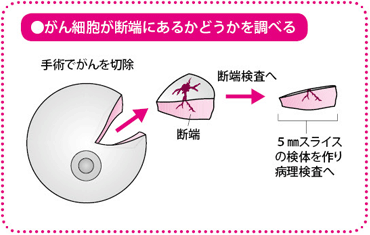
がんの治療方針を決めるのに欠かせないサブタイプ分類を調べるには、病理検査を行います。乳がんの病理検査は組織診として手術前に行うものと、手術で摘出したがんを病理検査に出して調べるものとがあります。
組織診のときは採取した組織片をそのまま検査しますが、手術後の病理検査では、さすがに切除したがんを含むかたまりをすべて調べるわけにはいきません。そこで、基本的には摘出したかたまりの端(断端(だんたん))を数カ所、外科医が切って、それを検体として病理の医師に渡します。病理検査では、組織を3~5mmくらいに薄くスライスして染色し、その細胞ががん細胞かどうかを確認します。病理の医師はそれを調べますが、この検体のなかにがん細胞がみつからなければ断端陰性となり、がん細胞がみつかれば断端陽性となります。
検査の結果が出るまでには、2週間ほどかかります(医療機関によって異なります)。また、医療機関のなかには「術中迅速診断」といって、手術中に断端を調べるところもありますが、この方法は結果がすぐにわかり、その場での対応が可能である反面、調べる方法が従来の病理検査で用いている方法と違うため、正確な診断ができにくいというデメリットもあります。