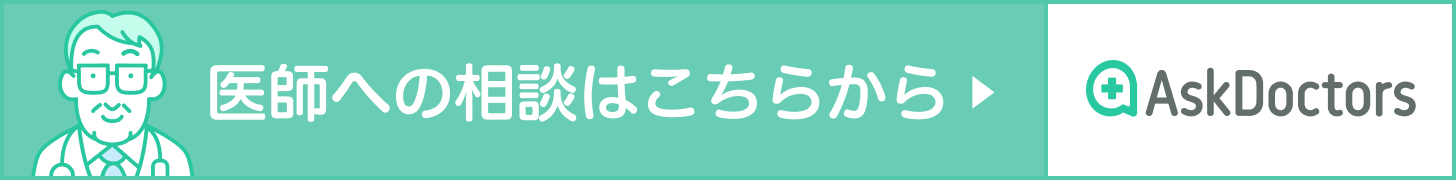相談:ステージ2の直腸がん、術後の化学療法は必要でしょうか
ステージ2の直腸がんと診断された50歳男性です。初回治療として、腹腔鏡手術を受けましたが、リンパ節への転移は見つかりませんでした。このような状況で、担当医師から「術後の化学療法をどうしますか?」と聞かれました。
リンパ節に転移がなければ化学療法はしなくてもよいと思い込んでいたため、家族とも必要か否か迷っております。化学療法を行った場合、行わなかった場合の5年生存率、10年生存率などのデータがあれば知りたいです。また、化学療法の必要性、副作用なども教えてください。
(家族、女性)
回答:ステージ2「再発高リスク」の患者さんに対しては、補助化学療法を行うことを弱く推奨
大腸癌研究会の「大腸癌治療ガイドライン医師用2019年版」によると、大腸がんの治療のポイントは以下の通りです。
大腸がんの術後補助化学療法に関して
・大腸がんの術後補助化学療法は、完全切除が行われた患者さんに対して、再発を抑制し予後を改善する目的で術後に実施される全身薬物療法です
適応の原則は、以下の通りです
・完全切除が行われたステージ3の大腸がん
・術後合併症から回復している
・全身状態が0~1
・主要臓器機能が保たれている
・重篤な術後合併症(感染症、縫合不全など)がない
大腸癌治療ガイドラインでは、ステージ2の大腸がんに、一律に術後補助化学療法を行うことは勧められていません。
大腸がんの術後補助化学療法に関して
・大腸がんの術後補助化学療法は、完全切除が行われた患者さんに対して、再発を抑制し予後を改善する目的で術後に実施される全身薬物療法です
適応の原則は、以下の通りです
・完全切除が行われたステージ3の大腸がん
・術後合併症から回復している
・全身状態が0~1
・主要臓器機能が保たれている
・重篤な術後合併症(感染症、縫合不全など)がない
大腸癌治療ガイドラインでは、ステージ2の大腸がんに、一律に術後補助化学療法を行うことは勧められていません。
その根拠として以下が挙げられています。
・3,238人の結腸・直腸がん(ステージ2:91%,結腸がん:71%)を対象とした「5-FU+レボホリナート±レバミゾール」と手術単独を比較したQUASAR試験により、化学療法を受けた患者さんの再発率および生存率は有意に良好で、5年生存率で3~4%の上乗せ効果が認められましたが、ステージ2のみに絞って解析した場合に有意差は認められませんでした
・T3N0(ステージ2a)を対象に「5-FU+レボホリナート」と手術単独を比較した臨床試験では、化学療法を受けたグループの方が治療成績が良好な傾向が見られたものの、再発率・生存率ともに有意差は認められませんでした
・ステージ2の結腸がんを対象に、術後補助化学療法として5-FUと手術単独を比較した臨床試験では、有意な再発抑制効果は証明されませんでした
一方で、大腸癌治療ガイドラインでは、ステージ2で「再発高リスク」の患者さんに対しては、補助化学療法を行うことを弱く推奨するとしています。
・海外のガイドラインでも、再発高リスクのステージ2結腸がんに対し、期待される効果と予想される副作用を十分説明したうえで術後補助化学療法を行うことが推奨されています
・再発高リスクの因子は、米国臨床腫瘍学会のガイドライン(2004年)では、「郭清リンパ節個数12個未満」「T4」「穿孔」「低分化腺がん・印環細胞がん・粘液がん」とされ、欧州臨床腫瘍学会のガイドラインでは、「T4」「低分化腺がんまたは未分化がん」「脈管侵襲」「リンパ管侵襲」「傍神経浸潤」「初発症状が腸閉塞または腸穿孔」「郭清リンパ節個数が12個未満」と規定されています
また、ステージ2の結腸がんに対する術後補助化学療法に関しては、ステージ3の結腸がんと同じ治療法と投与期間が推奨されていますが、至適投与期間に関する明確な根拠は、現時点では明らかになっていません。
直腸がんの生存率に関して
治療別の直腸がん生存率に関しては、見つけることができませんでしたが、進行度別の生存率がありましたのでご案内します。
直腸がんの10年相対生存率(2002~2006年調査)男性
限局:91.4%
領域:50.3%
遠隔:7.3%
直腸がんの5年相対生存率(2002~2006年調査)男性
限局:95.7%
領域:74%
遠隔:19.7%
限局:原発臓器に限局
領域:所属リンパ節転移(原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤なし)または隣接臓器浸潤(隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移なし)
遠隔転移:遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤あり
参考情報:
大腸癌治療ガイドライン医師用2019年版
CQ 18:Stage Ⅱ大腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか?
http://www.jsccr.jp/guideline/2019/cq.html#cq18
全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011年生存率報告(国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター, 2020)
独立行政法人国立がん研究センターがん研究開発費「地域がん登録精度向上と活用に関する研究」平成22年度報告書
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/dl/index.html#a30
・3,238人の結腸・直腸がん(ステージ2:91%,結腸がん:71%)を対象とした「5-FU+レボホリナート±レバミゾール」と手術単独を比較したQUASAR試験により、化学療法を受けた患者さんの再発率および生存率は有意に良好で、5年生存率で3~4%の上乗せ効果が認められましたが、ステージ2のみに絞って解析した場合に有意差は認められませんでした
・T3N0(ステージ2a)を対象に「5-FU+レボホリナート」と手術単独を比較した臨床試験では、化学療法を受けたグループの方が治療成績が良好な傾向が見られたものの、再発率・生存率ともに有意差は認められませんでした
・ステージ2の結腸がんを対象に、術後補助化学療法として5-FUと手術単独を比較した臨床試験では、有意な再発抑制効果は証明されませんでした
一方で、大腸癌治療ガイドラインでは、ステージ2で「再発高リスク」の患者さんに対しては、補助化学療法を行うことを弱く推奨するとしています。
・海外のガイドラインでも、再発高リスクのステージ2結腸がんに対し、期待される効果と予想される副作用を十分説明したうえで術後補助化学療法を行うことが推奨されています
・再発高リスクの因子は、米国臨床腫瘍学会のガイドライン(2004年)では、「郭清リンパ節個数12個未満」「T4」「穿孔」「低分化腺がん・印環細胞がん・粘液がん」とされ、欧州臨床腫瘍学会のガイドラインでは、「T4」「低分化腺がんまたは未分化がん」「脈管侵襲」「リンパ管侵襲」「傍神経浸潤」「初発症状が腸閉塞または腸穿孔」「郭清リンパ節個数が12個未満」と規定されています
また、ステージ2の結腸がんに対する術後補助化学療法に関しては、ステージ3の結腸がんと同じ治療法と投与期間が推奨されていますが、至適投与期間に関する明確な根拠は、現時点では明らかになっていません。
直腸がんの生存率に関して
治療別の直腸がん生存率に関しては、見つけることができませんでしたが、進行度別の生存率がありましたのでご案内します。
直腸がんの10年相対生存率(2002~2006年調査)男性
限局:91.4%
領域:50.3%
遠隔:7.3%
直腸がんの5年相対生存率(2002~2006年調査)男性
限局:95.7%
領域:74%
遠隔:19.7%
限局:原発臓器に限局
領域:所属リンパ節転移(原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤なし)または隣接臓器浸潤(隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移なし)
遠隔転移:遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤あり
参考情報:
大腸癌治療ガイドライン医師用2019年版
CQ 18:Stage Ⅱ大腸癌に術後補助化学療法は推奨されるか?
http://www.jsccr.jp/guideline/2019/cq.html#cq18
全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011年生存率報告(国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター, 2020)
独立行政法人国立がん研究センターがん研究開発費「地域がん登録精度向上と活用に関する研究」平成22年度報告書
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/data/dl/index.html#a30
医師に相談したい場合、現役医師が回答する「AskDoctors(アスクドクターズ )」の利用もおすすめです。