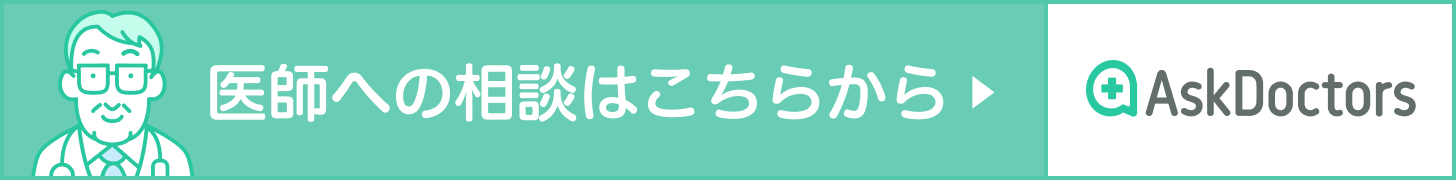相談:BCG療法の治療効果評価は「ウロビジョン」などで可能ですか?
2か月前にTURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)で筋層非浸潤膀胱がん(乳頭状膀胱腫瘍)を切除しました。その際、膀胱内に赤変した部分があったので同時に切除しました。病理検査の結果、初期の上皮内がん(CIS)と診断されました。乳頭状膀胱腫瘍の治療は完了しているので、現在はCIS治療のためBCG膀注療法を受けています。
治療終了後しばらくしたら、最初に受けたTURBTに準じた手法で膀胱内壁から数か所サンプルを切り取り、病理検査で治療効果を確認すると医師から聞いています。実際に短期入院してサンプリングし検査するのが確実ということなのでしょうが、身体的負担や仕事への影響などを考え、外来でのファイバースコープによる膀胱内視診に加えて尿細胞診で代替えできないかと考えています。最近は今までの尿細胞診の精度をフォローできる、ウロビジョンという検査も保険適用されているとのことですが、こうした外来で対処できる手法を使ってBCG膀注療法の効果確認ができないかと考えています。
(本人、男性)
回答:ウロビジョンで検出できない遺伝子変異がある膀胱がんも
膀胱がんの治療に関して、がんプラスに掲載されている記事からポイントをご案内します。また、ウロビジョンに関する情報は、医薬品医療機器総合機構の添付文書情報(体外診断用医薬品「ウロビジョン DNA FISHプローブキット」)からポイントをご案内します。
膀胱がんの経過観察
・筋層非浸潤性がんに対する経過観察は、膀胱内再発の早期発見により侵襲度の高い治療を避けることを目的に行われます
リスク分類に応じた経過観察
・筋層非浸潤性がんに対する経過観察中の検査方法、頻度、期間などはリスク分類に応じて行われますが、世界の主要機関によるガイドラインを比べると、記載が異なります。
【日本の場合】
低リスク:3か月後に膀胱鏡。その後、6か月ごとの膀胱鏡+細胞診を2年間。その後は1年ごとの膀胱鏡を5年まで。その後は臨床的判断で実施
中リスク:3か月後に膀胱鏡+細胞診。その後、6か月ごとの膀胱鏡+細胞診を3年間。その後は1年ごとの膀胱鏡+細胞診を5年まで。その後は臨床的判断で実施
高リスク:2年間は3か月ごとに膀胱鏡+細胞診。3~5年目は6か月ごとに膀胱鏡+細胞診。10年目までは1年ごとに膀胱鏡+細胞診。その後は臨床的判断で実施。尿中分子マーカーは適宜考慮。CT+CTUを3年までは毎年、その後は2年ごとに計10年程度観察
上部尿路観察:初診時にCTUなどでスクリーニング。その後、低・中リスクは臨床的判断で適宜CTU。高リスクはCTUを3年までは毎年、その後は2年ごとに計10年程度観察
AUA(米国泌尿器科学会)、EAU(欧州泌尿器科学会)、NCCN(全米総合がんセンターネットワーク)の情報は、参考記事「がんプラス 膀胱がんの再発・転移」にあります
ウロビジョンに関して
・ウロビジョンは、尿中細胞の3番、7番、17番染色体の異数倍数体(染色体の増減)、ならびに9番染色体の9p21遺伝子座の欠失を検出することで、膀胱がんの再発の診断補助に用いられる検査です
・ウロビジョンで陰性であっても、標準的な検査法(細胞診、膀胱鏡検査など)で陽性の場合は、標準的な検査法の結果が優先されます
・ウロビジョンは、膀胱がんに最も多いタイプの遺伝子変異を検出しますが、検出できない遺伝子変異を持つ膀胱がんもあります
3か月以内にBCG療法を受けた患者さんのウロビジョンと膀胱鏡検査/組織診の再発膀胱がん検出能の比較は以下の通りです
臨床的感度…92.3%
臨床的特異性…61.5%
・ここで言う感度とは、再発した人が正しく再発と判断されることです
・ここで言う特異性とは、再発していない人を正しく再発していないと判断されることです
病態はそれぞれの患者さんで異なります。なぜ病理検査が必要なのか、また身体的負担が少ない検査の希望を伝えてみてはいかがでしょうか。今後の治療方針など担当医の先生とご相談なさってみてください。
参考情報
がんプラス 膀胱がんの再発・転移
https://cancer.qlife.jp/bladder/bladder_tips/article18514.html
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 添付文書情報
ウロビジョン DNA FISHプローブキット
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/ivdDetail/100159_22900EZX00021000_A_01_02#69
医師に相談したい場合、現役医師が回答する「AskDoctors(アスクドクターズ )」の利用もおすすめです。