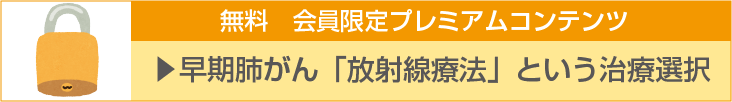非小細胞肺がん 局所再発と遠隔転移で異なる治療戦略
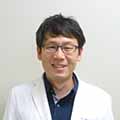
2018.6 取材・文:町口 充
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
検診技術の進歩により、肺がんは自覚症状のない早期に発見されることも増えています。進行してくると咳や息切れ、血痰、胸の痛みなどの症状が現れることがあります。がんが肺や同じ側の縦隔にとどまっている比較的早期の場合などでは、初期治療として手術や放射線による局所治療を行います。がんの再発は、手術や化学放射線治療によりいったん消失したがんが再び現れたり(局所再発)、血液やリンパの流れに乗って全身に広がったがん細胞が他の臓器で大きくなる(遠隔転移再発)ことがあります。肺がんの再発治療は抗がん剤などの薬物療法が中心となりますが、ケースによっては再手術や放射線などの局所治療で根治を目指すことがあります。薬物療法も、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤の登場により選択肢が広がっています。
遠隔転移か局所再発かで治療法は異なる
非小細胞肺がんの治療では多くの場合、手術でがんを切除したあと、再発を予防する目的に術後化学療法が行われますが、それでも再発が起こる場合があります。
再発は大きく分けると2通りです。1つは、切除した場所のすぐ近くや、肺と胸椎、胸骨に囲まれた部分である縦隔のリンパ節、あるいは放射線を照射した部位の周辺といった、限られたところで再びがんが現れる局所再発です。手術の際に取り残したがん細胞や、放射線治療で死滅させきれなかったがん細胞、初期治療の時点では確認できないほどの大きさのがん細胞が、原発巣の周囲で増殖したものです。この場合は、遠隔転移がなくまだ治癒の可能性があると判断されれば再手術が行われ、手術が困難ならば放射線治療が行われます。
もう1つは、初発の肺と逆側の肺への再発、脳や骨、肝臓といった別の臓器で再発する遠隔転移再発です。がんは血行性に転移するため、肺がんに限らず、多くのがんでは血流の豊富な肺や脳、肝臓、骨に転移が多いのです。
遠隔転移があると、病期でいえばステージIVと同列の扱いとなり、手術などの根治目的の治療は難しい状態と判断されます。検査ではがんが1か所または数か所でしか見つからない場合でも、実際には確認されていない微小な転移がほかにもたくさんあると考えられ、局所治療では制御は困難であり、全身治療である薬物療法が中心となります。
単一臓器少数個転移(オリゴメタスターシス)なら手術で根治も可能
最近、もう1つの再発のパターンとして考えられるようになってきたのが、「単一臓器少数個転移(オリゴメタスターシス)」です。これは、ステージI~IIIと診断されて治療を受けたあと、遠隔転移が見つかったものの転移病巣が1つや少数しかなく、経過観察してもそれ以外に新たな病巣が出てこないと判断される場合、遠隔転移に対して手術や放射線による局所治療を行って予後の延長を目指すケースをいいます。
オリゴメタスターシスへの治療は、大腸がんなどではよく行われています。肝臓や肺などに大腸がんの転移が見つかった場合に、早い段階で転移巣を切除するなど局所治療を行うと予後が延ばせることが報告されています。肺がんの進行は早いため、これまでは転移巣がたとえ1つでも見つかればほかにも転移が潜んでいる可能性が高く、目に見える病巣だけを切除しても意味がないと考えられていました。薬物療法の進歩などにより、最近は肺がんの分野でもオリゴメタスターシスの手法を取り入れた治療が検討されるようになっています。
たとえば、脳への転移が1か所しかない場合には、サイバーナイフ、あるいはガンマナイフによる放射線療法が行われることがあります。サイバーナイフは最先端の画像解析技術と、病変が動いても追尾できる病変追尾システム、それにロボット技術を応用した高精度の放射線治療装置のことで、ピンポイントでの放射線照射が可能なため脳転移の治療などで有効です。
ただし、肺がんのオリゴメタスターシス治療は、現段階では大規模な臨床試験で確かめられたものではなく、エビデンス(科学的根拠)のある治療として推奨されているわけではありません。どこまでがオリゴメタスターシスで、どこからがそうではないのかの線引きが定かではなく、患者さんにとってのメリットがどれだけあるのかもまだ明確になっていません。
したがって今のところ、たとえ1か所だけの転移でもほかにも転移があると考えるのが一般的な考え方ですが、今後、オリゴメタスターシスの有効性が確かめられ診断基準が明確になれば、標準的な治療選択肢の1つに加わる可能性があります。
ステージⅣの再発は分子標的薬を継続しながら局所治療する場合も
肺がんの発見時、すでにステージIVと診断された患者さんに対する治療でも、オリゴメタスターシスが注目されています。具体的には、がんの増殖にかかわる上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子の変異や未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)融合遺伝子、ROS1融合遺伝子の存在がわかった患者さんに対して分子標的薬による治療が行われている場合です。
一般的に、薬物療法中に転移が見つかると、それまでの薬はもはや効かなくなったと判断され、他の薬による二次治療に移ります。従来の抗がん剤ではがんを抑え込む期間が長くて1年ぐらいでしたが、分子標的薬を使う症例では2年、3年と制御できるまでになっています。分子標的薬によって病勢がコントロールできているなかで、たとえば脳に1か所だけの転移が見つかったという場合、その薬をやめてほかの治療に変えるのではなく、分子標的薬の投与は継続しつつサイバーナイフを用いるなどして脳転移に対する治療を行うことがあります。転移ができた臓器によっては、手術、または放射線治療、さらに手術に放射線治療を組み合わせる方法もあります。
がん細胞は、増殖・転移する過程で少しずつ“性格”や“顔つき(悪性度)”が変わっていく性質があります。このため、原発巣では投与している薬がよく効いて治療効果が継続していながら、転移した先ではがんの顔つきが変わったために薬の効果が弱くなることがあります。そのような場合、薬の投与は続けつつ、転移した顔つきの悪いがんだけを手術や放射線で治療すれば、予後の延長が期待できると考えられるのです。
同じ臓器に再度X線はできないが重粒子線治療という手段も
なお、初回治療で放射線治療を受けた場合には、再発時の治療で再び同じ場所に放射線治療を行うことは基本的にはありません。すでに初回治療でその臓器が耐えられる限界の線量を照射しているため、追加の照射が難しいからです。そのようなケースに対し、当院では重粒子線治療を行っていただくこともあります。
従来の放射線治療で使われるX線は、体外から照射される際、体の表面近くで放射線量が最大となり、それ以降は次第に減少していくので体の深いところにあるがんには十分なダメージが与えられません。そのため、多方向から照射するなどして治療効果を高める工夫が必要となり、どうしてもがん病巣以外の正常組織にもダメージを与えてしまいます。
これに対して重粒子線は体の表面では放射線量が弱く、がん病巣付近で放射線量がピークになる特性(ブラッグ・ピーク)を有しているため、まわりの組織への影響を最小限に抑え、がん病巣を狙い撃ちして放射線治療の効果を高めることができる特徴があります。
初回の放射線治療後、原発巣に隣接して1か所だけ再発があった患者さんの例ですが、重粒子線治療を追加で行った結果、その後数年たっても再発がなく元気に過ごしています。
EGFR-TKIの使用後はT790M遺伝子変異を調べたうえで二次治療を決定
再発したがんが局所治療が不適切で進行肺がんと判断された場合は、薬物療法による全身治療を行います。この場合、EGFR遺伝子変異の有無、ALK融合遺伝子の有無、ROS1融合遺伝子の有無を確かめ、遺伝子変異がある場合には、それぞれの遺伝子変異に合わせた分子標的薬を第一選択薬として使うことがガイドラインでも推奨されています。すでに分子標的薬による治療を受けた人や遺伝子変異のない人が再発した場合は、通常の細胞障害性の抗がん剤による治療が中心となります。
ただし、EGFR遺伝子変異がある場合の第1選択薬として、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)のゲフィチニブ(製品名:イレッサ)、エルロチニブ(製品名:タルセバ)、アファチニブ(製品名:ジオトリフ)という第1、第2世代の薬を使ったあとの治療薬の選択は、ほかの分子標的薬とは異なります(表1参照)。それは、薬剤耐性機序としてT790Mという遺伝子変異が新たに生じる場合があるため、治療薬を変更する際に、再度遺伝子検査が必要になります。
T790M遺伝子変異が生じた場合は、オシメルチニブ(製品名:タグリッソ)という第3世代の薬を使います。T790M遺伝子変異が生じていなければ、細胞障害性の抗がん剤が使われます。EGFRチロシンキナーゼ阻害薬を使用したあとにT790M遺伝子変異が生じるのは、どのEGFR-TKIを使った場合でも患者さんの半数くらいといわれています。最近、オシメルチニブを進行期の初回治療として用いた臨床試験で非常に有望な結果が報告されており、今後、第1、第2世代に代わってオシメルチニブによる初回治療が選択肢に加わると考えられます。
表1 EGFR遺伝子変異陽性の場合の分子標的薬(EGFRチロシンキナーゼ阻害薬)
| 一般名(製品名) | ||
| ゲフィチニブ(イレッサ) | 第1世代薬 | 第1選択薬 |
| エルロチニブ(タルセバ) | ||
| アファチニブ(ジオトリフ) | 第2世代薬 | |
| オシメルチニブ(タグリッソ) | 第3世代薬 | 再発時、T790M陽性の場合の選択薬 |
3剤あるALK融合遺伝子のどれを使うか
ALK融合遺伝子の検査で陽性だった場合は、クリゾチニブ(製品名:ザーコリ)かアレクチニブ(製品名:アレセンサ)もしくはセリチニブ(製品名:ジカディア)という分子標的薬が第1選択薬として使われます。どの薬を先に使うかという順番は明確になっていませんが、アレクチニブは効果が高くて副作用は比較的軽いといわれており、最近ではアレクチニブを最初に使う医師が多いようです。
再発した場合は、初回治療でクリゾチニブを使っていた人ならば次はアレクチニブに、アレクチニブを使っていたならばセリチニブに変えるというように、分子標的薬を変えて使う方法とともに、分子標的薬のあとに細胞障害性の抗がん薬を使うのも選択肢の1つです。どの順番で使うかは明確ではなく、副作用の出方や年齢、全身状態などを考慮して使い分けるのがベストの選択といえるでしょう。
なお、ROS1融合遺伝子については、検査で陽性となる頻度が少ないため再発時の対応も定まっていませんが、第1選択薬としてクリゾチニブが使用され、再発後は通常の抗がん剤が用いられることになります。
免疫チェックポイント阻害剤は化学療法後が基本
切除不能の進行・再発の非小細胞肺がんの治療薬として、近年、注目されているのが免疫チェックポイント阻害剤です。
ニボルマブ(製品名:オプジーボ)、ペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)はいずれも細胞障害性の抗がん剤であるプラチナ製剤併用の化学療法後に再発した患者さんに対して使われます(表2参照)。2018年4月に発売されたばかりのアテゾリズマブ(製品名:テセントリク)も、化学療法後に再発した人が対象です。
ペムブロリズマブだけは事前の検査で免疫チェックポイントの1つであるPD-L1の発現を調べて、これが発現している人にだけしか使えません。一方、ニボルマブとアテゾリズマブは、PD-L1の発現がなくても使えます。
この3薬のなかで、どれを選ぶかについての基準はまだ、明確になっていません。効果や副作用について、それぞれを直接比較したデータがないためです。ただし、PD-L1の発現が非常に高くて、TPS(PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合)が50%以上の人では、ペムブロリズマブを初回治療で使うと通常の抗がん剤より予後がよいとの進行期を対象としたデータがあるので、ペムブロリズマブは化学療法未施行の人でも使用することがあります。
表2 肺がんの免疫チェックポイント阻害薬
| 一般名(製品名) | 対象 |
| ニボルマブ(オプジーボ) | 化学療法後に再発した場合 |
| ぺムブロリズマブ(キイトルーダ) | |
| アテゾロリズマブ(テセントリク) | 化学療法後に再発し、PD-L1の発現がある場合 |
最近では、進行期において免疫チェックポイント阻害薬を単剤もしくは通常の細胞傷害性抗がん剤との併用で初回治療から使用することでより利益が大きいことを示すデータが報告されています。術後の再発などでもこれらの報告を参考にして治療が行われるようになると考えています。
免疫チェックポイント阻害剤では、治らない副作用が遅れて現れることも
免疫チェックポイント阻害剤の副作用は、従来の抗がん剤より比較的軽いといわれていますが、なかには重篤な副作用が出ることもあります。免疫に作用する薬であるため、従来の抗がん剤ではみられなかった副作用があらわれる特徴があり、この点も注意が必要です。
通常の抗がん剤の場合は、使用を止めてしばらくすると副作用の症状や体への影響が治まり元に戻ってきます。低下していた食欲は回復し、頭髪も再び生えてきます。ところが、免疫チェックポイント阻害剤の副作用の中には、治療を止めても回復しない不可逆的な副作用があります。特に内分泌系にあらわれる副作用には、1型糖尿病、甲状腺機能の低下、副腎や下垂体機能の低下などがありますが、そのまま回復しない例も少なくないといわれています。
また、副作用があらわれる時期も通常の抗がん剤とは異なります。治療を始めてすぐに出てくる副作用もありますが、何か月も経った後や、場合によっては治療効果が減退して他の薬による治療を始めて数か月たってから1型糖尿病を発症するなどの例も経験しており、副作用が出る時期の予測が難しいという問題があります。
免疫チェックポイント阻害剤の治療は、十分に治療の経験があり、副作用が起きたときにもきちんと素早く対応できる医療機関を選ぶ必要があるといえるでしょう。
プロフィール
峯岸裕司(みねぎし・ゆうじ)
2000年 国立がん研究センター東病院呼吸器内科レジデント
2003年 日本医科大学医学部呼吸器内科講座医員
2008年 日本医科大学内科学講座呼吸器・感染・腫瘍部門助手
2010年 日本医科大学内科学講座呼吸器・感染・腫瘍部門講師。日本医科大学付属病院がん診療センター化学療法科医長