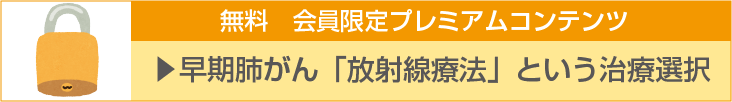非小細胞肺がんの「抗がん薬治療」治療の進め方は?治療後の経過は?
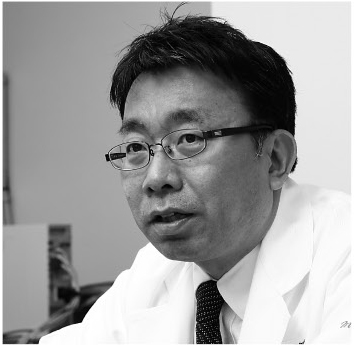
- 西尾誠人(にしお・まこと)先生
- がん研有明病院 呼吸器内科部長
1963年大阪府生まれ。89年和歌山県立医科大学医学部卒業。92年国立がんセンター中央病院医員、93年マイアミ大学微生物・免疫学教室博士研究員を経て、95年癌研究会附属病院 内科医員、2004年同内科医長。06年癌研究会有明病院(11年がん研究会有明病院に改称)呼吸器内科副部長、12年1月より現職。
本記事は、株式会社法研が2012年3月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肺がん」より許諾を得て転載しています。
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
がん細胞を攻撃し、がんの進行や再発を抑える
がん細胞の分裂・増殖を抑える抗がん薬によって、肺の局所のがん、体のどこかに潜んでいるがんを死滅させたり、縮小させたりする治療法です。
化学療法と呼ばれています。
がんを全身病としてとらえ抗がん薬によって治療

現在、肺がんで死亡する患者さんは増加傾向にあり、1年間に7万人近くに上っています。この背景には、手術療法や放射線療法が非常に進歩してきてはいても、局所療法だけでは、どうしても再発を防ぎきれないという肺がん治療の実情があります。
根治をめざす、あるいはがんを上手に抑えて患者さんがその人らしい生活をできるだけ長い期間維持していくには、肺とは遠いところに転移(遠隔転移)したがんや、目には見えないけれども全身のどこかに潜んでいる可能性のあるがん(潜在的ながん)をいかにコントロールするか。つまり、がんを全身病としてとらえて治療することが重要になってきます。
そこで、大きな役割を果たすのが、血流に乗って全身にくまなく運ばれて効果を発揮できる抗がん薬です。
それぞれの病期ごとに目的に合わせた化学療法を行う

これまで抗がん薬による治療は、主に手術療法や放射線療法といった局所療法では対応できない、すでに遠隔転移があるIV期の進行がんに対して行われていました。しかし、近年は、II~III期の手術後にも、潜在的ながんを死滅させ、再発を予防するための補助療法として積極的に導入されるようになってきています。
それぞれの病期や患者さんの状態に合わせて、手術の前後に組み合わせる(II~III期:術前補助化学療法・術後補助化学療法)、放射線療法と組み合わせる(III期:放射線化学療法)、1種類の抗がん薬だけを用いる(IV期:単剤療法)、2種類以上を同時に用いる(IV期:多剤併用療法)といった方法で、根治をめざしたり、がんの増殖を遅らせたりします。
「補助」という言葉がつきますが、転移や浸潤(しんじゅん)といった、もともと発生した場所にとどまらないがんの特性を考えると、全身に運ばれ、体のすみずみで作用する抗がん薬による治療は、がんをコントロールするためには理にかなった、非常に有効な治療であるといえます。
正常な細胞にも作用するのが難点 最近は分子標的薬の開発も
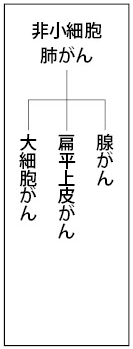
がん細胞は、変異をおこしてしまったDNAが次々に複製され、活発に細胞分裂を繰り返しながら、どんどん増えていきます。こうした増殖の過程で、DNAの合成を阻止する作用や分裂を抑える作用によって、がんを攻撃し、縮小させたり消失させたりするのが、殺細胞性といわれる抗がん薬です。ただし、このような抗がん薬の作用は、がん細胞だけでなく、細胞分裂が盛んな正常細胞にも及び、副作用として、さまざまな症状が現れることになります。
一方、最近非常に注目されているのが分子標的薬と呼ばれる種類の抗がん薬です。これは、がんの増殖のメカニズムにかかわる特定の分子を明らかにし、それを標的にしてがん細胞だけを狙い撃ちにする薬で、ここ数年、開発が進んできています。この種類の薬には、正常な細胞への影響を抑えることができるという大きなメリットがあります。
しかし、分子標的薬はどの患者さんにも効くわけではなく、患者さんのがんの遺伝子の特徴によって効果が異なります。
また、肺がんは組織型によって、大きく小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分かれます。このうち非小細胞肺がんはおおむね腺(せん)がん、扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん、大細胞がんに分類されています。
最近では非小細胞肺がんの場合、がん細胞の遺伝子のある種の変異と、分子標的薬の治療効果の関連性がわかってきています。そこで、現在は、分子標的薬の効果を予測するために、がん細胞の遺伝子のタイプを検査するようになっています。
さらに、扁平上皮がんか、それ以外のがん(非扁平上皮がん)かという組織型の違いによっても、薬の効果や副作用の現れかたに違いがあることが明らかになっています。
抗がん薬の選択にあたっては、がんの組織型、遺伝子変異のタイプの判定が、重要な条件となります。

組織型、遺伝子変異を加味して治療戦略を立てる
各病期それぞれの目的で化学療法が行われますが、肺がんに対する化学療法の基本は、シスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダなど)、またはカルボプラチン(商品名パラプラチンなど)に第三世代の抗がん薬を加える併用療法です。第三世代の抗がん薬というのは、主に1990年以降に承認された薬を指します。
シスプラチンに何を加えるか、また、2剤を組み合わせたうえに、さらに何か上乗せするかといった戦略は、患者さんのがんの組織型、病期、全身の状態に、今は遺伝子のタイプも加味して立てられます。
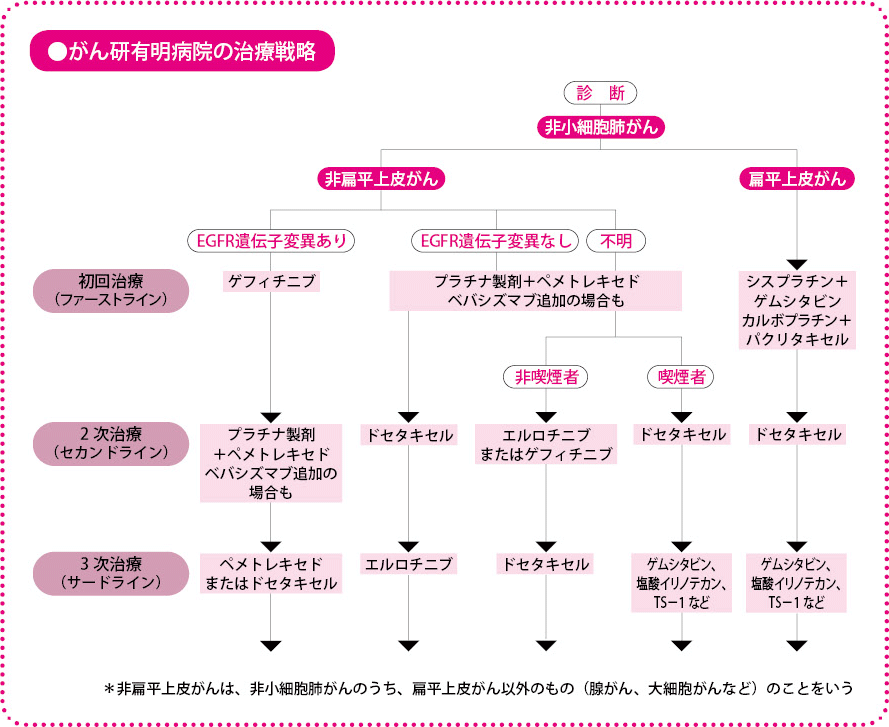
治療の進め方は?
シスプラチンに第三世代の抗がん薬をプラス、この療法を3~4週間で1コース。
副作用の出かたや効果などにより、量を調整しつつ、通常4~6コース行います。
抗がん薬は、扁平上皮がんか遺伝子変異があるかで選択

化学療法はいろいろな病期で行われますが、まず、IV期の進行がんに対する初回の治療内容とスケジュールについて解説します。すでに述べたように、化学療法の基本はシスプラチンを含む2剤併用療法です。場合によって、それにベバシズマブ(商品名アバスチン/分子標的薬)という血管新生阻害薬を加えることがあります。
シスプラチンと組み合わせる抗がん薬は、まず、組織型の分類で、扁平上皮がんであるか非扁平上皮がんであるかを考慮します。シスプラチン+ペメトレキセド(商品名アリムタ)とシスプラチン+ゲムシタビン(商品名ジェムザールなど)を比較した臨床試験によると、扁平上皮がんについてはゲムシタビンのほうが有効であり、非扁平上皮がんではペメトレキセドが有効であることがわかっています。
さらに、非扁平上皮がんであれば、ヒト上皮成長因子受容体(EGFR)の遺伝子の変異があるかないかもポイントになります。もし、変異があれば、ゲフィチニブ(商品名イレッサ)、エルロチニブ(商品名タルセバ)といった分子標的薬の効果が期待できるので、選択肢が1つ増えるわけです。変異がなければ、従来の抗がん薬を中心に考えることになります。
上乗せする薬としては、ベバシズマブが考えられますが、扁平上皮がんには使うことができません(健康保険適用外)。
進行がんに対する初回治療に用いる薬、組み合わせ例を整理すると次のようになります。
●扁平上皮がん
シスプラチン+ゲムシタビン
●非扁平上皮がん・EGFR遺伝子変異なし
シスプラチン+ペメトレキセド
(ベバシズマブを加えることもある)
●非扁平上皮がん・EGFR遺伝子変異あり
ゲフィチニブ(もしくは、シスプラチン+ペメトレキセド、ベバシズマブを加えることもある)
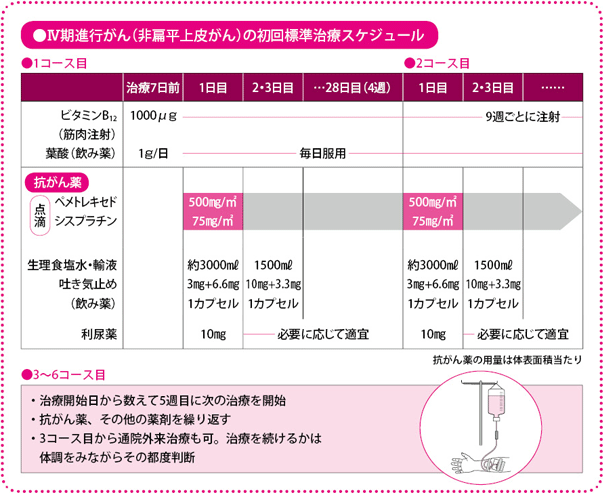
副作用の状態でコース数は考慮 体調管理のため入院治療
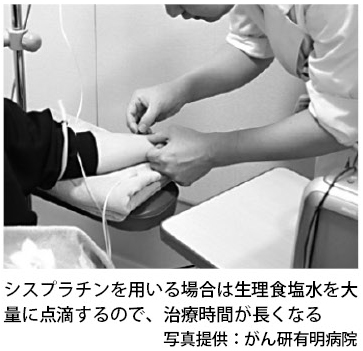
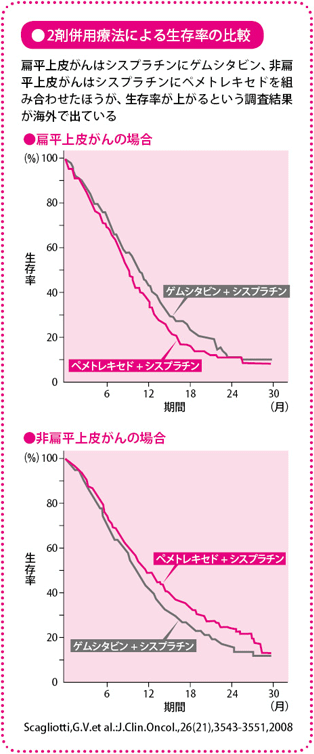
シスプラチンは、強い吐き気や、腎臓(じんぞう)への負担が大きいことが知られています。使用するときには、長時間にわたり大量に生理食塩水を点滴して、尿の量を確保するなどの予防対策や体調の管理が必要になります。もともと腎臓の機能が衰えている患者さん、長時間の点滴に耐える体力がないといった患者さんでは、カルボプラチンが選択されます。
カルボプラチンは、シスプラチンと同様の作用をもち(やや効果は劣りますが)、副作用が比較的抑えられる薬です。ただし、骨髄(造血細胞)への影響は、カルボプラチンのほうがやや強く出るので、血小板や白血球の減少には注意が必要です。
3~4週間で1コースとなりますが、抗がん薬によって投与の回数、間隔が違います。どのようなスケジュールで投与していくかの一例は、上図「IV期進行がん(非扁平上皮がん)の初回標準治療スケジュール」を参照してください。
1コース目が終了したところで、患者さんへの負担や効果を確認し、2コース目をそのまま行うか、あるいは同じ組み合わせで量を減らすか、または薬をかえるかといった検討を行います。2コース目以降、シスプラチンを用いる場合は、投与前後1週間程度の短期入院が必要ですが、カルボプラチンを用いる場合は外来で治療を行います。
患者さんの体力が耐えられれば、4~6コース繰り返します。そこで、初回治療は一旦終了し、定期的な受診をしながら経過をみるのが一般的な方法です。最近は、ここで治療を終了せずになんらかの薬の投与を続ける治療法が試みられ始めています。維持療法と呼ばれますが、これについては、後述します。
局所進行がんには化学療法と放射線療法を同時に行う
III期の一部で、手術が行えない局所進行がんの患者さんについては、化学療法と放射線療法を組み合わせますが、これを放射線化学療法と呼びます。抗がん薬の投与と放射線照射のタイミングは、順番に行うより同時に行ったほうがよいとされています。ただし、合併症の頻度も高まるので、患者さんの体力などによっては、先に化学療法を行い、その後放射線療法を行うこともあります。
抗がん薬の組み合わせは、カルボプラチンとパクリタキセル(商品名タキソールなど)を併用して、週1回投与を行う方法や、シスプラチンとビノレルビン(商品名ナベルビンなど)を併用して、4週ごとに投与する方法があります。同時に放射線療法を行う場合、その間、1日2グレイ(人体が受ける放射線のエネルギー量の単位:線量)、週5回を6週照射(総線量60グレイ)します。
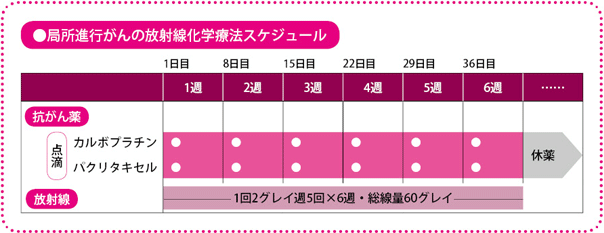
治療後の経過は?
病状や全身状態に応じて、2回目、3回目と化学療法を継続します。
最近は、休薬期間を設けずに、治療を続ける維持療法が注目されています。
自覚できない症状の管理には入院や採血で対応

従来の、殺細胞性と呼ばれる抗がん薬は、残念ながらがん細胞だけでなく、正常な細胞であっても、活発な細胞分裂を繰り返すという特徴があれば、その分裂を抑えようとしてしまいます。
そこで、分裂の盛んな消化器や口のなかの粘膜細胞、骨髄の造血細胞、毛根細胞などが影響を受けやすく、副作用として患者さんを悩ませることになります。
抗がん薬による副作用の症状、出かたには非常に個人差がありますが、どの時期にどんな症状が出やすいかには、およそのパターンがあります。そこで、予測される症状に備え、1コース目と2コース目(短期)は入院して治療を進めます。
吐き気、食欲不振といった症状がよく知られていますが、最近は有効な薬があり、予防的に飲み薬を内服したり、抗がん薬と同時に点滴をしたりするなど、事前の対策がとられるようになってきています。
吐き気などの消化器症状は、4~6日目くらいから現れます。症状はだいぶ軽減されるようになってきていますが、1週間ほど継続し、通常はその後徐々に改善していきます。
その症状がおさまったころに、今度は、造血細胞への影響である血液毒性が現れはじめます。血小板や白血球が減少し、約2週間目あたりでもっとも低い値となり、あとは回復に向かいます。
ほかに、とくに注意すべき特徴的な副作用としては、シスプラチンの腎臓への負担、ベバシズマブによる出血などが挙げられます。
1コース目は、ほぼ1週間に1度採血をし、腎機能、肝機能、血小板数、白血球数などのチェックを行います。
主にがん細胞だけを狙う分子標的薬も、副作用がまったくないわけではありません。湿疹(しっしん)がみられるほか、間質性肺炎をおこすと、ときとして生命にかかわることもあります。
投与に際しては、患者さんの肺の状態などを十分に確認する必要があります。
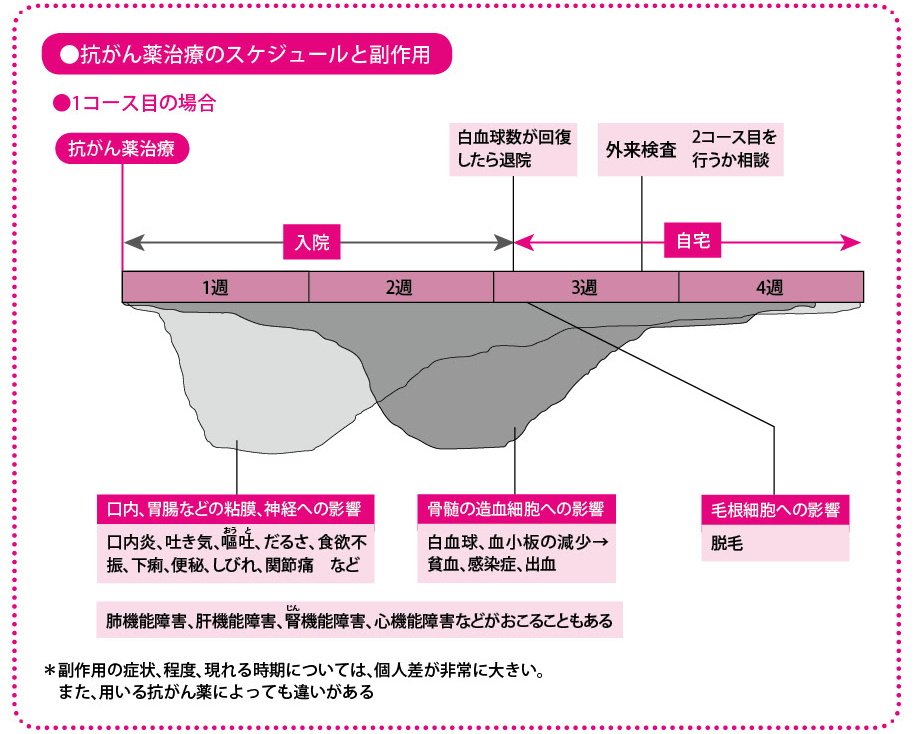
病状が悪化すれば2回目、3回目の化学療法を行う
IV期の進行がんの患者さんに対しては、化学療法によって完全にがんを消すということはできません。そこで治療の目的は、がんを小さくすること、がんの進行をできるだけ遅らせることになります。
患者さんによって、その時期はまちまちですが、初回の治療(ファーストライン)を終えたのちに、投与した抗がん薬の効果が消えて、がんが再び大きくなるといったことは、残念ながら避けられません。その際に行う2回目の化学療法を2次治療(セカンドライン)、さらにその次に行われるものを3次治療(サードライン)と呼びます。
2回目以降の治療は、1種類の抗がん薬で治療を行う単剤療法が基本となります。
初回の治療から比較的時間がたってから悪化した場合は、初回に使った抗がん薬と同じものを使うこともあります。一方、あまり間をおかずに悪化してしまった場合は、初回で使っていない薬にかえます。3回目は、また2回目と薬をかえる、というふうにして、患者さんの状態や条件を考慮しつつ、効果をみながら、治療を継続していきます。
患者さんへの負担が大きすぎて、日常生活に支障があるようでは、できるだけその人らしい生活を続けるという目的からはずれてしまいますので、薬の選択にあたっては、患者さんとよく相談しながら決めていきます。
2回目以降の治療に用いられる可能性がある薬は、ドセタキセル(商品名タキソテールなど)、ペメトレキセド、ゲフィチニブ、エルロチニブなどです。
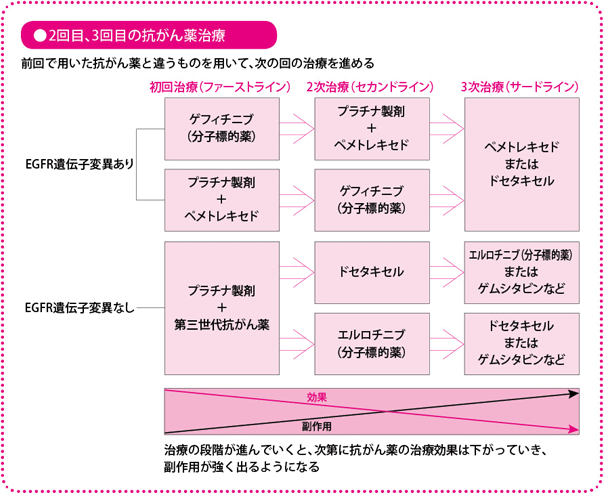
治療の切れ目をつくらない2種類の維持療法
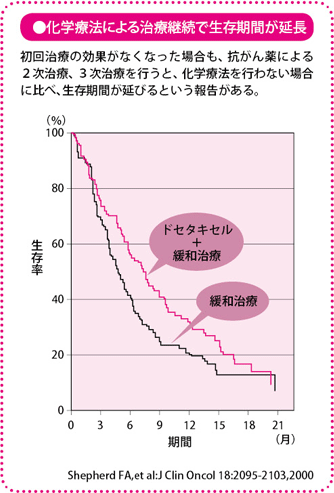
最近、効果が期待されている抗がん薬の投与法として、維持療法があります。これは、初回の治療が終わったあと、薬を休む期間を設けずに、単剤の抗がん薬の投与を続けるという方法です。
維持療法には、大きく2つの考え方があり、どちらに基づくかによって用いる薬が変わってきます。1つは、初回の治療を継続するという考えに基づく方法です。これを継続維持療法(continuation維持療法)といいます。この場合は、初回で用いていた薬のどれか1つを選んで治療を続けます。
もう1つは、切りかえ維持療法(switch維持療法)と呼ばれる方法で、これは、2次治療を早めに行うという考え方になります。この場合は、2次治療で使うつもりの薬を、初回の治療終了後、すぐ切りかえて投与し始めます。
いずれの方法も、従来の方法よりも効果が認められています。
これは、比較的毒性が低く、副作用が抑えられる抗がん薬が出てきたことによって可能になった方法といえます。ただし、副作用がまったくないわけではありません。これまでのような治療休止期間がないまま、切れ目なく治療が続くことに負担を感じる患者さんもいます。一方、休薬期間中に体調が悪化し、2次治療が行えなくなる患者さんもいます。
初回治療後の対応については、患者さんの求める生活、何を大切にして過ごしていくかといった意向を尊重して、検討すべきでしょう。
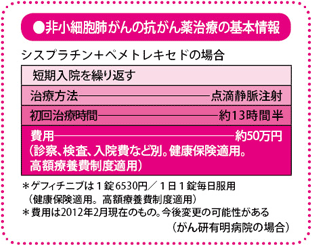
●維持療法のメリット、デメリット
・メリット
| ・がんの進行までの期間、生存期間の延長に効果があるという研究報告がある |
| ・初回治療の治療効果を持続できる |
・デメリット
| ・2次治療が行えなくなる場合がある |
| ・休みなく化学療法を続けなければならない |
| ・副作用のため、QQL(生活の質)が下がることがある |
| ・費用がかかる |
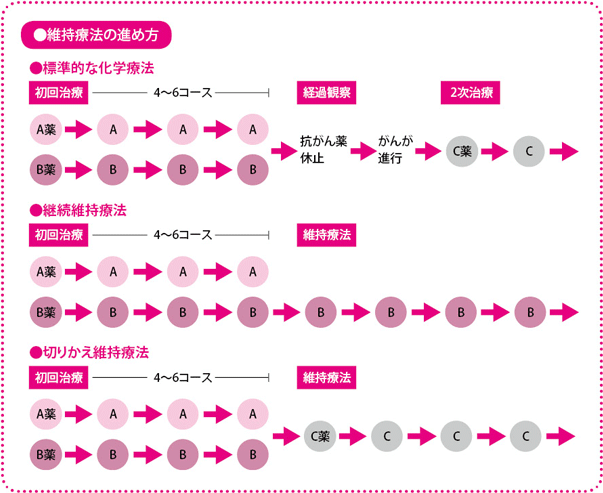
緩和ケアはがん診療の原点
痛みをはじめとし、すべての苦痛、つらい症状を極力抑える
がんと診断されたときから緩和ケアは始まる
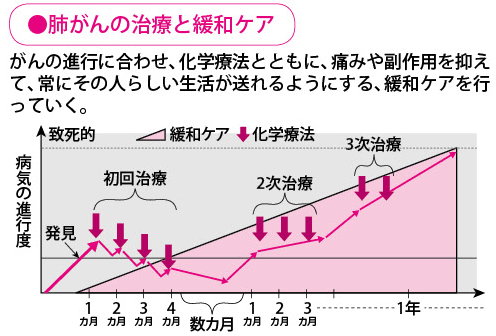
一般に「緩和ケア」というと、終末期の医療、あるいは、看取(みと)りの医療と理解している人がまだまだ多いのではないでしょうか。しかし、本来の緩和ケアは、病気が進行してしまい、積極的な治療の手段がないから行うケアとは違います。世界保健機関(WHO)によれば、がんと診断されたときから緩和ケアは必要であるとされています。
これは、がんのように生命にかかわる病気の場合、患者さんは診断を受けたときから、とまどいや驚きなど精神的にも大きく動揺し、病気による苦痛はすでに始まっていると考えられるからです。
つまり、がんの治療を始めるにあたっては、がんを治すための治療とともに、がんであることで感じる悩みや苦痛、そして治療によって生じる副作用など、すべてのつらい症状を抑え、緩和するケアを進めていく必要があるのです。
もちろん、これまでも、がん治療に伴い、患者さんがつらいと感じる症状や痛みを放置しておいたわけではありません。そのときどきに、医療者は、患者さんの苦痛を取り除こうとしてきました。しかし、残念ながら、医療者も本来の緩和ケアに対する理解が不十分だったり、スタッフが少なかったりして、患者さんの訴える苦痛にきめ細かく対応し、満足してもらう体制が整っていなかったことは事実です。
痛みは絶対にがまんしないで
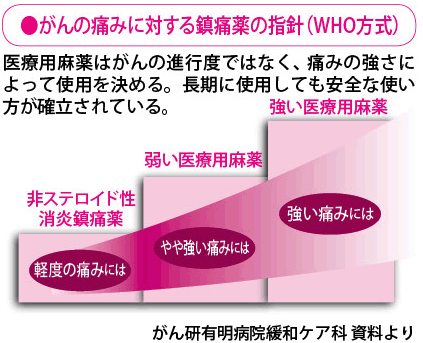
とくに、痛みへの対応については、問題が多かったかもしれません。さまざまな症状のなかでも、がんに伴う痛みは、睡眠を妨げたり、日常の活動を制限させたりして、患者さんのもつ多くの意欲を奪い、生活の質を非常に低下させます。がんの患者さんの約7割が痛みを経験するといわれています。
痛みをやわらげることができず、持続的な痛みをがまんしていると、患者さんの痛みはさらに増すという悪循環に陥ってしまいます。今は、必要に応じて、医療用麻薬(モルヒネ)を適切に使用して、痛みをコントロールすることが推奨されています。患者さんのなかには、モルヒネと聞くと「末期でなければ使えない薬である」とか、「一度使うと薬物依存になってしまう」といった誤った理解によって、痛みをがまんしてしまう人も少なくないかもしれません。以前は、医療者にさえもそうした誤解がありました。また、痛みを上手に抑える薬の使い方が確立しておらず、使いこなせる専門家も心細い状態でした。現在は、痛みをコントロールするためのモルヒネの使用法のガイドラインも示され、緩和ケアには、専門的な知識をもったスタッフが複数でチームを組んで、あたるようになっています。
生活するうえでの悩みや妨げはすべて取り除くのが緩和ケア
痛みだけでなく、抗がん薬で頻繁にみられる吐き気についても、効果的な薬が登場し、前もって服用したり、抗がん薬と同時に点滴したりすることで、かなり抑えることができるようになってきています。食欲がないときの調理の工夫や、脱毛がみられたときのかつらや帽子の利用など、生活面のさまざまなアドバイスも積極的に行われます。こうした、副作用をできるだけ抑えたり、生活に支障のないようにするケアは、支持療法と呼ばれることもあります。
そのほか、身体的なつらさだけでなく、仕事や経済面、家族の悩みなど、がんの治療を続けることで遭遇する問題には、例外なくともに向き合い、解決策を考え、できるだけ安心して治療に向かえるようなお手伝いもしています。
心身ともによい状態を保つことで、副作用の大きながんの治療にも耐えられ、効果も期待できます。患者さんは、どんな苦痛や悩みであっても、決して一人で抱え込んだり、がまんしたりせず、看護師や医師など、医療者に伝えるようにしましょう。がん研有明病院では、それを支える緩和ケアのための十分なしくみが整っています。
体力が落ちて化学療法が継続できなくなっても、できるだけその人らしい生活が保てるよう、緩和ケアを続けていきます。