乳がんのホルモン療法-女性ホルモンの作用を抑えて再発を予防

- 佐治重衡(さじ・しげひら)先生
- 京都大学大学院医学研究科 標的治療腫瘍学講座特定准教授
1968年岐阜市生まれ。1992年岐阜大学医学部卒業、東京都立駒込病院臨床・専門研修医、岐阜大学医学研究科院生、埼玉県立がんセンター研究所研修生、カロリンスカ研究所博士研究員、M.D.アンダーソンがんセンター短期留学、都立駒込病院乳腺外科・臨床試験科医長、埼玉医科大学国際医療センター腫瘍内科 准教授を経て、現在に至る。専門分野は乳がんに対する内分泌療法の臨床・基礎研究。エビデンスを創出するがんチーム医療の確立を模索している。
本記事は、株式会社法研が2011年11月25日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 乳がん」より許諾を得て転載しています。
乳がんの治療に関する最新情報は、「乳がんを知る」をご参照ください。
女性ホルモンの作用を抑えて乳がんの再発を予防
乳がんには女性ホルモンの影響で増殖するタイプ(ホルモン受容体陽性)があります。
女性ホルモンの作用を抑える薬を用いて、再発を予防します。
女性ホルモンの影響で増殖する乳がんに対して行う治療法
女性ホルモンは、女性らしい体つきにしたり、妊娠や出産などにかかわったりする大切な物質です。また、骨を丈夫にしたり、血液中の脂質を抑えて動脈硬化を予防したりする作用もあります。
女性の健康にとっては、必要不可欠な女性ホルモンですが、こと乳がんにおいては、負の影響が知られています。がん細胞のタイプによっては、女性ホルモンの作用によって、増殖してしまうのです。
乳がんにはさまざまなタイプがありますが、女性ホルモンの作用で増殖するのは、核のなかに女性ホルモンを受け入れる受容体(レセプター)が存在している(ホルモン受容体陽性)がんです。
そこで、ホルモン受容体陽性タイプの乳がんに対しては、女性ホルモンの分泌を抑えたり、働きを止めたりする薬を用いて乳がんの増殖や再発を抑えるホルモン療法(内分泌療法)を行います。
ホルモン受容体があるかどうかは、乳がん組織を調べればわかります。女性ホルモンにはエストロゲン(卵胞(らんぽう)ホルモン)とプロゲステロン(黄体(おうたい)ホルモン)の2種類がありますが、検査では両方の受容体を調べます。エストロゲン受容体(ER)、プロゲステロン受容体(PgR、PR)の二つとも陽性の場合はもちろん、どちらかが陽性であればホルモン療法が有効な患者さんと判断し、治療を行います。ホルモン療法の対象となる患者さんは乳がん患者さん全体の約7割を占めています。
ここでは、ホルモン療法の術後薬物療法について説明をしますが、最近では、「ルミナルA型」というタイプの乳がんの患者さんに対しては、がんの縮小効果を確認する意味も含めて、手術前にホルモン療法を始める術前薬物療法を積極的に行う流れになっており、術前にホルモン療法薬を用いることの有用性を実証するための臨床試験も進んでいます。
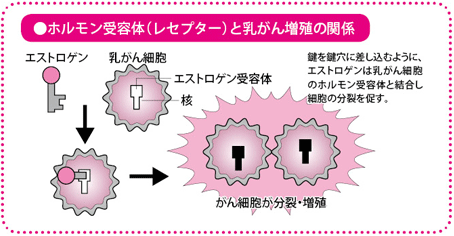
女性ホルモンはさまざまなルートに作用する
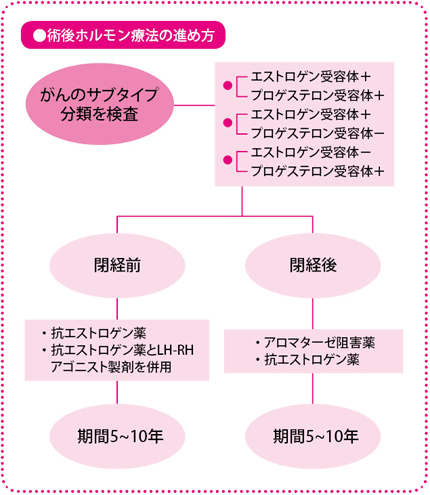
ホルモン療法に抗がん薬や分子標的薬を加える場合もありますが、抗がん薬を加える場合は、抗がん薬治療から始め、それが終わった段階でホルモン療法を始めます。分子標的薬とは併用して治療を進めることができます。
ホルモン療法に用いる薬には、抗エストロゲン薬、LH‐RHアゴニスト製剤、アロマターゼ阻害薬、プロゲステロン薬があり、それぞれ次のような特徴があります。
(1)抗エストロゲン薬
本来のエストロゲンの代わりに、がん細胞にある受容体にくっつくことで、エストロゲンと受容体との結合を阻止し、がん増殖のシグナルを抑える薬です。代表的な薬にタモキシフェン(商品名ノルバデックスなど)があり、ほかにトレミフェン(商品名フェアストン)があります。
閉経の前後で、エストロゲンを作り出す部位が大きく変わりますが、抗エストロゲン薬は、エストロゲンが作られる過程に作用するのではなく、がん細胞にエストロゲンが結合するのを止めるので、閉経前でもあとでも使うことができます。
(2)LH‐RHアゴニスト製剤
閉経前は、エストロゲンは主に卵巣で作られます。このとき卵巣に「エストロゲンを作れ」と指令を送るのが性腺(せいせん)刺激ホルモン(GnRH)です。LH‐RHアゴニスト製剤はこの分泌を止める薬です。卵巣でエストロゲンが作られなくなれば、受容体があってもがん細胞は増殖できません。LH‐RHアゴニスト製剤は卵巣でエストロゲンが作られなくなる閉経後は使われず、閉経前の患者さんに使われます。
主な薬にゴセレリン(商品名ゾラデックス)、リュープロレリン(商品名リュープリン、リュープリンSR)があります。ほかのホルモン療法薬は飲み薬ですが、LH‐RHアゴニスト製剤は注射剤となります。
(3)アロマターゼ阻害薬
閉経後になると、エストロゲンは卵巣では作られなくなり、副腎(ふくじん)から出る男性ホルモン(アンドロゲン)が腫瘍組織や脂肪組織などにあるアロマターゼという酵素の働きでエストロゲンに変換されます。このアロマターゼという酵素の作用を防いでエストロゲンができるのを止めるのが、アロマターゼ阻害薬です。当然ながら、閉経後の患者さんに有効な薬です。
アナストロゾール(商品名アリミデックス)、エキセメスタン(商品名アロマシン)、レトロゾール(商品名フェマーラ)があります。
(4)プロゲステロン薬
もう一つの女性ホルモン、プロゲステロンとして働く薬ですが、乳がんに対してはその効果やメカニズムがよくわかっていません。再発や転移乳がんでほかのホルモン療法薬が効かないときに用いられ、メドロキシプロゲステロン(商品名ヒスロンH200など)があります。
このほかに、新しいホルモン療法薬として、フルベストラント(商品名フェソロデックス)という注射薬が、2011年9月末に承認を受けました。これは、がん細胞にあるエストロゲン受容体の分解を促進する作用がある薬です。現時点での使用は、再発や転移乳がんに限られますが、それでも新しい薬として期待が集まっています。
| ●ホルモン療法に用いられる主な薬 | ||
|---|---|---|
| 一般名(商品名) | 特徴 | 投与方法 |
| 抗エストロゲン薬 | 閉経前・閉経後どちらも用いる。 エストロゲンの働きを阻害する。 |
内服(毎日) |
|
・タモキシフェン (商品名:ノルバデックス) ・タモキシフェン (商品名:タスオミン) ・トレミフェン (商品名:フェアストン) |
||
| LH-RHアゴニスト製剤 | 閉経前に用いる。 卵巣からのエストロゲンの産生を抑える。 |
皮下注射(4週/1回もしくは12週/1回) |
|
・リュープロレリン (商品名:リュープリン、リュープリンSR) ・ゴセレリン (商品名:ゾラデックス) |
||
| アロマターゼ阻害薬 | 閉経後に用いる。 アンドロゲンからのエストロゲンの合成を阻害する。 |
内服(毎日) |
|
・エキセメスタン (商品名:アロマシン) ・アナストロゾール (商品名:アリミデックス) ・レトロゾール (商品名:フェマーラ) |
||
| プロゲステロン薬 | ステロイドホルモンバランスなどに影響(作用メカニズムは完全にはわかっていない)。 | 内服(毎日) |
| ・メドロキシプロゲステロン (商品名:ヒスロンH200) |
||
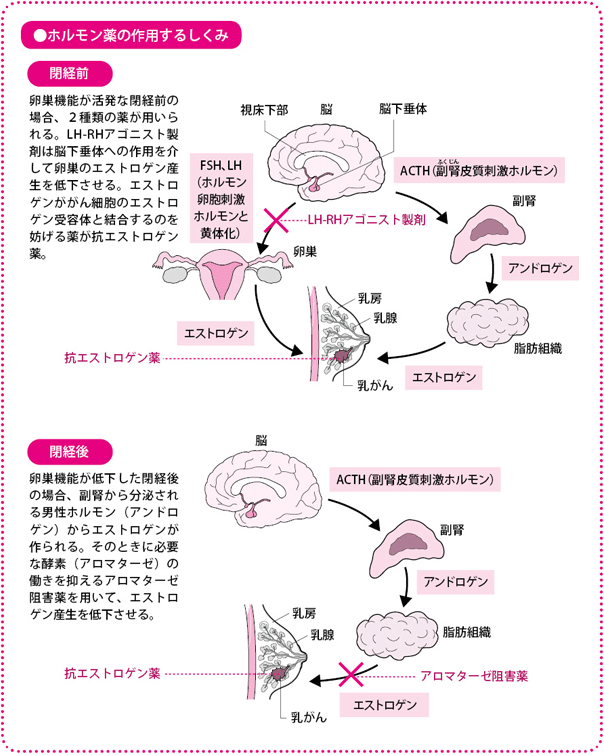
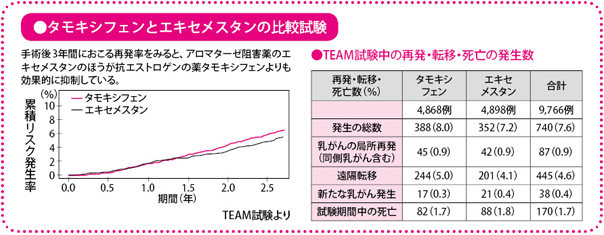
閉経前は抗エストロゲン薬閉経後はアロマターゼ阻害薬
ホルモン療法薬の選択のポイントは、閉経前か後かということです。
閉経前はほとんど卵巣でエストロゲンが作られていますから、「作れ」と指令するホルモンを抑制するLH‐RHアゴニスト製剤が効果的です。その際、「乳癌(がん)診療ガイドライン治療編2011年版」では抗エストロゲン薬のタモキシフェンを併用する方法も推奨されています。
閉経後は通常アロマターゼ阻害薬を使います。3年以内に再発するリスクについて比較した臨床試験によれば、タモキシフェンよりアロマターゼ阻害薬のほうが約13%抑えられることが確かめられています。
治療が閉経前から閉経後にまたいだ場合は、タモキシフェン±LH‐RHアゴニスト製剤を使用後にアロマターゼ阻害薬を用います。2~3年タモキシフェンを使ったあとに、アロマターゼ阻害薬に移行することも、有用な治療法です。
治療の進め方
事前の病理検査で女性ホルモンの受容体の有無を調べます。検査で受容体が多いとわかれば、ホルモン療法を行います。閉経前とあとでは使う薬、使う期間が違ってきます。
がん細胞を染色して受容体の有無を調べる
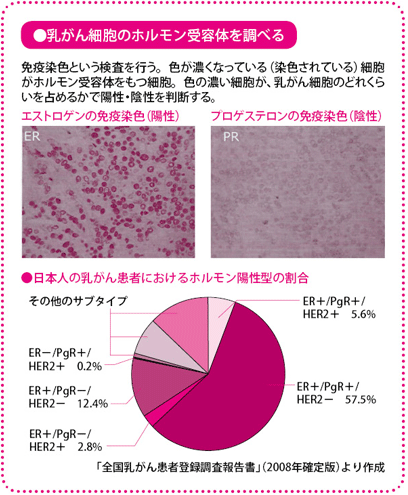
まず、ホルモン療法を行うかどうかを決めるには、ホルモン受容体の有無を調べる必要があります。針生検などで採取した組織を免疫染色し、染まりぐあいで判断します。術後薬物療法でホルモン療法を行うときには、乳がん細胞全体の1%以上が染まっていれば、陽性と判断する流れになってきています。たとえば、乳がん細胞100個のうち、1個でも染まっていれば、ホルモン療法を行います。
エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体のいずれかが陽性であれば、ホルモン療法の対象となりますが、「全国乳がん患者登録調査報告書(2008年確定版)」によると、治療の対象となる患者さん(エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体が両方、あるいはいずれかが陽性)は約7割でした(詳しくは上図の円グラフ参照)。
用いる薬は、閉経前であれば抗エストロゲン薬±LH‐RHアゴニスト製剤の併用、閉経後であればアロマターゼ阻害薬が基本的な選択になります。治療中に閉経を迎えた場合は、その時点でアロマターゼ阻害薬に変更します。
WHO(世界保健機関)では、閉経を「卵巣における卵胞の消失による永久的な停止」と定義しています。45歳以上で12カ月以上月経が来なければ閉経とみなします。
しかし、ホルモン療法では薬の作用によって月経が止まるので、本当に閉経を迎えたかどうかを調べることは難しいといえます。そこで、血液中のエストロゲンやFSH(卵胞刺激ホルモン)の濃度や年齢などを考慮して、担当医が総合的に判断します。
閉経前と閉経後それぞれについて治療の流れを紹介します。
(1)閉経前
タモキシフェンなどの抗エストロゲン薬を5年間、ゴセレリンなどのLH‐RHアゴニスト製剤を2~3年間続けます。抗エストロゲン薬は飲み薬で1日1~2回、服用します。これに対し、LH‐RHアゴニスト製剤は4週間に1回(または12週間に1回)、皮下に注射します。
若年性の乳がんで、閉経を迎えるまで時間がある患者さんは、タモキシフェン±LH‐RHアゴニスト製剤だけで治療を終えることが一般的です。しかし、リンパ節転移が高度に陽性であった患者さんなどでは、年齢や合併症、生活上の要因なども考えたうえで、本人とも相談してなんらかのホルモン療法をより長期に継続できないかを考えます(私見)。
(2)閉経後
アロマターゼ阻害薬のアナストロゾール、あるいはエキセメスタン、レトロゾールを5年間続けます。飲み薬なので1日1回服用します。抗エストロゲン薬の5年服用も選択することができます。
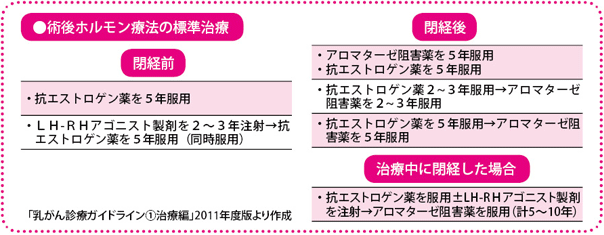
治療後の経過
ホルモン受容体陽性の乳がんに対しては高い有効性が認められています。副作用は抗がん薬とは傾向が異なって長期的な影響があり、関節痛、更年期障害に似た症状や骨粗しょう症などがあります。
ホルモン療法薬の有効性が実証 治療期間については検討中
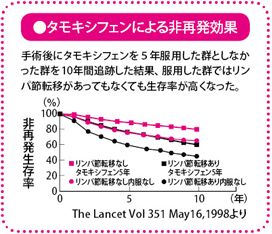
ホルモン受容体陽性の乳がんに対してホルモン療法をすると、再発を予防できる効果が高いことが、多くの臨床試験で明らかになっています。
たとえば、タモキシフェンを5年間服用したグループと、服用しなかったグループとで、10年間にわたって比較したところ、リンパ節転移の有無にかかわらず、服用したグループのほうで再発しない率を上げるという結果が出ました。また、50歳以上でタモキシフェンを使うと、ある1年間に再発するはずであった患者さんの割合を約50%減らせることがわかっています。抗がん薬が20%ですから、それと比べると大変高いことがわかります。50歳未満でもほぼ同じ傾向が出ています。
これだけの「力」が認められたからこそ、手術後に行うホルモン療法が標準治療になったともいえます。しかもホルモン療法の場合、服用期間を過ぎても効果が維持されることが知られています。これは抗がん薬ではみられない、大きな利点です。
ただ、ホルモン受容体陽性の乳がんは陰性乳がんに比べて、手術後3年ぐらいまでは再発リスクが低いのですが、それ以降は陰性乳がんより再発リスクが維持されてしまいます。そこで、5年を過ぎても治療を継続したほうがいいのではないかとも考えられていて、その臨床試験が現在進行中です。
薬による副作用は数週間~数カ月で改善する
ホルモン療法で使う薬も、抗がん薬ほど急激なものではありませんが、副作用があります。多くは女性ホルモンの作用を抑えられて急激に体内のホルモン環境が変わることによって生じるもので、更年期におこるような症状が特徴です。
代表的な副作用は、のぼせ、ほてり、発汗、頭重感などで、数週間から数カ月、場合によっては年単位で続きます。体が新しいホルモン環境に慣れれば、次第に症状は治まっていきます。またうつ症状が出たとき、抗うつ薬のパロキセチン(商品名パキシル)はタモキシフェンを使用している患者さんでは薬の効果を下げてしまう可能性があるので、使うことはできません。
タモキシフェンを使うと、子宮体がんになるリスクが数倍高まるとされています。ただし、実際には一般の女性が子宮体がんになる率は1000人中3~4人なので、それが10人前後に増える程度です。年に一度、子宮体がん検査を受けることが勧められていますが、明確な根拠があるわけではありません。私自身は、定期的な検査の必要性は低いと考えており、それよりもむしろ、体の変化に注意するように患者さんには伝えています。不正出血などいつもと違う症状があったら、すぐ婦人科を受診することが大切です。
そのほかに、まれに白内障が進行したり、味がわかりにくかったりするようになることもあります。
アロマターゼ阻害薬は、長い間、服用していると骨がもろくなる骨粗しょう症が心配されます。一定期間ごと(半年~1年)に骨密度を測定して、必要に応じて骨粗しょう症の薬を飲むことで予防できます。
また、関節痛もおこりやすい副作用です。朝、手がこわばる、歩くときにひざが痛くなるといった症状が代表的で、「ギシギシと油が切れたような感じ」と表現される患者さんが多いようです。鎮痛薬や理学療法で対応することもありますが、なかなか改善されないことも事実です。日常生活に影響が強い場合は、ホルモン療法薬の種類を変更することもあります。
| ●ホルモン療法薬の副作用 | |
|---|---|
| 一般名(商品名) | 主な副作用 |
| LH-RHアゴニスト製剤 | ほてり・熱っぽさ・肩こりなどの更年期症状に似た症状、食欲不振、疲労感、めまい など |
|
・ゴセレリン (商品名:ゾラデックス) ・リュープロレリン (商品名:リュープリン) |
|
| アロマターゼ阻害薬 | ほてり・熱っぽさ・肩こりなどの更年期症状に似た症状、めまい、関節痛(朝の手のこわばり)、不眠 など |
|
・エキセメスタン (商品名:アロマシン) ・アナストロゾール (商品名:アリミデックス) ・レトロゾール (商品名:フェマーラ) |
|
| 抗エストロゲン薬 | ほてり・熱っぽさなどの更年期症状に似た症状、おりもの、血栓症 など |
|
・タモキシフェン (商品名:ノルバデックス) ・トレミフェン (商品名:フェアストン) |
|
| プロゲステロン薬 | 食欲増進(体重増加)、ムーンフェイス、月経異常、血栓症 など |
|
・メドロキシプロゲステロン (商品名:ヒスロンH200) |
|

