再発・転移乳がんとはどんな状態?局所・領域再発と遠隔転移再発で異なる治療選択肢と目標設定
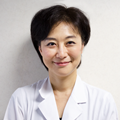
2017.9 取材・文:柄川昭彦
乳がんの治療に関する最新情報は、「乳がんを知る」をご参照ください。
乳がんで手術を受けて、いったんはがんがなくなっても、時間をおいて再びがんが現れてくることがあります。これが再発です。再発には、乳房とその周囲のリンパ節に起こる「局所・領域再発」と、乳房から空間的に離れた臓器に起こる「遠隔転移再発」とがあります。局所・領域再発の場合は、基本的に根治を目標に治療が行われます。これに対し遠隔転移の場合には、体内のがんをゼロにすることは基本的にできないので、「今できている生活をできるだけ維持していくこと」が治療の目標となります。治療の中心となるのは、薬物を使った全身療法で、乳がんのタイプに応じて、ホルモン療法、分子標的療法、化学療法などが行われます。緩和ケアも遠隔転移の治療では非常に重要です。また、手術や放射線治療といった局所療法も、症状緩和のために行われることがあります。
「再発」には「局所・領域再発」と「遠隔転移再発」という2つのタイプが
乳がんを初めて発症した際、がんが乳房やその周囲のリンパ節に限局していれば、通常は手術が行われ、必要に応じて術前あるいは術後の薬物治療や、放射線治療が加えられます。こうした治療によって、体内のがんはなくなり、画像検査などで見えない状態になります。そのまま治癒してしまえばよいのですが、時間をおいて再びがんが現れてくることがあります。これが「再発」です。
再発は、がんの現れてくる部位によって、大きく分けて2つに分類されています。
1つは、初発時と同側の乳房や胸壁、その所属リンパ節に起きてくる「局所・領域再発」です。所属リンパ節には、乳房内、腋下、鎖骨上、鎖骨下、傍胸骨のリンパ節が含まれます。
もう1つが、局所・領域ではなく、肺、肝臓、骨、脳などのように、乳房から空間的に離れた臓器に現れてくる再発です。これを「遠隔転移再発」と呼んでいます。再発で多いのは、遠隔転移のほうです。
遠隔転移が起きるのは、がん細胞が血管やリンパ管を通って全身に運ばれていくためです。とくに乳がんは、比較的小さい時期から血管やリンパ管に入っていきやすい性質を持っているため、遠隔転移が起きやすいのです。
再発の種類 |
||
局所・領域再発 |
遠隔転移再発肺、肝臓、脳、骨、など全身の臓器 |
|
局所再発(同側の)乳房内、 皮膚を含む胸壁 |
領域再発(同側の) 腋窩リンパ節、 鎖骨上リンパ節、胸骨傍リンパ節 |
|
乳がん治療ガイドライン 総論を参考にがん+編集部が作成
(http://jbcs.gr.jp/guidline/guideline/g2/g20800/)
治療目標が異なる局所・領域再発と遠隔転移再発
局所・領域再発の場合は、がんがその領域に限られるので、局所療法でがんを取り除き、根治を目指した治療を行うのが基本となります。たとえば、再発したがんを手術で取り除き、必要に応じて放射線治療や薬物治療を加える、といったことが行われます。治療の考え方は、最初に発見された乳がんが、乳房や周囲のリンパ節に限局している場合と同じです。
ただし、すでに1回治療を行っていることもあり、具体的にどのような治療を行えるかは、患者さんによって異なっています。原則としては、根治を目標にした治療になりますが、それができない場合もあります。
遠隔転移再発の場合は、治療目標が局所・領域再発の場合とは異なります。遠隔転移が起きているということは、がんが全身に飛び火している可能性があるので、全身治療が基本となるのです。たとえば肺に再発したからといって、肺のがんだけ切除すればいいということにはなりません。「見えているがん」だけ取っても、「見えないがん」が体内に残っていると考えられるからです。
そこで薬物による全身治療が行われます。しかし、それによって体内のがんをゼロにできるかというと、基本的にはできません。画像検査でがんが見えなくなることはありますが、いずれ増殖してきます。ごくまれに、がんが治癒したかのような状態が10年、20年と続く人もいます。しかし、原則的には、再発したがんが見えなくなっても、また出てきます。遠隔転移がある場合には、一生にわたってがんを抱えて生きて行くことになる、と考えてください。そこで、遠隔転移がある場合の治療は、「今できている生活をできるだけいつまでも維持していくこと」を目標にします。治療目標は、がんをゼロにすることでも、がんを小さくすることでもありません。
では、治らないのに、なぜ薬物による治療を行うのでしょうか。理由は2つあります。1つは、薬でがんが小さくなり、大きくならない状態が続けば、その分だけ延命につながると考えられるからです。もう1つは、がんがあることで現れている症状は、がんが小さくなると和らぐからです。がんを根治させるためではなく、この2つの目的のために、薬による治療が行われます。
ただし、遠隔転移に対する治療は、そこにがんがあるというだけでは行われません。薬による治療を行えば、その副作用によって、QOL(生活の質)が低下してしまう場合もあるからです。今の生活をできるだけ維持することが目標ですから、生活の質を低下させてしまう治療なら、無理にしないほうがいいという考え方もできます。術後の遠隔転移再発に対する薬による治療は、早く始めても生存期間が延びるわけではない、というデータもあります。小さい遠隔転移がただちに生命に関わることはありません。遠隔転移再発がみつかっても、「早く治療しなくては」、とあせる必要はないことがほとんどです。現在の生活とのバランスを考えながら、よく考えてから治療を開始すればよいのです。
このように、遠隔転移再発の治療を行う場合、主体となるのは全身治療である薬物治療ですが、局所治療の手術や放射線治療が行われることもあります。局所治療が行われるのは、たとえば骨転移による痛みがあるような場合です。「この部分の痛みさえなければ普通に生活できる」という場合、その部分への骨への放射線治療が痛みを和らげるのに有効な場合があります。また、薬で治療できない脳転移ができたような場合も、症状をコントロールするために、手術や放射線治療が行われることがあります。つまり、遠隔転移に対する局所療法は、緩和ケアの手段として大事な役割を果たしています。また、どのような治療が行われる場合でも、心のケアを含め、あらゆる苦痛に対処する緩和ケアもとても大切です。
全身治療にはホルモン療法、分子標的療法、化学療法という3つの選択肢
遠隔転移の全身治療(薬物治療)には、ホルモン療法、分子標的療法、化学療法という3つの方法があります。
ホルモン療法
乳がんの7~8割は女性ホルモンに対する受容体を持っていて、ここに女性ホルモンが結合するとこでがんが増殖します。その女性ホルモンの働きを抑える治療です。 患者さんが閉経前の場合には、下垂体に作用して卵巣からの女性ホルモンの分泌を抑える「LH-RHアナログ」という薬が使われます。閉経後になると、卵巣からの女性ホルモンの分泌はなくなります。しかし、副腎から分泌される男性ホルモンが、アロマターゼという酵素の働きで女性ホルモンに変わり、これががんに対する増殖刺激となります。そこで、アロマターゼの働きを抑える「アロマターゼ阻害薬」が、閉経後の乳がんに対しては使われています。 別の働きをする薬として、女性ホルモン受容体をブロックするタモキシフェンや、女性ホルモンの受容体を変質させるフルベステラントなどが使われることもあります。
主なホルモン剤
| 分類 | 一般名 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| LH-RHアナログ製剤 | リュープロレリン | リュープリンなど | |
| ゴセレリン | ゾラデックス | ||
| 抗エストロゲン薬 | 選択的エストロゲン受容体修飾薬 | タモキシフェン トレミフェン | ノルバデックスなど フェアストンなど |
| 選択的エストロゲン受容体抑制薬 | フルベストラント | フェソロデックス | |
| 黄体ホルモン剤 | プロゲステロン | メドロキシプロゲステロン | ヒスロンHなど |
| アロマターゼ阻害薬 | アナストロゾール エキセメスタン レトロゾール | アリミデックスなど アロマシンなど フェマーラなど | |
分子標的治療
いろいろな種類がありますが、最もよく使われているのは、「抗HER2薬」と呼ばれる種類の分子標的薬です。トラスツズマブ(製品名:ハーセプチン)など、数種類の抗HER2薬があり、化学療法と併用する形で治療に使われます。 乳がんの15~20%は、HER2遺伝子が増幅し、細胞の表面にHER2タンパクがたくさん発現していて、がんが無制限に増殖していくのに関わっています。抗HER2薬は、HER2タンパクの働きを抑え、併用する化学療法の効果を高めることができます。
主な分子標的治療薬
| 分類 | 一般名 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| 抗体 | 抗HER2薬 | トラスツズマブ ペルツズマブ | ハーセプチン パージェタ |
| 抗HER2薬+抗がん剤 | トラスツズマブエムタンシン | カドサイラ | |
| 血管新生阻害薬 | ベバシズマブ | アバスチン | |
| 小分子化合物 | 抗HER2薬 | ラパチニブ | タイケルブ |
| mTOR阻害薬 | エベロリムス | アフィニトール | |
化学療法
がん細胞にとっても、正常細胞にとっても毒性を発揮する薬です。乳がんの治療ではアンスラサイクリン系とタキサン系が代表的な化学療法薬として知られています。しかし、それは術前・術後の治療で使われることが多いため、再発した場合には、その組み合わせが第1選択になるわけではありません。多くの薬の中から、患者さんの状況に合わせて、メリットとデメリットを考えながら選択していくことになります。
| 分類 | 一般名 | 製品名 | |
|---|---|---|---|
| アルキル化薬 | シクロホスファミド | エンドキサン | |
| 代謝拮抗薬 | ピリミジン | フルオロウラシル テガフール・ウラシル カペシタビン テガフール・ギメラシル・オテラシル ゲムシタビン |
5-FU ユーエフティ ゼローダ ティーエスワン ジェムザール |
| 葉酸 | メトトレキサート | メソトレキセート | |
| 抗生物質 | アンスラサイクリン | ドキソルビシン エピルビシン |
アドリアシン ファルモルビシン |
| 微小管阻害薬 | ビンカアルカロイド | ビノレルビン | ナベルビン |
| タキサン | パクリタキセル ナブパクリタキセル ドセタキセル |
タキソール アブラキサン タキソテール |
|
| チューブリン重合阻害薬 | エリブリン | ハラヴェン | |
| プラチナ系薬 | カルボプラチン※ | パラプラチン | |
| トポイソメラーゼⅠ阻害薬 | イリノテカン | カンプト,トポテシン | |
※国内では、HER2陽性乳がんに対する抗HER2薬およびタキサン系薬剤との併用療法での使用のみ承認されています。
ホルモン療法、分子標的療法、化学療法という治療法がありますが、この中で最もデメリットの少ない治療法はホルモン療法です。女性ホルモンの欠乏症状が出ることはありますが、強い症状が現れる副作用はありません。脱毛や皮膚症状など、外見が変化する心配もありません。そのため、今まで通りの日常生活を送れる可能性が高い治療法なのです。そこで、ホルモン受容体陽性の乳がんであれば、まずはホルモン療法から治療を開始します。
しかし、ホルモン療法を続けていくと、いずれホルモン療法が効きにくい状態になってきます。そうなった場合には、ホルモン療法から化学療法に切り替える必要があります。そして、HER2陽性であれば、化学療法と抗HER2薬を併用します。HER2陰性の場合には、化学療法で治療していくことになります。
HER2陽性の乳がんに対しては、トラスツズマブとペルツズマブという2種類の抗HER2薬と、さらに化学療法を併用する3剤併用療法が行われています。この治療では、生存期間中央値がおよそ5年まで延びています。
新しい治療として、アナストロゾールやレトロゾールといったアロマターゼ阻害剤がききにくくなったホルモン受容体陽性HER2陰性乳がんにおいて、エキセメスタンという別の種類のアロマターゼ阻害剤に分子標的薬のエベロリムスを使用する方法もあります。また、ホルモン療法との併用に新しい分子標的薬であるCDK4/6阻害薬や、BRCAという乳がんの遺伝に関連する遺伝子の異常を持つ患者さんに対するPARP阻害剤も、臨床試験を終え、今後の治療選択肢となることが期待されています。
医師とよく話し合い、目標を共有して治療法の選択を
このように、乳がんで遠隔転移がある再発の場合、医学的な観点で、推奨される治療は必ずしもひとつとは限りません。また、たとえば、化学療法を行った場合、1次治療だと奏効率は4~5割くらいあります。それが効かなくなって2次治療を行った場合、奏効率は3~4割程度になります。3次治療になると軒並み2割程度です。4次治療以降だと1割あるかどうか、というレベルになります。効いても効かなくても副作用は現れます。たとえば、化学療法を3次治療までやった人が、4次治療を受けるか考えるとします。もちろん、「化学療法が残っているなら受ける」という選択もあるでしょう。その一方で、「1割程度にしか効果がないのなら、それはやめて緩和ケアを受ける」という選択もあります。こういった場面での選択に、型通りの正解はありません。主治医とよく話し合う中から、自分なりの正解を見つけていくことが大切なのです。
このように複数の治療の選択肢の中から、自分の病状や生活の状況に合った治療法を選ぶためには、主治医とのコミュニケーションが非常に大切になってきます。最近では、「シェアード・ディシジョン・メイキング」(shared decision making, SDM)といって、医療者と患者が、病状と治療に関する正確な情報を共有し、治療の選択肢について検討し、患者さん目線での治療の価値をよく話し合って、納得できる形で治療方針を立てていくことが提唱されています。治療法を選択するときには、治療の目標に立ち返り、「がんと付き合いながら自分の生活や人生を実現する」ために、どの治療を受けるのがいいかを考えるようにしましょう。
プロフィール
清水千佳子(しみずちかこ)
2003年 国立がんセンター中央病院乳腺・腫瘍内科医員
2003年 M.D. Anderson Cancer Center Medical Exchange Program参加
2010年 国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科スタッフ
2012年 同外来・病棟医長、2013年アピアランス支援室兼任
2014年より現職、2017年 遺伝子診療部門兼任

