「大腸がんはよく治るがん」だからこそ検診を 山口茂樹先生
本記事は、株式会社法研が2012年6月26日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 大腸がん」より許諾を得て転載しています。
大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。
患者さんの命を守る手だてはいくつもある。そんな予後のよい大腸がんだからこそ、検診、検査を受けてほしい。
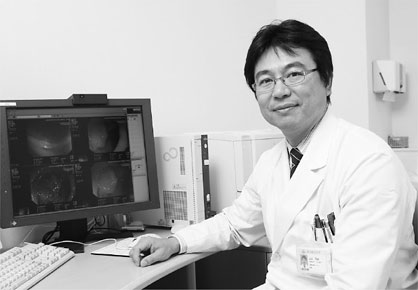
横浜(横浜市立大学医学部附属病院)のころは「帰りの信号は点滅しか見たことがなかった」という山口先生。1日の仕事を終え、帰宅が深夜に及ぶのが当たり前の日々でした。その後、静岡県立静岡がんセンター、現在の埼玉医科大学と勤務先が変わっても、帰宅時間はあまり早くなりません。「夜の11時前に帰ることはない、ずっとそんな生活です」。週日の忙しさは、事務仕事に費やす時間も多く、臨床医としてはもの足りなさを感じる山口先生は、休日の日曜日も病棟に顔を出します。「みなさん、そうなんじゃないですか。日曜以外、ゆっくり時間は取れない。朝のうちに回診して、普段時間を取れないぶん、じっくりと話を聞き、こちらも安心して家に帰る」。
人間対人間として接すること、それを山口先生は大切にしています。「本当に忙しいので、油断すると、医師として、人間として半分くらい自分自身を見失いそうになりがち。僕らにとっては毎日のことでも、患者さんにとって、がんという診断も、手術も初めてのこと。何から何まで不安でいっぱい。そこを忘れて、流れ作業になってしまわないように、心がけています」。
学生時代、実習でいろいろな診療科を回り、点滴をオーダーしたきり研究室に閉じこもる先輩、手術が終わると患者さんのようすを見に病棟まで出向く先輩、いろいろな医師の姿を見て「自分がやろうとしている医者はこれ(後者)」と思ったとの言葉が、患者さんに寄り添う今の山口先生の姿勢につながります。
消化器外科医としては、1999年、アメリカ(ニューヨーク・マウント・サイナイ病院)留学が一つの転機になったといいます。日本でも大腸がんに対して腹腔鏡手術が広がりはじめたころでした。
当時、直腸がんの神経温存手術に熱心に取り組んでいた山口先生にとって、当初の腹腔鏡手術への本音は「あまり信用していなかった」。しかし、留学先で創始者の一人ミルソム(Milsom)医師のもと、間近で何例か手術を見るうちに「世界が変わった。これは確かに画期的、かなりなんでもできる手技」と実感します。何より目をみはったのは、手術後の患者さんが元気そのものだということ。「もともと、アメリカは入院日数が短いですが、1週間もしないうちに患者さんがどんどん退院していく」。その姿は、腸閉塞で退院延期や入退院をくり返す例が少なくなかった日本での現状に比べ、新鮮な驚きでした。
帰国後、本格的に腹腔鏡手術に取り組むようになった山口先生、「最初は試行錯誤だった」そうですが、横浜で2年、静岡に移って5年を経て、今では確かな手技として確立させています。
「こうした低侵襲の手術が登場してきたことで、これまで手術で根治できるのに、あきらめざるをえなかった人にも手術が可能になってきました。ただし、全身状態は普通の人たちより悪いので、リスクは高くなるし、準備はより大切になります。残念ながら術後合併症がおこったときは、同じことをくり返さないように、何が悪かったか、次はどうしていけばよいのか、じっくり反省します」。新しい手技を確立させ、広く普及させるには、先人の挑戦する勇気と謙虚な分析と反省、それを持続する根気が必要なのかもしれません。
「いつの時代でも、医師がやりがいを感じるのは、患者さんの笑顔。死ぬかもしれないという心配、それを払拭(ふっしょく)させるための説明、そして、正確な手術。うまくいったあとに元気でニコニコしてくれていれば、あぁよかったと心から思えます」。
今後は2人に1人ががんになる時代。「大腸がんはよく治るがん」と話す山口先生。「だからこそ、検診を受けてください。まずは便潜血検査、それが陽性の場合は、必ず内視鏡検査を」。
山口茂樹(やまぐち・しげき)先生

埼玉医科大学国際医療センター 包括的がんセンター 消化器病センター長・下部消化管外科教授
1961年神奈川県生まれ。86年、横浜市立大学医学部卒。92年、同大学院修了、医学博士。99年よりニューヨークのマウント・サイナイ病院留学。帰国後、静岡県立静岡がんセンター大腸外科部長、埼玉医科大学消化器・一般外科教授を経て2007年より現職。主な役職に、日本大腸肛門病学会理事、日本消化器外科学会、日本臨床外科学会、日本内視鏡外科学会、米国大腸外科学会評議員、大腸癌研究会世話人ほか多数。大腸肛門病学会指導医、内視鏡外科の技術認定医など消化器外科の専門医として後進の指導にもあたり忙しい日々を送る。

