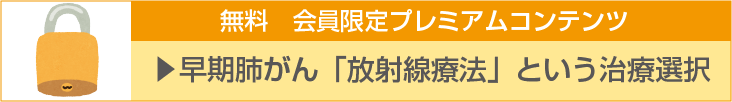よい医師の条件「ちゃんとしたことをしっかりと伝える」西尾誠人先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年3月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肺がん」より許諾を得て転載しています。
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
がんと共存が可能な時代、前向きに考えてほしいから、バッドニュースをいかに上手に伝えるかを、大切にしています。

腰椎(ようつい)転移から脊髄(せきずい)の圧迫症状で下半身まひになって寝たきりの患者さんが、歩いて退院。骨転移による大腿骨(だいたいこつ)骨折、骨盤にも多発転移がみられた患者さんは、粉砕骨折が回復し、これも歩いて退院。いずれもイレッサの「劇的」と称される効果です。「これまでの抗がん薬、薬物療法では考えられないような効果。一旦おこってしまったまひが改善されるとか、骨折が回復するとか、イレッサが登場するまでは、経験がありません」。決して大げさではなく、専門医として、その力は目を疑うほどだったといいます。
「肺がんの化学療法をやってきたなかで、大きな転換点はやはりこの薬ですね」。これまでの抗がん薬によって、いわば、やみくもにじゅうたん爆撃をかけるのも1つの戦略なら、がんのバイオロジーや発生メカニズムを解明してピンポイントで狙うというのも、また新たな戦略です。「そうした戦略をうまく組み合わせていかなくてはならない。それには、基礎と臨床の架け橋のような研究がもっと進展していかないと」とがんの「画期的な薬の開発」に意欲をみせます。
もともと科学に興味があり、科学に関与する仕事をしたくて医学部を選んだ西尾先生。肺がんの化学療法を専門にしたのも「ほとんど未解決な分野だったから。原因もわからない、治療法も確立していないところにひかれたのかな」。
思いおこせば、20数年前、化学療法は「百害あって一利なしとまでいわれていました」。まだ若かった、当時の西尾先生にとって「がんとともに生きる、がんと共存する」という言葉が詭弁(きべん)に思えたときもあったといいます。「でも、今ではなくてはならない治療として確立し、心からがんとともに生きましょうといえるようになりました」。
2人に1人はがんにかかるという時代、誰にとってもがんは人ごとではありません。「がんに対しては、若い人と高齢の人とでは考え方が違う。若い人は、少し無理をしても根治をめざしたほうがよいけれど、高齢者のがんは糖尿病などのように慢性の病気として、いかにコントロールしてつきあっていくかをめざしたほうがよいのでは」といいます。
西尾先生はよい医師の条件の1つに「ちゃんとしたことをしっかりと伝える」ことを挙げます。
「僕たち、がんに携わる医師には、グッドニュースだけでなく、バッドニュースを伝える場面がたくさんあります。それをいかにうまく伝えられるかには、僕自身とても気を遣うし、大切なこと」。つらい事実を伝えるのは確かに容易なことではありません。
以前は、告知自体、死の宣告と思われた時代もあります。「今でも、それに近い状況や、完全には治らないといったこと、副作用やリスクの説明も必要。緩和医療だけに切りかえるといったタイミングもすごく難しいです」。でも、伝えるべきことは伝える、それもできるだけ早いタイミングで、と西尾先生は心がけています。「ある程度最初の時点から今後の治療の流れを話します。根治が難しいといったことも含めてね」。厳しいともいわれますが、それは患者さんに積極的に、いかに生活をキープしながら治療するかを前向きに考えてほしいから。
「がんだからとあきらめてほしくないんです。長生きするためにはどんな治療があるのか、毒性を減らして副作用を抑えるにはどんな治療があるのか、単純に手術か薬かという選択ではなく、目標を自覚したうえで、患者さんにはよりその人に適した治療法を選んでほしい」。
よい情報も悪い情報もきちんと話すことを大事にする西尾先生。「医『学』をめざして医者になったと思っていたけど、本当はやっぱり人間が好きなんですかね」。
西尾誠人(にしお・まこと)先生
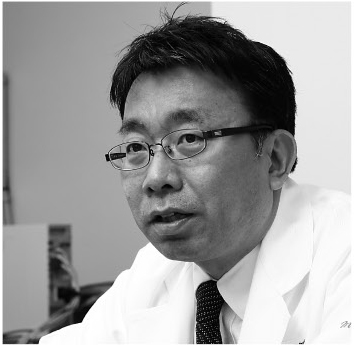
がん研有明病院 呼吸器内科部長
1963年大阪府生まれ。89年和歌山県立医科大学医学部卒業。92年国立がんセンター中央病院医員、93年マイアミ大学微生物・免疫学教室博士研究員を経て、95年癌研究会附属病院 内科医員、2004年同内科医長。06年癌研究会有明病院(11年がん研究会有明病院に改称)呼吸器内科副部長、12年1月より現職。