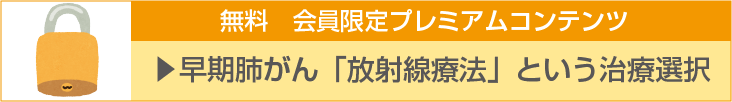進歩する肺がんの最新薬物治療 プレシジョン・メディシンと個別化医療

2018.6:取材・文 柄川昭彦
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
肺がんの薬物療法は、がんの治療の中でも特にプレシジョン・メディシン(精密医療)が進んでいます。その第一歩となったのは、2002年に承認された分子標的治療薬のゲフィチニブ(製品名:イレッサ)で、EGFR変異陽性の肺がんに有効であることが明らかになりました。その後、いくつものドライバー遺伝子が発見され、それに応じた分子標的薬が開発されています。その後、免疫チェックポイント阻害薬が登場しましたが、これに関しては、本当に有効なバイオマーカーがまだ見つかっていません。現在、世界中でその探索が進められていますが、見つかれば、免疫チェックポイント阻害薬でも個別化が進むことになります。プレシジョン・メディシンでは組織を用いた遺伝子解析が治療方針を決めるために必要ですが、将来的には血液を用いた遺伝子解析が主流となり、患者さんの負担が軽減されていくと思います。肺がんの遺伝子スクリーニングネットワークである「LC-SCRUM-Japan」※1では、2017年12月から、肺がん患者さんを対象として血液による遺伝子解析を開始しています。
分子標的薬の登場が、肺がんの個別化医療の始まり
肺がんに対する最初の分子標的治療薬として、ゲフィチニブが承認されたのは2002年のことです。この分子標的治療薬が、肺がんの個別化医療のきっかけとなりました。
ただ、当初は効果を予測できるバイオマーカーが分かっていなかったため、患者さんに投与すると、非常によく効く人と、まったく効かない人がいました。そこでがん組織の遺伝子解析が進められ、EGFR遺伝子変異がある患者さんにはよく効くが、EGFR遺伝子変異のない患者さんには効かない、ということがわかってきました。
ゲフィチニブは、奏効割合が70~80%、PFS(無増悪生存期間)がほぼ1年で、これは従来の抗がん剤治療の成績を大きく上回るものでした。さらに、毒性も従来の抗がん剤に比べて軽いこともわかり、肺がん治療における分子標的治療薬の有用性が世界中で認識されるきっかけとなりました。こうして、がん組織の遺伝子検査を行い、患者さんの遺伝子変異に対応する分子標的薬を選択するという個別化医療が始まりました。
希少ドライバー遺伝子に対する治療薬の開発
正常な細胞のがん化に関わる遺伝子をドライバー遺伝子といいます。ドライバー遺伝子には、正常な機能を失う変化と新たな機能を獲得する変化があります。肺がんに関連するドライバー遺伝子として、EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子変異、RET融合遺伝子などが見つかっています
非小細胞肺がんのうち、EGFR遺伝子変異がある患者さんの割合は、30~40%程度ですが、ALK融合遺伝子の割合は3~5%です。ROS1融合遺伝子の割合はさらに低く、1~2%程度です。
遺伝子解析の技術が進歩したことにより、その他のドライバー遺伝子も次々と見つかるようになりました。ところが、それらのドライバー遺伝子は、いずれも肺がん全体のわずか1~2%にしか見られない希少な遺伝子でした。そのため、ドライバー遺伝子が見つかっているにも関わらず、治療薬の開発につなげられないという問題が生じました。EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子変異のように、それに対する分子標的治療薬が開発されれば、そのドライバー遺伝子を持つ肺がんには高い有効性が期待できます。ところが、その頻度が1~2%と希少な場合は、大規模な臨床試験を行うことが難しいため、治療薬の開発が困難になります。
2012年に、日本で新たに発見されたドライバー遺伝子であるRET融合遺伝子もその1つで、肺がん全体の1~2%に見られます。肺がん全体のわずか1~2%しかいないのでは、1施設で見つかる患者さんが非常に少なく、従来の方法では臨床試験を実施することが困難でした。そこで、日本中で大規模に遺伝子スクリーニングを行い、患者さんを見つけ出して臨床試験につなげる仕組みを作ることにしました。こうして誕生したのが「LC-SCRUM-Japan(エルシー(Lung Cancer=肺がん)・スクラム・ジャパン)」です。
日本における肺がんの罹患数は年間約13万人ですから、わずか1~2%といっても、日本全体では1000人以上は見つかることになります。そこで、まずEGFR遺伝子変異陰性の患者さんを対象に積極的に遺伝子スクリーニングを行い、RET融合遺伝子、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子が陽性の患者さんを見つけ出し、臨床試験につなげるということが行われました。この「LC-SCRUM-Japan」の活動がスタートしたのは2013年のことです。希少ドライバー遺伝子を持つ患者さんにも、効果的な治療薬を届けたいという思いから始まった活動です。
全国的な遺伝子スクリーニングによって発見されたRET融合遺伝子陽性肺がんの患者さんは、バンデタニブ※2の臨床試験に登録されました。また、ROS1融合遺伝子陽性肺がんの患者さんは、クリゾチニブ(製品名:ザーコリ)の臨床試験に登録されました。こうして、肺がんのわずか1~2%に見られるドライバー遺伝子に対しても、それに対する治療薬を開発することが可能になりました。
「LC-SCRUM-Japan」という全国的なスクリーニング基盤ができたことで、希少ドライバー遺伝子を持つ肺がんに対する治療開発は順調に進んでいます。
肺がんの分子標的薬(承認済)一覧
| 一般名(製品名) | 標的 |
| ゲフィチニブ(イレッサ) | EGFR |
| エルロチニブ(タルセバ) | EGFR |
| アファチニブ(ジオトリフ) | EGFR |
| オシメルチニブ(タグリッソ) | EGFR |
| クリゾチニブ(ザーコリ) | ALK/ROS1 |
| アレクチニブ(アレセンサ) | ALK |
| セリチニブ(ジカディア) | ALK |
| ダブラフェニブ/トラメチニブ(タフィンラー/メキニスト) | BRAF |
免疫チェックポイント阻害薬の課題はバイオマーカー
分子標的治療薬に続いて、肺がんの治療を大きく変えたのが免疫チェックポイント阻害薬です。がん細胞が免疫から逃れる機構に働きかけ、免疫細胞が攻撃できるようにする働きがあります。日本では、切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんに対して、PD-1抗体のニボルマブ(製品名:オプジーボ)が2015年に、同じくPD-1抗体のペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)が2016年に承認され、PD-L1抗体のアテゾリズマブ(製品名:テセントリク)が2018年に承認されています。免疫チェックポイント阻害薬の奏効割合は、単剤で使用した場合には15~20%程度とあまり高くありませんが、従来の薬剤とは異なる画期的な治療薬であることは間違いありません。
どのような効き方をする薬なのか、簡単に説明しておきましょう。免疫細胞ががん細胞を攻撃しようとしたとき、免疫細胞の表面にあるPD-1と、がん細胞の表面にあるPD-L1が結合すると、免疫細胞の攻撃にはブレーキがかかってしまいます。そこで、PD-1抗体のニボルマブやペムブロリズマブは免疫細胞のPD-1に結合することで、PD-L1抗体のアテゾリズマブはがん細胞のPD-L1に結合することで、免疫にブレーキがかかるのを防ぎ、従来ヒトに備わっている免疫の力でがんを攻撃できるようにするのです。
EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のように、ドライバー遺伝子が陽性の肺がんには、1次治療でそれぞれの遺伝子に合わせた分子標的治療薬が選択されます。免疫チェックポイント阻害薬が主に使われるのは、ドライバー遺伝子が陰性の場合です。遺伝子変異が陰性の場合には、1次治療で免疫チェックポイント阻害薬が使われることもあります。一方、ドライバー遺伝子が陽性の場合は、分子標的治療薬の効果が認められなくなった場合に免疫チェックポイント阻害薬の投与が検討されます。
ニボルマブは2次治療以降に使用できる薬剤で、PD-L1陽性の細胞が1%以上ある場合に適しているとされています。これに対しペムブロリズマブは、PD-L1陽性の細胞が50%以上ある場合は一次治療から使用可能です。アテゾリズマブは、やはり2次治療以降に使用される薬剤です。
免疫チェックポイント阻害薬は有効な治療薬のひとつですが、どの人によく効き、どの人に効かないのかを見分けるバイオマーカーがまだはっきりしていません。PD-L1の免疫染色による評価が現時点ではひとつのバイオマーカーであり、陽性細胞の割合によって、薬の有効性をある程度予測できます。ただ、現時点ではまだ大まかな目安にしかならず、PD-L1が陰性の肺がんに対しても有効である場合もあります。そこで、免疫チェックポイント阻害薬のバイオマーカー探索が世界中で行われています。
日本でも、LC-SCRUM-Japanが中心となって、免疫チェックポイント阻害薬のバイオマーカー探索を行っています。免疫チェックポイント阻害薬がよく効いた肺がんと、効かなかった肺がんの遺伝子を比較し、バイオマーカーとなる遺伝子候補を探しています。
肺がんの免疫チェックポイント阻害剤
| 一般名(製品名) | 標的 |
| ニボルマブ(オプジーボ) | PD-1 |
| ペムプロリズマブ(キイトルーダ) | PD-1 |
| アテゾリズマブ(テセントリク) | PD-L1 |
| デュルバルマブ(イミフィンジ) | PD-L1 |
遺伝子解析によるプレシジョン・メディシンで、個別化が進む肺がんの薬物治療
肺がんの薬物治療は、プレシジョン・メディシンがますます進んでいきます。現在も希少ドライバー遺伝子に対する分子標的治療薬の開発が行われていますし、免疫チェックポイント阻害薬のバイオマーカー探索が進められているからです。免疫チェックポイント阻害薬のバイオマーカーが見つかれば、効果が期待できる人だけに選択的に投与できるようになります。患者さんのがんのタイプに合わせ、最も効果が期待できる治療薬を、バイオマーカーに基づいて選択する時代になるのです。
遺伝子解析の技術も進歩しています。これまでは気管支鏡や手術などで採取したがん組織を用いて解析していましたが、これからは血液で遺伝子解析を行う時代になっていきます。血液中に入り込んだがんのDNAを使って、遺伝子解析が行えるようになっています。LC-SCRUM-Japanでも昨年末から「血液を用いた遺伝子解析の研究」を開始しています。
検査の感度からいえば、現時点では、組織を使った検査のほうが高感度であることは確かです。しかし、肺がんはがん組織を採取しにくく、気管支鏡による採取は患者さんの負担が大きいのも事実です。また、肺がんは腫瘍の部分によって、遺伝子変異があったりなかったりすることがあり、採取する部位によって結果が違うということもありました。血液を使う遺伝子検査なら、そういった心配が低くなります。さらに、患者さんの負担が少なくなることで、治療によって遺伝子が変化した場合でも、その変化を繰り返して血液検査を行いながら把握することができるようになります。
血液による遺伝子解析は、患者さんから血液を採取し、血液中にわずかに存在するがんの遺伝子を検出し、検出した遺伝子の変化を調べます。
LC-SCRUM-Japanで行われている研究では、血液から73種類の遺伝子の変化を一度に測定できる「Guardant360」という新しい遺伝子解析技術を導入しています。約2000人の非小細胞肺がんの患者さんの組織と血液の遺伝子解析結果を比較し、血液を使った遺伝子解析法の感度を評価します。
プレシジョン・メディシンが進むほど、遺伝子解析の重要性が高まってきます。より簡便で、より正確で、より低価格の遺伝子解析の方法が求められています。
※1 LC-SCRUM-Japanでは、2013年から主に希少な肺がんを対象として遺伝子スクリーニングを開始し、2018年5月末までに約6500人の患者さんが登録されています。国立がん研究センターが全国の医療機関、製薬企業と協力して行っている遺伝子スクリーニング事業です。肺がん患者さんの遺伝子変化に対する治療薬や、次世代シーケンサーを使った診断薬の開発を目指しています。
※2バンデタニブ(製品名:カプレルサ)は、血管内皮増殖因子受容体2(VEGFR-2)、上皮増殖因子受容体(EGFR)、RETのそれぞれを標的とする分子標的薬で、甲状腺がんを対象として承認されています。RET肺がんの患者さんを対象とした臨床試験(LURET試験)が医師主導治験として実施されました。
プロフィール
後藤功一(ごとうこういち)
1900年 熊本大学医学部第一内科
1999年 国立がんセンター東病院 呼吸器科医師
2014年 国立がん研究センター東病院 呼吸器内科長
2014年 国立がん研究センター東病院 サポーティブケア室長併任
2017年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科包括腫瘍学連携講座教授併任