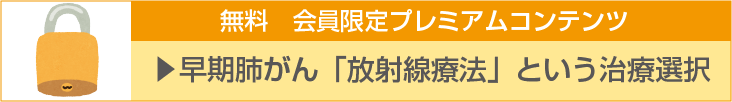「難敵」と闘った「“幸せな”手術」近藤晴彦先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年3月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肺がん」より許諾を得て転載しています。
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
最善の治療が受けられるよう患者さんの個性を尊重して話す。そこに臨床医としての思い入れがあります。
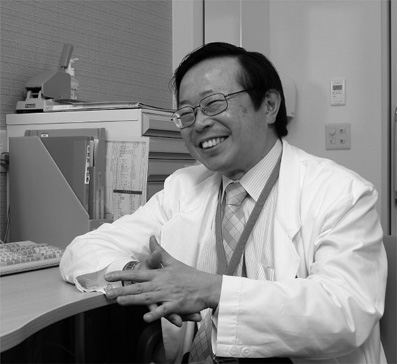
近藤先生が主治医として執刀した最初の肺がん手術は1988年。国立がんセンター(当時)のシニアレジデント(研修医)からスタッフ(医員)になってすぐのことです。「図らずも外科医として華々しいスタートを切ることができました」と、晴れ舞台を振り返ります。
患者さんは親友の父親。近藤先生が同施設のスタッフになったことを知って、親友が「ぜひ診(み)てほしい」と頼ってきたのです。他施設では「手術は無理」といわれ、放射線療法を受けていました。肺の最上部、いわゆる「胸腔の頂上」にできた肺がんであり、周囲の神経や背骨などにも広がっているため、切除はあきらめられていたのです。
この「難敵」と闘うには、背中から腕に走る神経の一部や血管を一緒に切除したり、背骨を削ったりする必要がありましたが、血管を切ってつないだり、背骨の手術が得意な整形外科医に協力してもらったり、総力を上げたチームで、手術を成功させることができました。「多くの先生方のご協力を得て、親友のお父様のお力になることができ、大変“幸せな”手術でした」。
近藤先生は、もともとは科学者志望の少年で、中学生のころから量子力学などの専門書を読み込んでいました。大学の医学部には基礎医学を学ぶことを念頭に置いて入学。それからすぐに、ご自身の父親が心臓病で入院し、これが転機となりました。父親を見舞いに行くたびに、主治医らが「医学生」としての近藤先生に声をかけてくれたのです。しかも大学には自分よりも“基礎向き”の人がいっぱいで、臨床医、それも胸部外科医という目標がはっきりしてきました。このころには、下宿に集まった友人たちの前で「全世界の人より、まず、目の前の一人の患者さんを救いたい」と宣言したとか。
胸部外科医をめざして、大学病院や三井(みつい)記念病院で研鑽(けんさん)を積むうちに、心臓よりも肺がんのほうに興味を強くもつようになり、みずからの意思で国立がんセンターへシニアレジデントとして修行に出ることにしたのです。そして国立がんセンターでの15年間で、肺がんの外科治療の第一人者になりました。
その間の患者さんのなかには、実は近藤先生の母親が含まれています。人間ドックで肺がんがみつかり、手術の適応だったものの、本人は自分の病気を認めようとしません。「手術を受けるよう説得するのに1年かかりました。母からみれば、私は医者ではなくただの息子。最後は仲間の先生に助けてもらいました」。近藤先生の手で手術は成功。ただし、近藤先生ではなく、仲間の先生が執刀したことにしてあるそうです。
もちろん、幸せな手術ばかりではありません。重大な合併症をおこした人はすべて覚えています。「こんなことがおこるかもしれないと、先にいってほしかった」という患者さんの声は忘れられないといいます。
患者さんに手術のデメリットを伝えることはもちろん必要ですが、そこを強調しすぎれば、畏縮(いしゅく)して治療のチャンスを逃してしまうかもしれません。「患者さんやご家族の状態に合わせながら、最善の治療が受けられるように話し方を工夫しています。こんなところに医師としてのスペシャリティを感じるのは、やはり基礎医学ではなく患者さんとじかに接する、臨床医向きだったのでしょう」。
根治して通院の必要がなくなっても、定期的に近藤先生を訪ねる「元」患者さんもめずらしくありません。その1人が91歳になる現役写真家の女性です。「元気をもらいに行きます、といってくださるのですが、元気なお姿に接することで私のほうがいつも元気をもらっているんです」。
患者さんやご家族に近藤先生はこう呼びかけています。「治療に関して、わからないことはそのままにせず、納得できるまで医師に尋ね、必要ならセカンドオピニオンもとるべきです」。
近藤晴彦(こんどう・はるひこ)先生
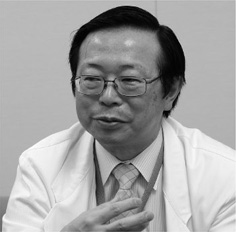
杏林大学医学部付属病院 呼吸器外科教授
1956年大阪府生まれ。東京大学医学部卒。三井記念病院外科レジデント、東大胸部外科医員等を経て、87年より国立がんセンター病院にて肺がん手術を中心とした外科診療に従事。2002年4月、静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科部長、11年1月より同副院長兼任。2012年4月から杏林大学医学部外科教室(呼吸器・甲状腺)教授に就任。