「何より大切な目標は大腸がん撲滅」田中信治先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年6月26日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 大腸がん」より許諾を得て転載しています。
大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。
内視鏡は医師の技量が露骨に出る手技。
診断と治療技術の確立は、不断の「情熱と努力」でしか成しえないと思う。
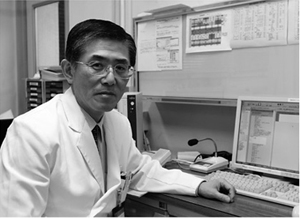
「情熱と努力」。良医、名医の条件として、技術向上や目標達成の原動力として、インタビュー中に田中先生の口から幾度となく出てきた言葉です。そのたびに、先生の表情に力がみなぎります。「ローマは1日にして成らず、ちりも積もれば山となる、千里の道も一歩から、継続は力なりといった一連の言葉が僕は大好き。1日少しの努力でも毎日やっていたらものすごい力になる」。
田中先生が専門とする内視鏡の操作は「医師の技術の差が露骨に出る」といいます。特に、手術の既往があり癒着がある人、大腸憩室(けいしつ)炎がある人などは、挿入のハードルが高くなります。一般のクリニックなどでは内視鏡がうまく入らず、紹介されてくる患者さんも少なくありません。「そうした患者さんも、僕らのところだと、8~9割はスッと入る。どうして入らなかったかが不思議なくらい」。未熟な内視鏡医が力づくで入れようとすると「死ぬほど痛い」そうです。その技術を得るのも情熱と努力。「特別なセンスや勘が必要なのではなく、うまくなりたいという気持ちと、そのための努力を怠らなければ、患者さんに安心して受けてもらえるだけの一定のレベルには達することができる」。多くの学生や後輩を教育し、また自分自身それを体現してきた田中先生だからこそいえる言葉です。「僕が初めて内視鏡検査を始めたのは27年前、当時はファイバースコープ」だったという田中先生。先生が、大腸を専門にすると決めた1990年代初期は「大腸がんでいえば、工藤進英(くどうしんえい)先生(昭和大学横浜市北部消化器センター教授)が陥凹(かんおう)型腫瘍を発見し、前処置の薬もよいものが出はじめた時代。がん以外でも、日本にクローン病や潰瘍性大腸炎などの増加の兆しがみえはじめ、まさに〝腸の時代幕開け〟のころ」。その後の変遷を思うと、歴史に立会い、歴史をつくってきたという感慨もひとしおです。
具体的な数字でみると、91年当時の広島大学病院の大腸内視鏡検査の年間受診数は約300件。それが今では約4,000件を数えるまでになっています。質の面でいえば、検査・診断から出発した内視鏡の手技は、今では治療の分野まで応用されています。内視鏡に搭載するデバイス(処置具)の開発、進化により、その目的が大きく変化してきたのです。「まだまだ可能性は広がるはず。鉗子やスネアを使えば、内視鏡は組織を切除し摘出してくるサンプリングの手段。一方、注射針などを使用すれば、局所に薬剤を運ぶ役割も担える」と期待はふくらみます。「なかでも、基礎医学との融合は模索されるべき。遺伝子や分子生物学的なマーカーを応用した、新しい診断技術の確立なども可能なはずです」。患者さんごとにオーダーメイドで行う、大腸がんの個別化治療に内視鏡が一役買う時代がやってくると思います。
広島大学で、大腸内視鏡の分野を一人でゼロから中心的に開拓してきた田中先生の情熱と努力の一つの結実といえるのが、2013年竣工予定の内視鏡センターです。消化管のほか、肝、胆、膵(すい)、気管支鏡もカバーし、田中先生が設計を担当しました。1,100m2という規模はもちろんのこと、設備、スタッフの技術など「どれをとっても、日本で有数だと思う。国立大学のなかでは内視鏡という分野を充実させているほうかな」と自信をのぞかせます。
「学問的な病態の解明、診断学、治療手技の開発や研究は大事。しかし、われわれ医師は、患者さんに貢献することが第一義」。検診の受診率の低さ、施設による内視鏡技術の格差は大きな課題。「何より大切な目標は大腸がん撲滅。そして、世界に誇る日本の内視鏡技術の情報を発信し、日本国民だけでなく、世界の人々に恩恵を与えていきたい」。新しいセンターを拠点に、田中先生の夢は尽きず、情熱と努力は絶え間なく続きます。
田中信治(たなか・しんじ)先生

広島大学病院 内視鏡診療科教授
1958年島根県生まれ。84年、広島大学医学部卒業後、同大医学部附属病院内科に研修医として入局。86年より北九州総合病院内科、広島赤十字・原爆病院内科、国立がんセンター病院(現・中央病院)内視鏡部研修医などを経て帰局。97年、ブラジル・リオグランデ州立大学消化器科客員教授。98年、広島大学医学部附属病院光学医療診療部助教授。2000年に同光学医療診療部部長、07年現職に至る。主な資格に、日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会、日本大腸肛門病学会、日本内科学会指導医、日本消化器がん検診学会認定医ほか。

