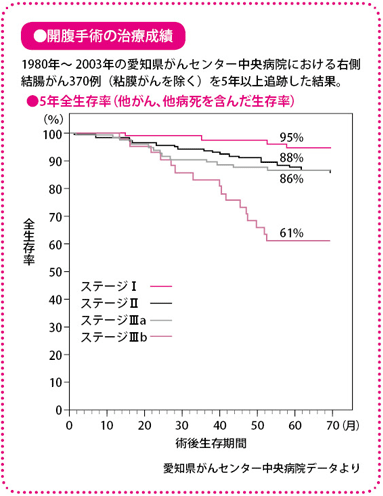結腸がんの「開腹手術」治療の進め方は?治療後の経過は?

- 金光幸秀(かねみつ・ゆきひで)先生
- 国立がん研究センター中央病院 大腸外科長
1965年岐阜県生まれ。90年名古屋大学医学部卒業後、市立四日市病院外科医員、名古屋大学医学部第二外科入局。95年より国立がんセンター中央病院外科レジデントを勤め、98年帰局。2000年に愛知県がんセンター中央病院消化器外科部を経て、13年国立がん研究センター中央病院大腸外科長に就任。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本大腸肛門病学会専門医、日本がん治療認定医。論文多数。
本記事は、株式会社法研が2012年6月26日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 大腸がん」より許諾を得て転載しています。
大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。
腹部を切開してがんを切除する
おなかをあけて、結腸がんを切除する治療法で、歴史が古く、確実な方法です。
「過不足なく取る」ことを追求し、根治を目指します。
進行がんで根治が可能なのは手術をおいてほかにない
がんの治療の3本柱は、手術(外科治療)、薬物療法(化学療法)、放射線療法ですが、進行した大腸がんの治療では、手術をおいてほかに根治を目指せる方法はありません。原発(げんぱつ)がん(最初にできたがん)だけでなく、再発や転移でも手術による根治の可能性があるのは、大腸がんの大きな特徴です。超早期のがんでは、内視鏡治療でも根治できますが、リンパ節転移の可能性のある段階では、がんとともに、一定のリンパ節を切除する手術が行われます。
●結腸がん手術の適応
| ・病変の大きさが2cm以上 |
| ・病変が粘膜下層の深い部分まで浸潤(しんじゅん) |
| ・病変が固有筋層を越えて浸潤 |
| ・遠隔転移のあるがん |
今の手術はできるだけ臓器を残し機能を温存する
結腸がんの手術の場合、根治を目指すには、二つの原則を守る必要があります。一つは「がんのある部分の腸を切除し、つなぎ合わせること」、もう一つは、「転移している、あるいは転移している可能性のあるリンパ節をすべて切除すること」です。最近では、それらに加え、手術後のQOL(生活の質)を考慮し、「臓器や神経などを温存して、機能をできる限り残すこと」も重視されるようになってきました。
大腸は「結腸」と「直腸」に分かれていますが、そのなかで直腸がんの手術は、時代とともに、その考え方ややり方が大きく進化を遂げています。
たとえば、1970年代半ばの手術では、おなかをあけ、直腸だけでなく、その周辺の臓器や組織までごっそり切除する「拡大手術」が行われていました。拡大手術の普及により、直腸がんで亡くなる患者さんはかなり減りましたが、その一方で、手術後におこる排尿障害や性機能障害などの合併症(臓器や神経などが失われたことによって生じる症状)で苦しむ患者さんが多くなりました。
80年代に入ると、がんをしっかり切除するという原則は当然のことながら、拡大手術のあとにおこる合併症を防ごうと、「機能温存手術」の取り組みが始まりました。
このような直腸がん手術の時代的な変遷に対し、結腸がんに対する標準的な手術法には大きな変化はありません。ただし、2000年以降になると、内視鏡治療や腹腔鏡(ふくくうきょう)下手術に代表されるような、患者さんにかかる負担を軽減させるための技術が登場し、そうした低侵襲(しんしゅう)手術が実際に試みられるようになりました。これらの手術の対象は、標準的な治療ガイドライン上では、超早期あるいは早期などに限られていますが、実際には、徐々に対象が広がる傾向にあります。
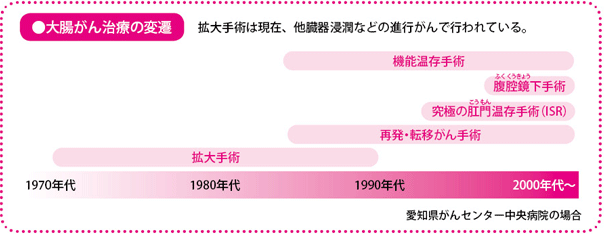
現在の結腸がんの標準治療は開腹手術
現在の結腸がんの標準治療は、開腹手術です。開腹手術とは、おなかを大きくあけて行う方法です。結腸がんの手術には腹腔鏡下手術もありますが、当施設(愛知県がんセンター中央病院)は「大腸癌(がん)治療ガイドライン(2010年版)」を遵守(じゅんしゅ)し、その適応どおりに、腹腔鏡下手術はステージ0~ステージIの患者さんに限っており、それ以外は開腹手術を行っています。
開腹手術のメリットは、執刀医が患部を直接見て、触った感覚を確認しながら治療が進められるところだと、私は考えています。患部を広く見渡せるため、出血などがあってもすばやく対応できます。
また、見逃されがちですが、結腸がんの開腹手術にかかる費用は、10日間(手術前2日間・手術後8日間)の入院で、約30数万円で、(健康保険が3割負担の場合)、使いきりの器具を使わなければならない腹腔鏡下手術に比べ、経済的であることも、実は大きなメリットといえます。
ある程度の大きさの傷口が必要になるため、患者さんへの体の負担の大きさ、手術後の痛みなどが予想されるデメリットとして指摘されますが、まだ証明はされていません。痛みについては、硬膜(こうまく)外麻酔や非ステロイド性消炎鎮痛薬などを使うことでやわらげることができます。手術中に患部が空気に触れるため、腸がまひしやすくなったり、腸と周辺の組織がくっつきやすくなったりして(癒着)、腸閉塞(へいそく)(腸の動きが停滞して内容物が通過できなくなる状態)という合併症がおこる可能性は、幾分高まることが指摘されていますが、明確ではありません。
●開腹手術のメリット・デメリット
メリット| 患部を直接確認でき、リンパ節郭清(かくせい)の取り残しがない |
| 術野が広く出血にすばやく対応できる |
| 手術時間が短く、手術費用が経済的である |
| 傷が大きく回復にやや時間がかかる |
| 合併症リスク(腸閉塞(へいそく)、感染症など)がやや高まる |
進行結腸がんの手術が多い愛知県がんセンター中央病院

実際に、当施設(愛知県がんセンター中央病院)で実施されている結腸がん手術の概要をみてみましょう。スタッフとしては、私を含め大腸を専門にする外科医3人が中心となって大腸がんの手術を実施しています。手術件数は年間330件余り、そのうち結腸がんの手術件数は90~120件です。2010年には88件の結腸がんの手術を行っていますが、「全国がん(成人病)センター協議会(全がん協)」のなかでも、ステージIVのかなり進行した結腸がんの手術の実施数が多いのが特徴です。
1980年~2003年に行った370例の結腸がんの開腹手術の治療成績(5年生存率)は、ステージIが100%、IIが95%、IIIaが91%、IIIbが70%です。これは結腸がんが死因となった場合の生存率で、ほかの病気などで亡くなった方は「死亡」に含まれていません。
がんのある場所から10cmずつ離して切除する
先に結腸がんの手術の二つの原則を述べましたが、それを実践するための具体的な手技は、「がんのある大腸と周囲の血管、リンパ節を丸ごと扇形に切除する」ことです。結腸がんの手術の方法(術式)は、たとえば上行(じょうこう)結腸がんなら「上行結腸切除術」、横行(おうこう)結腸がんなら「横行結腸切除術」というように、切除する腸の位置が名前につけられていますが、右側の結腸を大きく切除する場合には、別に「結腸右半切除術」といいます。それぞれの位置によって、切除する範囲は、「大腸癌取扱い規約(2009年1月・第7版補訂版)」で決められています。
詳細はのちほど触れますが、手術の進め方は大きく三つの段階に分かれます。
・第1段階「剥離(はくり)・授動(じゅどう)」
背中側にあって腸を動かないように固定している後腹膜から、腸をはがしてブラブラにする。
・第2段階「血管処理とリンパ節郭清(かくせい)」
がん細胞に栄養を送る血管(栄養血管)とその周囲のリンパ節を切除する。
・第3段階「縫合(吻合(ふんごう)」
腸管を切除して両端をつなぐ。
切除する結腸の長さは、栄養を送る血管とがんとの位置関係を考慮して決定されます。一般的には、10cm以上離れたところにリンパ節転移がおこることは非常にまれであることから、がんのある場所から口側・肛門(こうもん)側に10cmほど離したところで切り離します。最近では、7cmぐらいの短さで切除するという考え方も出てきていますが、がんを取り残す危険性がわずかながらあります。切る長さによって特に問題がおこらないのであれば、従来どおり10cmずつの長さで切除したほうが望ましいと考えます。
切除する長さは、全体で20cmぐらいになります。そんなに切ったら合併症がおこるのでは? と心配される方もいるかと思いますが、大腸(結腸と直腸)自体は2mもある大きな臓器であり、結腸の主な機能は水分の吸収なので、切除後に、なんらかの合併症に悩まされる可能性はほとんどありません。
進行度に応じて切除するリンパ節の範囲が異なる
続いて、リンパ節の切除について説明します。
結腸がんの場合、リンパ液の流れる方向に沿って、一定の法則でリンパ節転移がおこることがわかっています。まず、結腸の壁の周囲にある「腸管傍(ぼう)リンパ節」に転移し、次に少し離れたところにある「中間リンパ節」に広がります。さらに腸管に血液を送る血管の根元にある「主リンパ節」にたどり着きます。このようにがんが転移する法則にのっとり、予防的にリンパ節を切除することを、リンパ節郭清といいます。腸管傍リンパ節(第1群リンパ節)を郭清することをD1郭清、腸管傍リンパ節と中間リンパ節(第2群リンパ節)を郭清することをD2郭清、主リンパ節(第3群リンパ節)まで郭清することをD3郭清といいます。Dは郭清を意味する英語「Dissection」の略です。リンパ節郭清の範囲は、がんの進行度によって次のように決められています。
・ステージ0
粘膜内がん(Mがん)はリンパ節転移の可能性がないので郭清をせず、内視鏡治療だけで終わらせるのが一般的です。ただ、手術前の内視鏡検査による進行度の診断は100%ではありません。治療後の病理検査により、がんが粘膜下層にまで広がっていたり、がんの悪性度が高かったりすると、手術をしたほうがよいと判断されることもあります。その場合はD2郭清をします。・ステージI
手術前の診断で粘膜下層がん(SMがん)の可能性がある場合は、リンパ節への転移のリスクが約10%とされ、D2郭清が必要になります。同じくステージIの固有筋層に浸潤(しんじゅん)したがん(MPがん)でもD2郭清は必要です。D3郭清については、まだ科学的な根拠がないものの、見落としのリスクを考慮して、D3郭清まで行うケースが普通です。・ステージII
がんが固有筋層を越えて、漿膜(しょうまく)まで広がっていたり(SSがん)、がんが漿膜の表面に出ていたりする(SEがん)場合は、D3郭清となります。・ステージIII
D3郭清を行います。切除した主リンパ節にがん細胞が認められたときは、全身への転移の可能性が出てくるため、手術後に抗がん薬などによる化学療法が必要になります。
リンパ節郭清の数が多いほど再発・転移は少ない
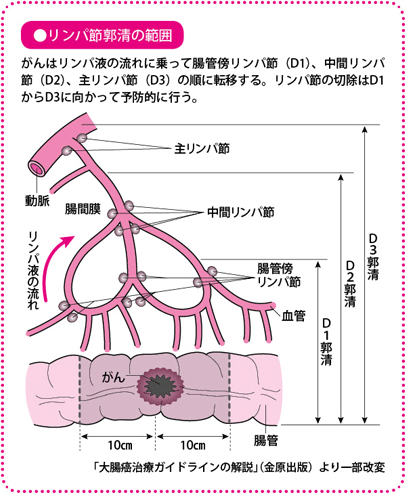
このように郭清範囲が決められているリンパ節ですが、手術で切除した範囲のなかにリンパ節が何個含まれているのか、その数は個人差もあって、なかなか知ることはできません。また、どのリンパ節にがんが転移しているかも、目で見ただけではわかりません。
しかし、転移の有無にかかわらずできるだけきれいに郭清したほうが、リンパ節転移の危険性は低くなり、再発を予防できると考えられています。幸い大腸がんでは、乳がんや子宮がんのリンパ浮腫(ふしゅ)(むくみが出る症状)のような、リンパ節郭清による合併症はみられません(足のつけ根のリンパ節を大きく郭清した場合は除く)。
このリンパ節郭清の個数について、以前、調べた結果では、施設や医師によって大きな差があり、10数個から30数個という開きがありました。当施設(愛知県がんセンター中央病院)では、1回の手術で、平均29個のリンパ節を郭清しています。当施設(愛知県がんセンター中央病院)の治療成績が全国的にみて高い要因の一つが、こうした丁寧なリンパ節郭清の仕方だと考えています。
手術前の検査とシミュレーションが大事
手術の大まかな流れをみてきましたが、こうした手技を確実に行いながら、私たち外科医が常に心がけていることは、がんを取り残すことなく、また、合併症がほとんど出ないように、つまり、「がんを過不足なく取る」ということです。大腸がんの場合は、肝臓や肺などに転移していても、手術で取りきることができれば、根治が期待できます。そういう意味では、ほかのがんと比べて外科医の役割はより大きく、重要となります。
がんを過不足なく取るために重要なのは、なんといっても手術前の検査とそれに基づくシミュレーションです。根治性を担保したうえで、機能を温存できるぎりぎりの切除範囲をいかに、手術前にイメージできるかに尽きるといえます。
内視鏡検査やCT(コンピュータ断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像法)などによる検査でわかった、病気の進行度や広がり方、場所、転移の有無などの情報を基に、どの範囲をどうやって切るか、リンパ節はどこまで取るか、機能を温存するためにはどうしたらいいかといった戦略を徹底的に練り上げます。
結腸がんの手術において、優秀とされる外科医のほとんどは、この手術前の検査と手術のシミュレーションを大変重視しています。事前のこの段階で実際の手術のよしあしが決まるといっても過言ではありません。
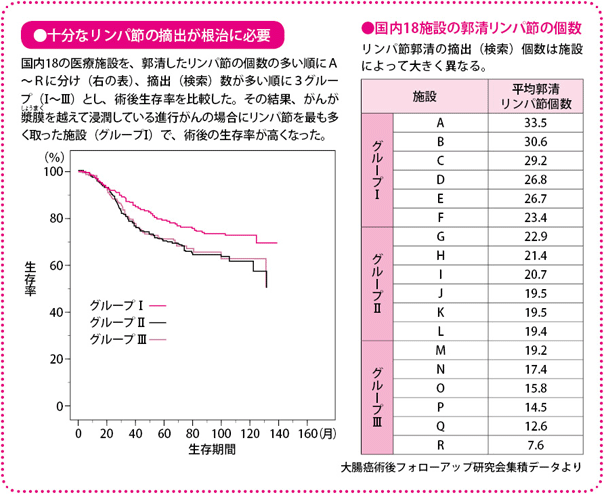
治療の進め方は?
全身麻酔をしたあと、がんを結腸とともに切除します。
合わせて周辺リンパ節も切除します。入院期間は10日ほどです。
血管とリンパ節を処理したのち腸を切除するという流れ
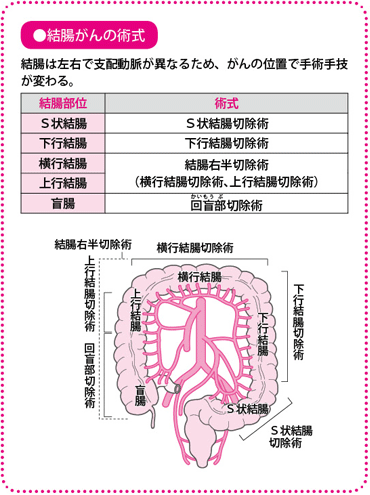
当施設(愛知県がんセンター中央病院)では、開腹手術の一般的な標準法とは異なる「中枢側血管剥離先行法」を行っています。腫瘍(しゅよう)部位に触れずに、中枢側の血管を先に処理することで、血液中に散布される腫瘍細胞を減らすという考え方です。ここでは上行結腸にできたがんを切除する治療の流れを簡単に示します。
まず、全身麻酔をかけたあと、みぞおちから恥骨(ちこつ)にかけてのおなかの皮膚を15~25cm切開します。おへそのところは横に避けて切開します。おなかの傷の大きさは人によって違い、太っている人の場合は傷がもう少し長くなることがあります。
おなかをあけると見えてくるのは、小腸です。結腸は小腸のうしろにあるので、まず小腸をおなかの外に出して治療のできる体勢に整えます。おなかの外に出した小腸は、乾かないように湿った布で包みます。
次に、腸間膜の処理に移ります。腸の周囲には腸間膜と呼ばれる薄い膜が何層にも重なって存在しています。腸を切除するためには、この膜を1枚1枚はさみや電気メスで切っていかなければなりません。とても細かい作業で、血管や隣接するすい臓などの臓器を傷つけないように、慎重に進めていきます。
続いて、切除する腸に栄養を送っている血管(栄養血管)を処理します。上行結腸とつながっているのは、上腸間膜動脈から枝分かれした右結腸動脈、回結腸動脈です。そこで右結腸動脈、回結腸動脈の分岐部をクリップではさみ、縛って出血をしないようにしてから、はさみで切り離します。
血管の処理と同時進行で、リンパ節郭清を行います。リンパ節は脂肪に埋もれているので見た目にはほとんどわかりません。そのため、リンパ節を一つひとつ郭清するのではなく、リンパ節が含まれる腸間膜の層を脂肪ごと取っていきます。この方法なら転移の可能性のあるリンパ節の取り残しを防ぐことができますし、直接触って、がん細胞をまき散らしてしまう危険も回避できます。
上行結腸の血管とリンパ節の処理が終わったら、次は横行結腸の処理です。先ほどと同じように栄養血管を処理しますが、横行結腸の場合は上腸間膜動脈と下腸間膜動脈の両方から中結腸動脈につながっているので、それらの根元を同じように処理しながらリンパ節郭清をします。
血管とリンパ節の処理が終わったら、腸を切り離して摘出し、残った腸をつなぎ合わせます。最後に腹筋、皮膚を縫い合わせたら手術は終了です。
手術時間は2~3時間 早期なら2時間以内
当施設(愛知県がんセンター中央病院)では開腹手術に要する時間は通常は2~3時間で、結腸右半切除手術に絞ると、かなり巨大な腫瘍も含めて手術の平均時間は154分です。時間はがんの進行度によっても違い、ステージIやIIであれば2時間はかかりません。出血量は50mLほどで、輸血が必要になることはほとんどありません。
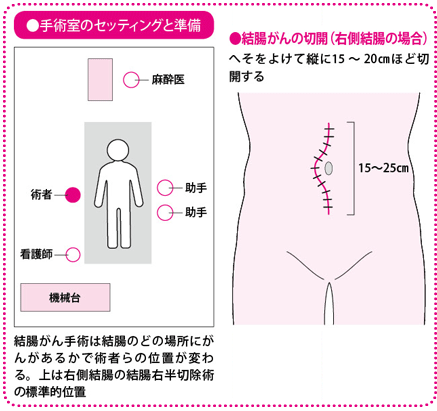
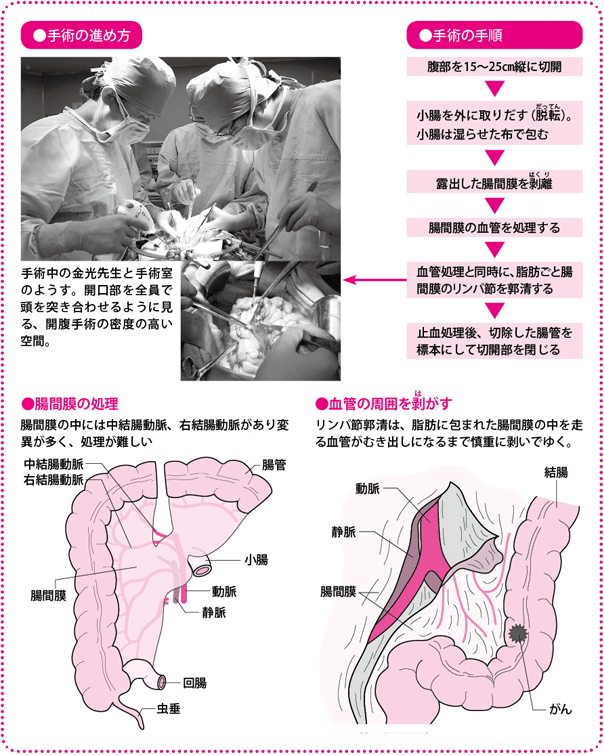
翌日から歩行を開始 痛みは麻酔と鎮痛薬で抑える
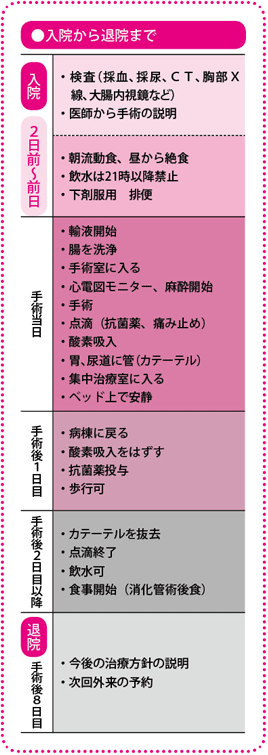
手術直後は個室の回復室で過ごし、翌日から一般病棟に移って、歩行を始めます。安静を保つより、早くにベッドから起きて動くことで、腸の動き始めも早まるので、血栓症や腸閉塞を予防することができます。体を動かすと呼吸機能も改善し、痰(たん)が出やすくなるので、誤嚥(ごえん)による肺炎もおこしにくくなります。
痛みは切開した傷がもたらすものです。そこで普通は硬膜外麻酔という背中から麻酔を注入する方法をとります。注入する管は手術前に入れておき、手術中から麻酔をかけ始めます。この硬膜外麻酔だけでは、呼吸をしたときやせきをしたとき、体位を変えたときなどに痛みが出ることがあります。その場合は、あわせて非ステロイド性消炎鎮痛薬を点滴で入れていきます。
腸が動き始めたことを確認できたら、水を飲んでもかまいません。排ガスや排便ができるようになったら、食事をとることも可能です。当施設(愛知県がんセンター中央病院)では食事は手術後3日目に「消化管術後食(お交じり:重湯の中に飯粒のまじったもの)」から始めます。4日目からは三分がゆ、7日目からは全がゆに変わります。
しっかりと食事がとれるようになれば、退院です。
治療後の経過は?
退院後は、再発や転移を早い段階でみつけるために定期検査を続けます。
5年間続けて問題がなければ、「根治」として治療は終了します。
進行度などによって定期検査の時期は変わる

どのがんもそうですが、がんを手術で切除しても、実は目には見えない微細ながんが残っていたり、リンパ液や血液に乗ってリンパ節、肝臓や肺などほかの臓器に転移していたりする可能性はゼロではありません。そこで、退院後も定期的に検査をして、再発や転移がないかの確認が必要となります。
治療後の定期検査では、血液検査と画像検査を行います。血液検査では、がん細胞が血液中に放出する物質(腫瘍マーカー)を測定します。画像検査では肺への転移をみるための胸部のX線検査、肝臓への転移をみるための腹部超音波検査やCT検査のほか、内視鏡検査も定期的に実施していきます。
通院するタイミングは、がんの進行度や治療からの期間などにより異なります。粘膜内がんや粘膜下層がんといった早期がんでは、6カ月~1年ごと、固有筋層まで進んだがんや、それ以降の進行がんでは、手術後2年目までは3~6カ月に1回、2年目以降5年目までは6カ月に1回、検査を受けてもらいます。
この定期検査は最低でも5年間は続けてもらいます。転移や再発の約8割が3年の間におこり、それ以降は急激に減りますが、まれにそれ以降に再発することもあるからです。そして5年間、再発がみられなかったら「根治」として、広い意味での結腸がんの治療は終了となります。
5年目以降は、再発というより新しく大腸がんができていないかを診(み)る検診的な意味合いで、毎年、検査を受けてもらいます。
合併症で重要なのは縫合不全と腸閉塞の二つ
大腸がんの手術後におこる合併症には、縫合不全、腸閉塞、創感染(傷口から細菌が入る)などがあります。結腸がんに限ると、当施設(愛知県がんセンター中央病院)のデータでは縫合不全が1.1%、腸閉塞が9.4%(1991~99年)でした。
結腸がんで最も問題となる合併症は、縫い合わせたところから内容物がもれ出す縫合不全です。そこに炎症がおこって、場合によっては膿(うみ)がたまることもあります。軽症なら飲食を中止して抗菌薬を点滴するだけですが、腹膜炎に至るほど重症になると、手術で一時的な人工肛門をつけなければなりません。ただ、そこまで深刻な縫合不全は、結腸がんではまれです。
結腸がん手術後に、一時的ですが便がゆるくなったり(軟便)、下痢や便秘などが生じたり、おなかが張ったりすることもあります。特に回盲部(かいもうぶ)と呼ばれる、小腸と結腸の境目を切除すると、排便回数が増加したり、便秘と下痢をくり返したりすることがわかっています。
同じ結腸でもがんができる部位で5年生存率が異なる
結腸がんは手術をしても合併症がおこりにくく、完全な切除がしやすいがんといえます。大腸癌研究会の「大腸癌全国登録」にみる結腸がんの部位ごとのステージ別累積5年生存率は、ステージ0、ステージIであればどの部分の結腸でも9割以上と高くなっています。一方、ステージIIIbになるとその割合はがくんと下がり、ほかの臓器に転移があるステージIVではさらに低くなります。結腸の部位ごとで比較すると、S状結腸が最も成績がよいことがわかります。