大腸がんは治りやすいがんとはいうものの「治療をすり抜けるがんが必ずいる」赤木由人先生
本記事は、株式会社法研が2012年6月26日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 大腸がん」より許諾を得て転載しています。
大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。
患者さんが納得できる治療をみつけて、提供するのが僕らの仕事。最終的には、患者さん自身の人生観なんです。

実家は四代続いた外科医。「美しい建物が好きでね、建築士を目指した時期もありましたが、医者はファミリービジネスですから」。赤木先生の表情に、一瞬、当時の葛藤(かっとう)がよぎったかに見えましたが、すぐに医学生時代の話へ。「学生のころから、専門は大腸か肛門と決めていました」。公衆衛生の疾患動向によれば、これから腸の疾患、特に大腸がんが増えるという予測もあり、「どうせやるなら患者さんが多い病気を」と興味をもったそうです。
当時、胃がんが花形の時代、大腸グループの志望者は少なく、進路はすんなり決まりました。以来、腸疾患はもちろん、婦人科系のがんや泌尿器のがんが腸まで広がった場合など「心臓および肺以外は何でもやる外科」で広い守備範囲の手術を行っています。そのなかでも、研鑽(けんさん)を積んできたのが骨盤内の直腸がんの手術であり、肛門温存手術です。赤木先生の所属する久留米大学病院は、特に肛門温存手術に関しては、白水和雄(しろうずかずお)教授(久留米大学外科)の方針のもと、国内でも屈指の実力を誇る医療機関となっています。「白水教授の長年の病理診断による、がんの切除範囲の綿密な検討があってこそ、今のわれわれの手技の完成度につながっています」。
赤木先生は、1990年代、分子生物学の研究に憧れ渡米した経験もあります。「そのころ、転移を征するものががんを征するといわれていました。現在、治療薬として用いられるようになった分子標的薬のベバシズマブの標的因子を研究していたんです」。
しかし、細胞レベルでおこる現象ほど、人間の体内でおこることは単純ではないことを痛感します。「がん細胞1個なら、どうとでも変えることはできる。しかし、それと同じように人間の中でおこっていることを変えることができるかというと、それは無理。いろいろな要素の影響があり、複雑を極めます。やはり、実際の臨床でどうすべきかが問われる」との思いを強くし、帰国しました。「ひょっとしたら、人の寿命は生まれたときから決まっているかもしれない。でも、患者さんの求める、その人に合った治療があるはず。それをみつけて、提供してあげるのが、僕たちの仕事だと思います」。
例えば、肛門を残すことで精神的な部分は満足しても、日常生活では機能低下を実感する、それでも納得して生きていけるかどうかは、結局患者さん自身の人生観にもかかわってきます。そのためにも、患者さんの話をよく聞き、自分の意見を押しつけない謙虚さを心がけています。
患者さんとの話には微妙な倫理観の問題を含むこともあります。「大腸がんには遺伝性のものもあります。僕のみている患者さんでいちばん若いのは中学3年生。実は父親もその数年前に僕が手術しました」。少女は、学校の健康診断時の貧血で精密検査を行い、大腸がんがみつかったといいます。今は、定期的な検査で経過観察。「お父さんは違うがんで亡くなり、親戚(しんせき)にもがんが多く、遺伝性が疑われます。本人に弟がいるので遺伝子検査をするように、お母さんには勧めているのですが」。強制できるものではなく、悩ましい限りです。
大腸がんは治りやすい性格のがんとはいうものの「約2割は治らないですからね。昔も今も転移・再発の予防が課題。いろいろな治療が試みられるけれど、がんも賢いですからね。治療をすり抜けるがんが必ずいるんです」とがん治療の難しさを改めて指摘します。「僕らができるのはあくまでも治療のお手伝い。患者さんも不安に思ったことは決してそのままにせず、理解し納得してから治療を受けることをお勧めします」。
お子さんたちはファミリービジネスの次世代に?「朝は早く夜は遅い。手術に明け暮れる生活を見て、誰がなるかといわれています(笑)」。
赤木由人(あかぎ・よしと)先生
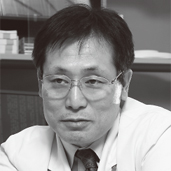
久留米大学 外科准教授
1957年、熊本県生まれ。85年、久留米大学医学部卒業後、同大第一外科入局。90年より社会保険久留米第一病院外科、大牟田市立病院外科を経て、96年渡米。テキサス州M.D.アンダーソンがんセンターに留学。98年に帰国し現職に至る。日本外科学会、日本消化器外科学会指導医・専門医、消化器がん外科治療認定医。日本大腸肛門病学会指導医、評議員ほか。

