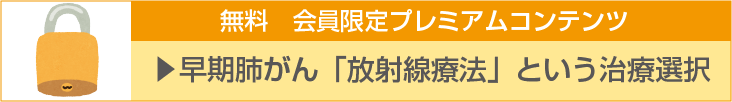肺がん治療「分子標的薬の力を垣間見た瞬間」光冨徹哉先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年3月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肺がん」より許諾を得て転載しています。
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
「この人の肺がんにはこの治療」と、今後、個別化医療はますます進み根治は難しくとも、がんとともに元気に生きられる人も出てきます。

「父親の背中を見て、というのだと、できすぎですか」。父は内科医。中学、高校と成績もよく、光冨先生にとって医師をめざすのは、特別なことではなく、自然なことだったのかもしれません。「素直に人の命を助ける仕事がしたかったし…」と、さりげなく続けます。
医学部卒業の時期が迫り、専門の診療科を選ぶ段になり、どうしてもと、こだわったのは「聴診器を持たない医者にはならない」、そして、「がんを専門にする」こと。「チャレンジ精神だったのでしょうかね、がんの医者になりたかったのは。今もそうですが、あのころはまだまだ難敵でしたから…」。そこで、がんを攻略するには内科か外科か、の選択です。「自分はどちらかというと内科向きか」と思いつつも、当時、日本には腫瘍内科という部門もなく、抗がん薬による化学療法は、生存期間は延びても、過酷な副作用が前面に取り沙汰されるものでした。
一方、実習で経験した手術ではチームとしての雰囲気が、中学、大学時代にやっていたサッカーを彷彿(ほうふつ)とさせました。「練習で泣いて試合で笑う。自分を殺して全体を生かす。協力して手術に集中し、あとはお疲れさまと肩をたたき合う。そのあたりがなじむような気がして」外科の道に進みます。
当初は消化器外科を志していた光冨先生は教授の「呼吸器やらんか」のひとことがきっかけで呼吸器へ。外科の本流である消化器からの転身に悩んだといいますが、最終的には「肺がんは手ごわい。相手にとって不足はない」と納得。その後、アメリカ留学。肺がんの研究室で分子生物学の手ほどきを受けました。「大学院の時代も基本的なものですが、がんの生物学的な研究を手がけたりしていたので、遺伝子レベルの話と臨床を関係づける仕事にはまった感じ。PCR法(微量のDNAを酵素反応によって大量に増やす方法。遺伝子の解明や臨床応用に貢献した技法)の開発に研究が後押しされた時期でもありました」。がんを生物学的に理解したうえで、一人ひとりの患者さんのがんの性格を知る。そこに効果的な攻撃法がみつかるはず、という戦略です。
多くの専門医が異口同音に語る肺がん治療の転換点、それが分子標的薬「イレッサ」の登場。光冨先生も例外ではありません。「こういうときに、よくお話に出す患者さんがいるんです」と紹介してくれたのがAさん。最初の手術は1995年、開胸したものの、がんが胸膜に散らばっている胸膜播種(はしゅ)。原発巣のみ切除して閉じ、化学療法を実施。約7年後に息切れなどの自覚症状も悪化、胸部のX線画像が吹雪のような状態になっていました。そこで、治験段階のイレッサをAさんの同意を得て使ってみると、「1週間後には、にこにこして屋上の家庭菜園で作業していましたからね」。これまで出合ったことのないような劇的な効果に「分子標的薬の力を垣間見た瞬間」でした。Aさんは、抗がん薬の種類や投与法を適宜かえながら、もう16年以上がんとの共存が続いています。
完全な治癒は難しい、でも、この肺がんにはこれと、ターゲットを絞って、有効な手段をみつけていけば「Aさんのように、がんとともに元気に生きられる人も出てきます。より慢性的な病気にしましょう、というのが目下の合言葉です。患者さんの伴走者として僕たちがせめてできるのは、そのくらいです」。
光冨先生いわく「がんはたぶん生物の宿命。無理に勝とうと思ってもだめ。髪が白くなるのと同じく老化の一種」。しかし、理不尽なのは、それが一様に年齢を経た人だけに現れるのではなく、子どもや若い世代にも現れてしまうことです。「がんの研究は日々進んでいます。気になることはなんでも相談してください。きっと医師だけでなくチームとしてお手伝いできると思います」。
光冨徹哉(みつどみ・てつや)先生

近畿大学医学部外科 呼吸器外科教授
1955年福岡県生まれ。80年九州大学医学部卒業。86年同大学大学院修了。89年米国国立癌研究所留学。産業医科大学第二外科、九州大学第二外科などを経て、95年より愛知県がんセンター中央病院胸部外科部長。2006年同センター副院長に就任。2012年5月、近畿大学医学部外科 呼吸器外科部門に就任。現職。