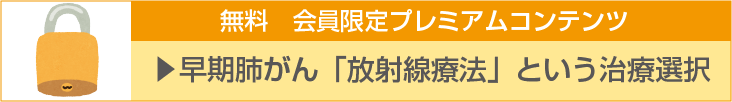麻酔から醒めた患者さんとの握手「この感動にまさるものはない」鈴木健司先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年3月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肺がん」より許諾を得て転載しています。
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
がんを取り除くのが第一。そのうえで体への負担をできる限り減らす高いクオリティを追求します。

剣道五段、文字どおり剛腕外科医の鈴木先生は、力強くこういいきります。「クオリティの低い手術をして平気な顔をしているような助手には、手術中といえど厳しく対応します。手術を受ける患者さんのためにはあたり前です」。
そこまでの気構えですから、当然、自分自身には常に厳しく、他施設で手術を断られた難しい症例も、患者さんや家族としっかり話をし、手術によるリスクを「共有できる」ならば引き受けています。
「難しい手術を重ねていっても地位は高くなりませんが、医療事故として報道されるリスクは高くなります」。それでも、なぜ危険とされる手術に挑むのか。「やはり、ほかの病院で、手術をしたら死にます、とまでいわれた患者さんの手術が成功し、『がんはうまく取れましたよ』と報告するときのご家族の反応ですね。涙ながらに『ありがとう』といってくださる。そして麻酔から醒(さ)めた患者さんと握手。この感動にまさるものはないからですよ」。
“そのとき”の患者さんやご家族のようすを思い浮かべ、鈴木先生の厳しいまなざしが一瞬、ゆるみます。
そんな鈴木先生も、最初から医師志望というわけではありませんでした。
高校時代は「砂漠の熱エネルギーを転換して利用できないものか」と壮大な夢をもち、大学受験は工学部志望。しかし、浪人時代に受けた模擬試験で、隣の席の受験生が防衛医科大学校の要綱を見て話しているのが聞こえてきたのです。「えっ、受験料がタダ? お金をもらいながら医者になれる?」。その席に座っていなかったら、年間200例以上をこなす肺がん手術の名医は生まれなかったわけです。
偶然の妙で入学した防衛医科大学校の学生気質は、「ハングリーかつ謙虚」。同級生みんなが、医学を崇高なものとして“畏(おそ)れ”をもっていました。「おかげで卒業証書、国家試験の合格免状をもらうころには、純粋に医者という職業に誇りをもって向き合っていました」。
縮小手術における「クオリティの高さ」を常に追求する一方で、まず強調するのは、当然のことながら「がんを完全に取り切ること」。そのためには「病理学的、放射線学的、臨床的にがんを的確に見極めて手術をすることが非常に大切です」。そして、一般に迎合して「傷の小ささ」だけを優先し、肝心のクオリティがあと回しになりがちな最近の風潮に警鐘を鳴らしています。
困難な手術にも挑み続ける鈴木先生は、その成果を積極的に学会などで発表。しかも、内科など異分野の医師たちが参加する学会でも最新情報を発信しています。「さまざまな先生方に呼吸器外科の現状を正しく理解してもらい、紹介していただくことで、救える患者さんを1人でも増やしたい」。
これまでに執刀した患者さんは約2500人。そして、3年前、母親が肺がんに。外科医は肉親を切って一人前とか。さすがの鈴木先生も緊張したのでは?「いや、まったくの平常心。震えるとかよく聞くんですけどね」と淡々とした表情。当時78歳、ヘビースモーカーだった母は息子の手によって肺葉を切除し、4日目で退院。その後は「ピンピンしています」。
剣道とともに野球にも熱中した少年時代、「ボールが止まって見えた。あのまま続けていたらイチローになれた」と豪語する一方で、五段の腕前ながら、剣道の話になると一転、謙虚に。「学生時代、剣道九段の方とお手合わせいただいたのですが、体力的には上なのにまったく打ち込めない。あの方は宮本武蔵(みやもとむさし)です。気がついたら隅っこに追いやられて……グサッ。非常に貴重な経験でした。こういう世界は、手術にも必ずあると思います」。竹刀がメスに変わっても、選んだ道を極めようとする姿勢は変わっていません。
鈴木健司(すずき・けんじ)先生
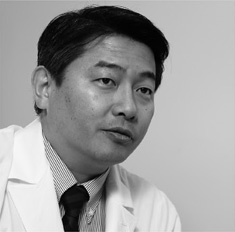
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器外科教授
1965年東京都生まれ。90年防衛医科大学校卒業。95年国立がんセンター東病院レジデント、99年国立がんセンター中央病院スタッフドクター、2007年同病院医長を経て、08年より現職。