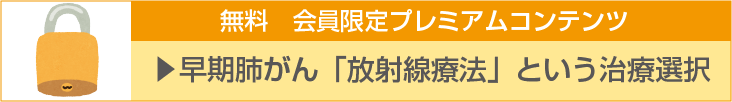安心して最期を迎えられる社会こそ成熟した社会「その人にとっての最善は何か」中川和彦先生インタビュー
本記事は、株式会社法研が2012年3月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 肺がん」より許諾を得て転載しています。
肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。
新薬の開発から看取りまで、患者さんの傍らに寄り添い、最善の診療を提供できる腫瘍内科医を育てていきたい。
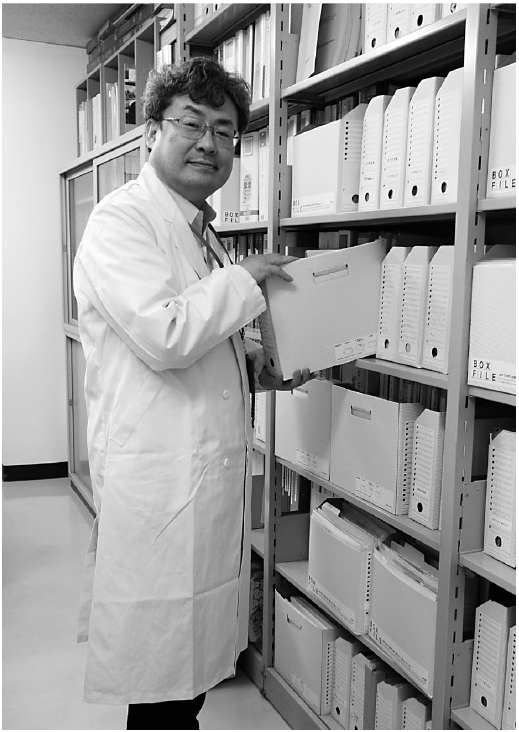
近畿大学医学部腫瘍内科は、日本でももっとも早い時期に、初代教授福岡正博(ふくおかまさひろ)先生のもと、開設されました。「日本全体のがんの薬物療法を考えられる医師、主たるがんを横断的に診(み)ることができる医師。腫瘍内科医らしい腫瘍内科医を育てる」。福岡先生とともに掲げた目標実現のために、今は、中川先生が陣頭指揮を執ります。「診療と教育を担う大学として、肺がんから始まり、今では消化器、乳腺、頭頸部(とうけいぶ)、骨軟部から原因不明のがんまで、幅広く同時に扱えるようになっています。そのなかで、新薬の開発から看取(みと)りまで、最善の診療を提供できる腫瘍内科医を力強く根づかせなくてはいけません」と中川先生は、自負と熱意をほとばしらせます。
もともとは「患者さんのそばに仕えるファミリードクターになりたかった」中川先生が、がんの薬物療法、とくに肺がんとかかわるようになったのは、卒業して初めて受けもった患者さんがきっかけでした。
1983年、シスプラチン承認の、その年に出会った36歳の男性。III期の肺がんでした。手術をしましたが、間もなく再発。まだシスプラチンの標準的な投与方法を模索している時期で、「恐る恐る点滴をしたのを覚えています」。3年後、ほかの施設に移っていた中川先生に訃報が届きます。当時の担当医が解剖のための献体をお願いしたところ「中川先生がつき添ってくれるなら」との奥様の希望で、急きょ中川先生が立ち会うことに。「薄暗い解剖室に入ったとたん、奥様は私に抱きついてこられ、人目を憚(はばか)らず泣きだされました」。
肺がんを専門とする内科医がほとんどいない現実を思い、それなら自分が、と心を決め、国立がんセンター(当時)に国内留学。その後、羽曳野(はびきの)病院で4年間、福岡先生とともにみっちり臨床と基礎を結ぶ研究を実践。さらに海外留学で研鑽(けんさん)を積み、近畿大学へ。
質の高い臨床研究を追求し続ける一方で、中川先生が日本のがん医療に求めるのは成熟した死生観。日本社会全体の課題とも考えています。医師だけでなく、あらゆる職種、患者さんや家族、さらには患者予備群としての一般の人々が、もっと「死」と向き合い、「死」を受け容(い)れる社会であってほしいといいます。「治療法は進み、決して希望は失うべきではない。しかし、今、国民の3分の1ががんで亡くなっていきます。人生の最期をタブー視していては、充実した生をまっとうすることはできません。緩和ケアもある意味合いにおいては積極的な治療法。見捨てるわけではないのです」。
信頼し合い、安心して最期を迎えられる社会こそ成熟した社会であり「社会全体で生と死の問題に向き合う。命にかかわる病気をもつ人とその家族を支えるのは私たちであり、みなさんなんです」。そのために必要なものは「勇気」と中川先生はいいます。「勇気あるひとこと、勇気ある1つの行為。それを積み重ねていくことで一歩一歩成熟した社会に近づいていくのではないでしょうか」。
顔の見える地域連携への取り組みもその一環です。在宅で緩和ケアを行っている医師や看護師、ホスピスや中核病院の医療スタッフやケースワーカーなど広い職種が参加する、南大阪キャンサーネットワークというグループを組織し、年に4回の集まりをもっています。
また、自身が会長を務めることになる第10回日本臨床腫瘍学会学術集会では、アジア諸国との国際的な連携や市民参加による地域の活性化など新しい試みに挑戦します。
「最前線の研究と看取りは表裏一体。緩和ケアに携わったときも、最期を間近に控えた患者さんの傍らで、その人にとっての最善は何か。それを考えられるのが、私たちのめざす腫瘍内科医です」。
中川和彦(なかがわ・かずひこ)先生
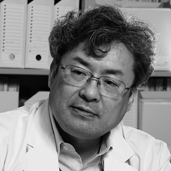
近畿大学医学部 腫瘍内科教授
1957年、熊本県生まれ。1983年熊本大学医学部卒業。国立がんセンター研究所、同中央病院内科を経て、90年大阪府立羽曳野病院第二内科、97年近畿大学医学部第四内科、2002年同大医学部腫瘍内科、03年同大医学部腫瘍内科助教授(当時)、07年より現職。がんの新薬、分子標的薬治療など臨床試験に積極的に取り組み、日本における質の高い腫瘍内科の確立をめざす。